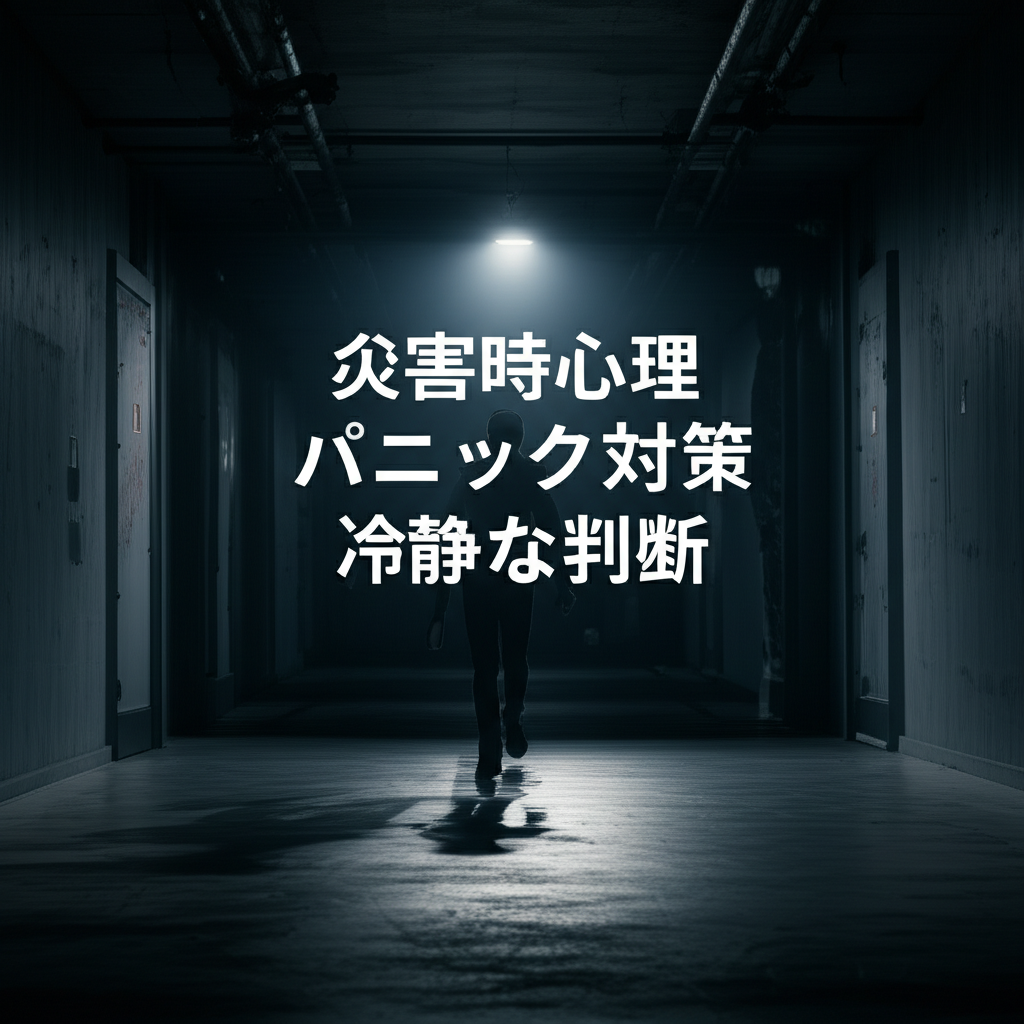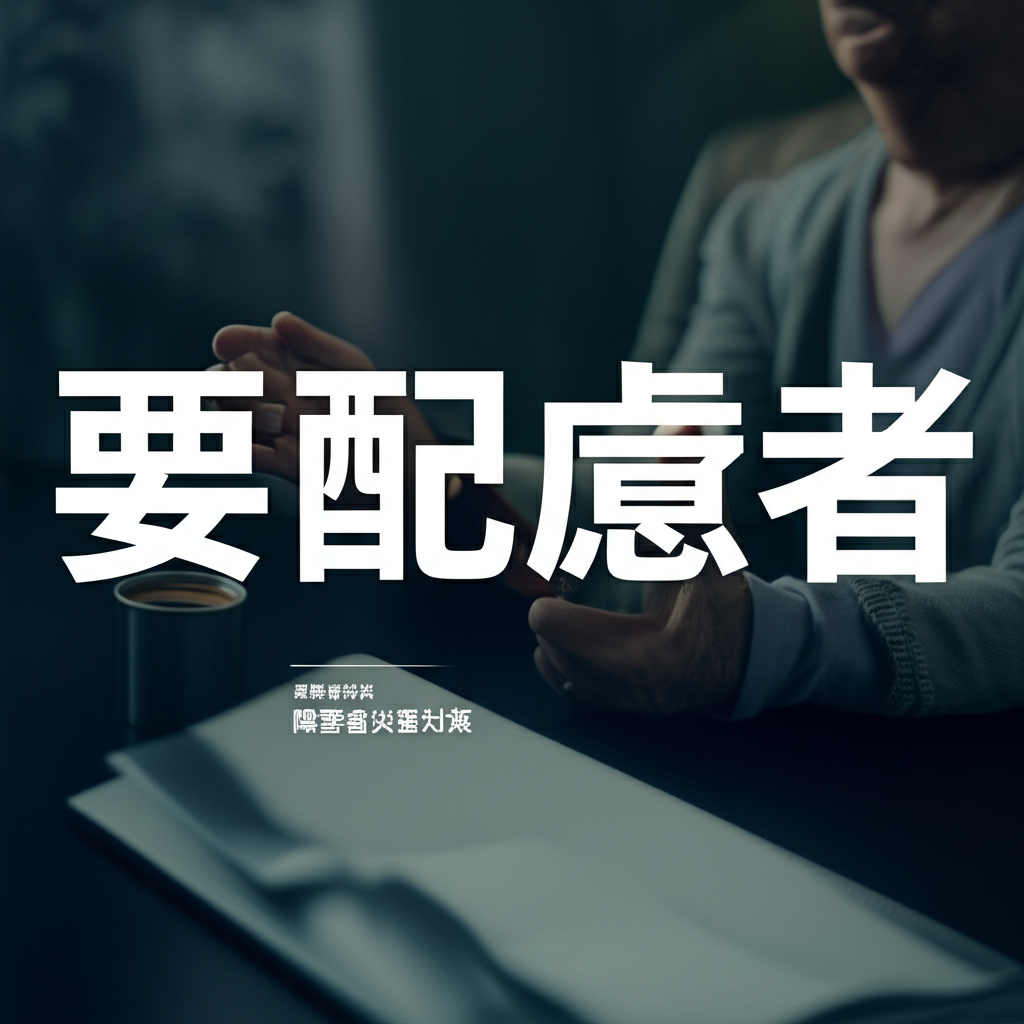
はじめに:要配慮者の災害対策はなぜ重要なのか
災害大国日本において、誰もが被災する可能性があります。しかし、同じ災害でも被害の程度は人によって大きく異なります。特に、高齢者、障害者、難病患者、乳幼児、妊産婦、外国人などの方である要配慮者は、災害時により困難な状況に直面する可能性が高いのです。
現在、65歳以上の高齢者がいる世帯は全世帯の約半分という統計がでており、一人暮らしの高齢者が増加傾向にあるため、災害時の備えがより重要になってきています。また、NHKが行った障害者と防災に関するアンケート調査によると、アンケートに答えた876名のうち、災害への不安を感じている方が87%と高い水準という結果も出ており、当事者の不安の高さが浮き彫りになっています。
この記事では、家族に高齢者や障害者がいる主婦の皆さんに向けて、要配慮者を災害から守るための具体的な対策を5つのポイントでお伝えします。
要配慮者とは?避難行動要支援者との違いを理解しよう
要配慮者の定義と範囲
平成25年6月の災害対策基本法の一部改正により、高齢者、障害者、乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する方(要配慮者)のうち、災害発生時の避難等に特に支援を要する方の名簿(避難行動要支援者名簿)の作成を義務付けること等が規定されました。
要配慮者と避難行動要支援者は、しばしば混同されがちですが、実は異なる概念です。
– 要配慮者:災害時に何らかの配慮が必要な人(高齢者、障害者、難病患者、妊産婦、乳幼児、外国人など)
– 避難行動要支援者:要配慮者のうち、特に避難時に支援が必要な人
避難行動要支援者とは、要配慮者(災害時要援護者)のうち、自ら避難することが困難な方であって、特に支援を要する方とされており、各市町村によって具体的な対象者が定められています。
具体的な対象者の例
多くの自治体では、以下のような基準で避難行動要支援者を定めています:
– 介護保険制度の要介護認定者(要介護3以上)
– 身体障害者手帳を所持する者(1・2級)
– 精神障害者保健福祉手帳1級の方
– 療育手帳A判定の方
– 一人暮らしの高齢者(75歳以上など)
ただし、これらの基準は自治体によって異なるため、お住まいの市町村に確認することが重要です。
ポイント1:避難行動要支援者名簿への登録とそのメリット
名簿登録の重要性
災害時にひとりで避難が難しい人は「避難行動要支援者名簿」に登録しましょう。この名簿は、災害時の安否確認や避難支援に活用される非常に重要なツールです。
平常時から、名簿情報の提供に同意された方の情報等を、避難支援等関係者である警察、消防、民生児童委員、社会福祉協議会(自主防災組織・自治会)等に提供し、災害時の避難支援や平常時からの避難体制作りなどに活用します。
名簿登録のメリット
1. 優先的な安否確認:災害時に地域の支援者が優先的に安否確認を行います
2. 避難支援の確保:事前に支援者が把握されているため、迅速な避難支援が受けられます
3. 必要な支援の理解:障害の特性や必要な配慮について支援者が事前に理解できます
4. 孤立防止:日常的な見守り体制により、災害時の孤立を防ぎます
プライバシーの保護
名簿登録に不安を感じる方もいらっしゃいますが、名簿情報等については、担当する地域の支援者に限り提供し、個人情報が無用に共有、利用されないよう指導します。また、支援者に対し、守秘義務が課せられていることの説明を行い、個人情報の適正管理を図りますと定められており、適切な管理がなされています。
ポイント2:個別避難計画の作成~一人ひとりに合わせた避難プラン
個別避難計画とは何か
個別避難計画は避難行動要支援者がスムーズに避難できるよう、事前に一人ひとりの状況に合わせた避難方法等を記載する計画です。これは、画一的な対応ではなく、個人の特性や状況に応じてオーダーメイドで作成される避難計画です。
計画に含めるべき内容
個別避難計画には以下の項目を盛り込むことが重要です:
1. 本人の基本情報
– 氏名、住所、生年月日
– 緊急連絡先(家族、かかりつけ医など)
– 障害の種類や程度、必要な介助内容
2. 避難支援者の情報
– 主担当者、副担当者の連絡先
– 支援可能な時間帯
3. 避難場所と経路
– 第1候補、第2候補の避難場所
– 車椅子等でも通行可能な避難経路
– 移動手段(徒歩、車椅子、車など)
4. 必要な支援内容
– 移動時の介助方法
– コミュニケーション方法
– 医療機器の取り扱い
家族での話し合いが重要
ご家族や地域の支援者と話し合い作成することが効果的ですとされているように、家族全員で定期的に計画を見直し、実際に避難経路を歩いてみることが大切です。
ポイント3:要配慮者のための防災グッズ選び~一般的なグッズとの違い
高齢者向け防災グッズの特徴
高齢者の方の防災グッズは、一般的なものとは異なる配慮が必要です。高齢者の場合は、一般的な防災グッズだけでなく、持病の薬や健康保険証、老眼鏡などの自身の体調や環境にあわせたグッズも忘れないようにすることが重要です。
#### 必須アイテム
1. 医薬品関連
– 持病の薬が不足すると命にかかわることもあるため、非常用に最低3日分、できれば7日分を備えておく
– お薬手帳のコピー
– 健康保険証のコピー
2. 身体機能をサポートするもの
– 老眼鏡(予備も含めて)
– 補聴器と電池
– 携帯用の杖やおむつ
– 入れ歯と洗浄剤
3. 口腔ケア用品
– 口腔ケアはシートタイプであれば、水のゆすぎが不要で便利
障害者向け防災グッズの配慮点
障害の種類によって必要なアイテムが大きく異なります。
#### 視覚障害がある方
– 白杖(予備も含めて)
– 音声機能付きラジオ
– 点字器や点字用紙
– 障害者手帳、おくすり手帳
#### 聴覚障害がある方
– 筆談用のメモ帳とペン
– 補聴器の電池
– 聴覚障害者であることを示すカード
– スマートフォン(文字による情報収集のため)
#### 精神障害がある方
精神障害がある方は、災害時に心理的ストレスがかかり、不安や苛立ち、不眠など精神障害が現れる可能性があります。そのため、以下のものを準備しておきましょう:
– いつも飲んでいる薬
– 障害者手帳や薬や内容や効果がわかる薬剤情報提供書
– 困った際の医療機関の連絡先
#### 知的障害がある方
知的障害がある方は、正しい情報を理解したり、伝えることが難しい可能性があります。以下のようなものを準備しておくと安心です:
– ヘルプカードなど、名前や住所電話番号などが記載されているもの
– おもちゃや本など、いつも使っていて落ち着くもの
防災グッズの収納のコツ
高齢者の場合、重い荷物を持ち運ぶのが難しいことが多いため、軽量で持ち運びやすいリュックタイプの防災袋が適しています。また、避難経路となる玄関付近に防災袋を配置しておけば、慌てずに行動できるため安心です。
ポイント4:家庭内での安全対策と避難計画の立て方
家庭内の安全確保
災害時に怪我をしてしまっては避難どころではありません。特に要配慮者がいる家庭では、以下の対策が重要です。
#### 転倒防止対策
転倒防止のために、大きな家具はL字金具や突っ張り棒などを使って固定します。家具の下敷きになったり、通路を塞いだりするリスクを減らします。
高齢者や障害者の方は特に転倒リスクが高いため、以下の点にも注意しましょう:
– 寝室には背の高い家具を置かない
– ガラス製品は高い場所に置かない
– 廊下や階段に物を置かない
#### 避難経路の確保
災害が発生したときにすぐ避難できるように、ドアや玄関周りをすっきりさせるようにしましょう。また、車いすを使用している場合は、より広い動線の確保が必要です。
避難計画の作成
#### 避難場所の確認
避難先は「指定避難場所」が基本です。指定避難場所は、災害の種類によって異なることがあるので、防災マップまたはYahoo!が提供する避難場所マップで確認しておきましょう。
ただし、要配慮者の場合は一般の避難所だけでなく、福祉避難所についても確認しておくことが重要です。
#### 避難のタイミング
高齢者の方々や妊婦さん、乳幼児がいる家庭は避難に時間がかかることが予想されるため、レベル3のタイミングで早めに避難を開始することが望ましいとされています。
警戒レベルと避難行動の関係:
– 警戒レベル3:高齢者等避難(高齢者や障害者など避難に時間がかかる人が避難開始)
– 警戒レベル4:避難指示(危険な場所から全員避難)
– 警戒レベル5:緊急安全確保(すでに災害が発生している可能性が高い)
#### 避難時のシミュレーション
高齢者は足腰が弱っていることが多いので、どうしても避難に時間がかかります。災害時に効率よく避難するためには、「早めの行動」「避難時のシミュレーション」が重要です。
実際に家族で避難経路を歩いてみて、所要時間や危険箇所を確認しておきましょう。
ポイント5:地域との連携と日頃からの準備
地域とのつながりの重要性
普段から近所や地域の人と交流しておくと、災害時に効果的な支援が期待できます。特に要配慮者がいる家庭では、地域とのつながりが命を救うことにもつながります。
#### 近所づきあいを大切に
「あの家には在宅介護中のおばあちゃんがいる」「ひとり暮らしのおじいさんがいる」などと気にしてもらえるでしょう。避難時の誘導やサポートがあるか・ないかでは、精神的負担が大きく違います。
日頃から以下のことを心がけましょう:
– 挨拶を欠かさない
– 自治会活動に参加する
– 近所の方に家族構成を知ってもらう
防災訓練への参加
防災訓練に参加すると、いざという時にどのような行動をとればよいのかが明確になります。ピンチの時にも、適切な行動がとれるようになるのです。
また、防災訓練に参加すると、防災の知識が身に付くだけでなく、地域の人と顔見知りになることができますので、積極的に参加しましょう。
日頃からやっておきたいこと
#### 定期的な見直し
高齢者世帯の場合は、普段から家族で話し合うなど、1年に1回は備蓄品を確認し合う時間を持ちましょう。
– 薬の期限切れチェック
– 防災グッズの動作確認
– 避難計画の見直し
– 緊急連絡先の更新
#### 情報収集手段の確保
要配慮者の中には、普段はテレビや新聞で情報を得ている高齢者は、携帯電話やスマホによる情報収集を素早くできない可能性がありますという方もいます。そのため、複数の情報収集手段を準備しておくことが重要です。
– ラジオ(電池式・手回し式)
– スマートフォン(家族が使い方を教える)
– 近所との情報共有体制
実践例:我が家の要配慮者対策体験談
Aさん家族の事例(要介護3の祖母と同居)
Aさんは、要介護3の祖母と同居する3世代家族です。祖母は歩行が困難で、普段は車椅子を使用しています。
実践した対策:
1. 避難行動要支援者名簿に登録:市役所で手続きを行い、民生委員の方と顔合わせ
2. 個別避難計画の作成:家族と民生委員で話し合い、車での避難計画を策定
3. 防災グッズの準備:祖母専用の薬と介護用品を入れた非常袋を作成
4. 家庭内安全対策:寝室の家具を固定し、車椅子での移動経路を確保
結果:
台風による避難勧告が出た際、事前に計画していた通りスムーズに避難できました。避難所でも民生委員の方が気にかけてくださり、祖母も安心して過ごすことができたそうです。
Bさん家族の事例(聴覚障害のある息子さんがいる家族)
Bさんの息子さん(中学生)は生まれつき聴覚に障害があり、手話でコミュニケーションを取っています。
実践した対策:
1. ヘルプカードの作成:聴覚障害があることと必要な配慮を記載
2. 筆談用具の準備:防災袋に筆談ボードとマーカーを常備
3. 地域への理解促進:自治会で聴覚障害についての理解を深める勉強会を開催
4. 避難所との事前相談:指定避難所に聴覚障害者への配慮について相談
工夫した点:
– スマートフォンの災害情報アプリを活用
– 家族間での安否確認方法を事前に決定(LINEなど)
– 避難時の役割分担を家族で明確化
考察:要配慮者災害対策の課題と今後の展望
現在の課題
要配慮者の災害対策には、まだまだ多くの課題があります。
#### 情報格差の問題
ハザードマップを確認した人は3割から4割程度と低くなってしまっています。その理由はハザードマップ自体が自分に分かる形になっていないことや、そもそもハザードマップを知らないという方がいるからです。
#### 避難所での課題
「行政のマニュアルでは、要援護者も、一般の避難所に行ってから福祉避難所へ移動になっているが負担が大きい。直接、福祉避難所へ行きたい」という声もあり、避難所運営の改善が求められています。
今後の展望
#### 合理的配慮の推進
障害者差別解消法が施行されたことから、「今までどおり…」は通用しない。行政が指定する避難経路、避難所、仮設住宅、避難物資配布方法等の見直し、社会的障害の除去と合理的配慮が必要不可欠とされています。
#### 福祉避難所の充実
年々、福祉避難所数は増加しているが、理解している人が少ないことから知名度を上げることが必要です。今後は、福祉避難所の拡充と周知が重要な課題となります。
#### テクノロジーの活用
災害情報の多言語化や、視覚・聴覚障害者向けのアプリ開発など、テクノロジーを活用した情報提供の改善も期待されます。
まとめ:今日から始める要配慮者のための災害対策
要配慮者の災害対策は、「いつか」ではなく「今すぐ」始めることが大切です。災害はいつ起こるかわからず、後悔してからでは遅いのです。
今日からできること5つのステップ
1. まずは情報収集:お住まいの市町村の要配慮者支援制度を調べる
2. 名簿登録の検討:避難行動要支援者名簿への登録を検討する
3. 防災グッズの見直し:一般的なものに加え、個人に特化したアイテムを追加
4. 家族での話し合い:避難計画と役割分担について話し合う
5. 地域とのつながり:近所の方との関係づくりから始める
継続的な取り組みが重要
災害対策は一度やって終わりではありません。定期的な見直しと更新が必要です。
– 年1回の全体見直し:防災グッズ、避難計画、連絡先の確認
– 季節ごとの点検:薬の期限、電池の残量など
– 訓練への参加:地域の防災訓練に積極的に参加
家族の絆が最大の防災力
別居している場合は、電話での声掛けだけではなく、里帰りのように実際に親の住んでいる環境をチェックして、何かあったときには近所の方やかかりつけ医、民生委員に相談してみるのも良いでしょう。
要配慮者の災害対策で最も重要なのは、家族の結束と地域のつながりです。一人では難しいことも、みんなで力を合わせれば乗り越えることができます。
災害から大切な家族を守るために、今日からできることから始めてみませんか。小さな一歩が、いざという時の大きな安心につながります。あなたの行動が、家族全員の命を守る第一歩となるのです。
災害対策は「備えあれば憂いなし」という言葉通り、事前の準備がすべてです。要配慮者がいる家庭だからこそ、より丁寧で具体的な対策が必要になります。この記事でご紹介した5つのポイントを参考に、ご家族に合った災害対策を構築してください。
家族の笑顔と安全な暮らしを守るために、今日から行動を始めましょう。