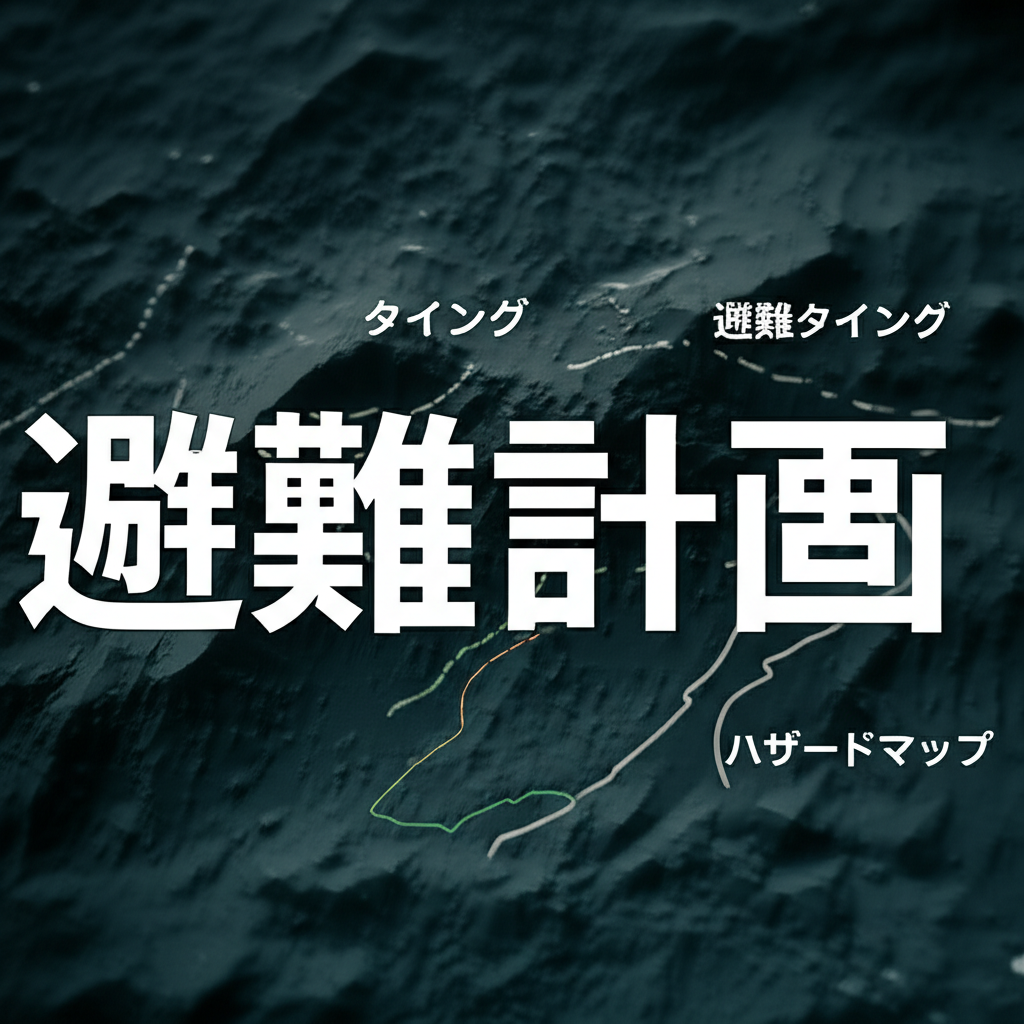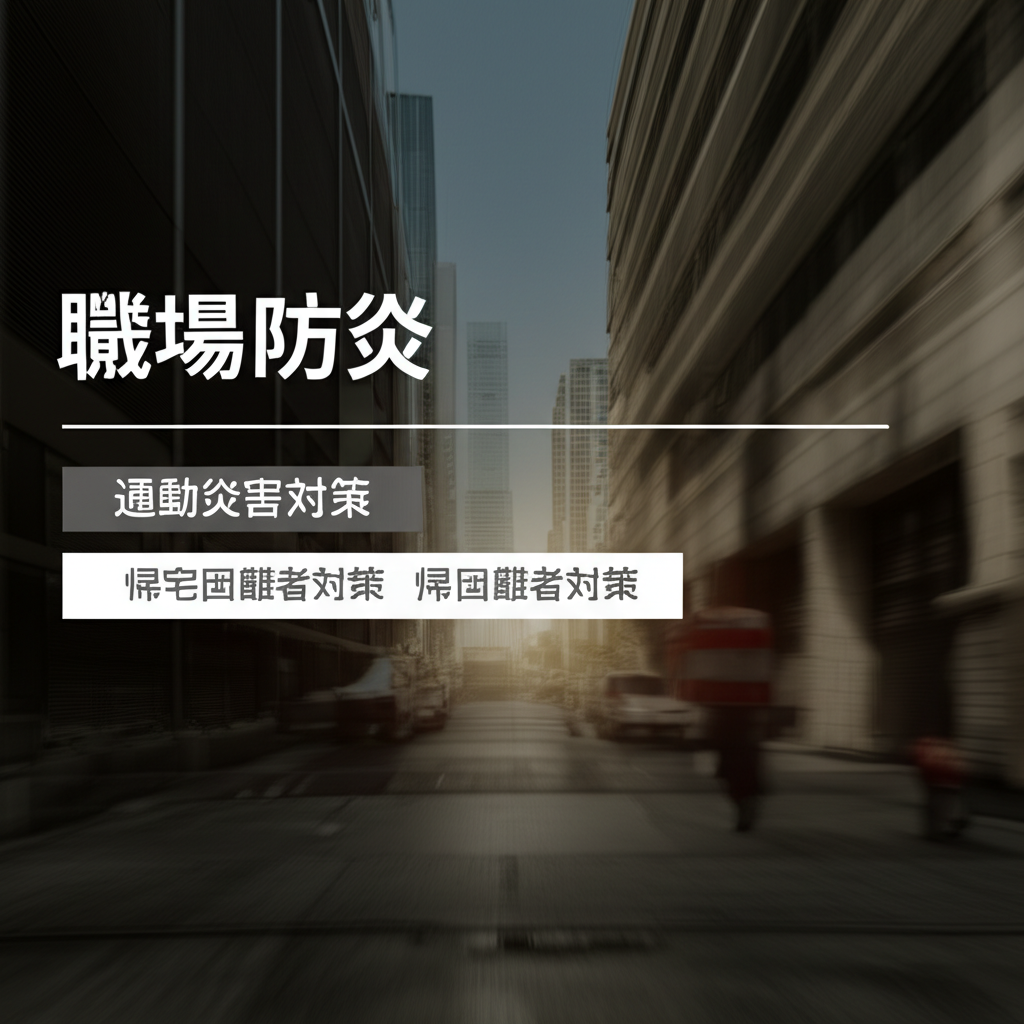災害大国日本で注目される「在宅避難」という選択肢
こんにちは、皆さん。日々家族の安全を第一に考えていらっしゃる主婦の皆様、お疲れ様です。近年、地震や台風、豪雨などの自然災害が頻発する中で、「在宅避難」という言葉を耳にする機会が増えたのではないでしょうか。
実は、・避難者抑制のため、自宅が無事な者は避難所への避難を控え、自宅で避難生活を送ることを原則としているという自治体が増えています。これは決して「避難所に行かなくていい」という意味ではなく、自宅の安全が確保できる場合に限り、在宅避難という選択肢があるということなのです。
今回は、在宅避難の判断基準から必要な防災グッズ、実際の対応方法まで、家族を守るために知っておきたい知識を詳しくお伝えします。ぜひブックマークして、いざという時の参考にしてくださいね。
在宅避難とは?その判断基準を知ろう
在宅避難の基本的な考え方
在宅避難とは、災害発生時に避難所ではなく自宅で避難生活を送ることです。自宅の被害がない、または軽微であり、自身や家族にも怪我がない場合には在宅避難を選択するケースがあります。
この在宅避難という選択肢が注目される背景には、避難所の収容限界や感染症対策、そして住み慣れた環境での生活継続というメリットがあります。しかし、重要なのは「自宅の安全が確保されている」ことが大前提だということです。
在宅避難の判断チェックポイント
災害が発生した際、在宅避難するかどうかは以下のポイントで判断しましょう:
【地震の場合】
– 自宅の家屋に倒壊などの被害がないか
– 隣家の倒壊・火災などで自宅に影響があるか
– 建物の構造に問題がないか
– ライフラインの状況はどうか
【風水害の場合】
– 自宅が水害や土砂災害の被害を受け、生活できないか
– 周辺の河川の氾濫リスクはないか
– 土砂災害警戒区域に含まれていないか
【共通項目】
– 日常生活をするうえで、他人のサポートが必要であるか
– 家族全員の身体的・精神的な状態は安定しているか
これらの項目をしっかりとチェックし、一つでも危険と判断される場合は、迷わず避難所への避難を選択してください。
在宅避難のメリット・デメリットを理解する
在宅避難のメリット
在宅避難では、プライバシーが保護されているため心理的安全性を確保でき、生活空間が普段と変わらないためストレスを感じにくく、生活環境をコントロールしやすいメリットがあります。
具体的なメリットとしては:
1. プライバシーの確保:家族だけの空間で、他人に気を使うことなく過ごせます
2. ストレスの軽減:慣れ親しんだ環境で、普段に近い生活リズムを維持できます
3. ペットとの同居:避難所では難しいペットとの生活が継続できます
4. 感染症リスクの低減:避難所での混雑を避けることで、感染症のリスクも少なくなります
5. 子どもへの負担軽減:特に小さなお子さんにとって、環境の変化によるストレスを最小限に抑えられます
在宅避難のデメリットと対策
一方で、デメリットとしては、停電や断水が起きた場合にライフラインを確保できない点が挙げられます。また、生活物資・支援物資は避難所で配布されることが一般的であるため、物資が不足するリスクもあります。
主なデメリット:
1. ライフラインの確保困難:電気、水道、ガスが止まった場合の対応が必要
2. 物資不足のリスク:食料や日用品の備蓄が重要
3. 情報収集の困難さ:災害情報の入手が遅れる可能性
4. 孤立感:一人暮らしの場合など、精神的な不安が増大する可能性
これらのデメリットを理解した上で、事前の準備をしっかりと行うことが在宅避難成功の鍵となります。
在宅避難に必要な防災グッズ完全リスト
基本の備蓄品(最低3日分、理想は1週間分)
最低でも家族の人数×3日分、可能であれば1週間分は用意しておく必要があります。実際に近年は、高層マンションでの電気システムの水没で復旧までに時間がかかったことから、7日程度の備蓄を呼びかけるようになりましたとされています。
【食料・飲料水】
– 飲料水:1人1日3リットル×家族人数×7日分
– 非常食:米、パン、麺類などの主食
– 缶詰・レトルト食品
– 栄養補助食品・お菓子類
– 乳幼児用ミルク・離乳食(該当する場合)
【調理・生活用品】
– カセットコンロがあることで、停電時に調理ができます。カセット用のガスボンベの備蓄もしておく必要があります
– カセットコンロ・ボンベ×6本(夏)、9本(冬) ※1人1週間およそ6~9本程度
– 鍋、やかん、食器類
– ラップ、アルミホイル
– ウェットティッシュ・除菌シート
電気・照明関連の必需品
停電は災害時によく起こる問題です。停電時の明かりの確保として必須です。LEDライトのランタンなどもあると良いでしょう。
【照明・電源】
– LEDライト・ランタン ※1人1灯と1部屋に1灯
– スマホで情報を得るために、モバイルバッテリーも必須です
– 乾電池(単3形の場合)×33本*目安 ※ライトなど機器にあわせてサイズや本数を確認
– ソーラー充電器
– 延長コード・電源タップ
衛生・健康管理用品
災害時でも清潔な環境を保つことは、健康維持に欠かせません。
【衛生用品】
– 断水した場合にも衛生的に過ごすために必要ですとして、十分な水の備蓄
– 携帯トイレは、袋と給水シートと凝固剤がセットになっている商品です。水で流す必要がなく、小さく折りたためるため、防災グッズに向いています
– 1日5〜8回が一般的です。例えば、4人家族でそれぞれが1日5回トイレに行くのであれば、5回×4人=20回分の携帯トイレを準備しておきましょう
– 生理用品・おむつ
– 石鹸・シャンプー・歯磨きセット
– タオル・着替え
【医療・救急用品】
– 救急箱(絆創膏、消毒液、包帯、体温計など)
– 常備薬・処方薬
– マスク
– 体温計
– お薬手帳のコピー
情報収集・連絡手段
災害時の情報収集は命に関わる重要な要素です。
【情報収集機器】
– ラジオには、速報性、地域に根ざした細やかな災害情報、日頃から親しんでいるパーソナリティによる安心感など、テレビやネット、SNSにはないメリットがあります
– 乾電池やUSB充電で使用できるラジオが重要な役割を果たします
– 手回し充電ラジオ
– 予備のスマートフォンバッテリー
– 筆記用具・メモ帳
災害時の情報収集方法を確立する
ラジオの重要性とスマホアプリとの使い分け
万能なスマホが普及している近年では、「ラジオなんて古臭いものは必要ない」と感じるかもしれません。しかし、スマホが万能すぎることによって支障を来たす場合もあります。
ラジオのメリット:
– 電波は届くところであれば、どこに居ても放送を聞くことができる
– 長い歴史を持つ中で、災害時でも放送を続けられるノウハウがある
– 音声配信アプリであるラジコは、動画配信アプリに比べるとバッテリーとデータ通信量の消費が格段に少ないという大きなメリットがあり、災害時の利用に適しています
スマホアプリとの使い分け:
– スマホ:家族との連絡、詳細な地図情報の確認
– ラジオ:継続的な情報収集、バッテリー節約
おすすめの防災アプリ
現代の在宅避難では、スマホアプリも重要な情報源となります。
【総合防災アプリ】
– 災害が起こる前に、地震・豪雨・津波などの情報をプッシュ通知で知らせてくれるアプリ。災害に応じた避難場所を確認することもできます「Yahoo!防災速報」
– NHKの災害ニュースをいち早く受け取れるアプリ。NHKが提供するニュースなのでフェイク情報の心配なし!「NHK ニュース・防災」
【ラジオアプリ】
– 災害用のラジオが準備できていなくても大丈夫!radiko.jp(ラジコ)は、インターネットを通じて、今いるエリアのラジオ放送を無料で聞くことができるサービス
自治体からの情報収集方法
目黒区からの情報発信には以下の方法があります。どの媒体で受け取ることができるか、普段から確認しておきましょうとして、以下が挙げられています:
1. 防災無線放送
2. 自治体ホームページ
3. SNS(X、LINE)
4. 防災アプリ
5. 緊急速報メール
お住まいの自治体の情報配信方法を事前に確認し、複数の手段で情報を受け取れるよう準備しておきましょう。
在宅避難中の生活を維持するコツ
トイレ対策の重要性
大規模な災害では、断水や排水管の損傷などの影響で、自宅のトイレが使えなくなる可能性があります。また、集合住宅では、排水管の状況を確認せずに水を流すことで、上階の汚水が下階のトイレから溢れ出る可能性もあります。
トイレ対策のポイント:
– 成人の1日あたりのトイレ使用回数は5回と言われているため、家族1人につき1週間分である35個の備蓄が目標です
– 組み立て式の簡易トイレや、個包装された携帯トイレのほか、いざというときにはゴミ袋と新聞紙などの紙類や布類を使って非常用トイレを作るとも可能です
食事の工夫と栄養管理
在宅避難中でも、可能な限り栄養バランスを考えた食事を心がけましょう。
食事管理のコツ:
– レトルト食品と缶詰を組み合わせて栄養バランスを改善
– 「ローリングストック」という方法がおすすめです。ローリングストックとは、生活用品を多めに購入しておき、期限の早いものから使用し、減った分を買い足しながら備蓄する方法のことです
– 湯せん調理で美味しい食事を作る工夫
– ビタミン・ミネラル不足を補うサプリメント
精神的な健康管理
在宅避難中は、外部との接触が減るため精神的な負担が大きくなることがあります。
メンタルヘルス対策:
– 規則正しい生活リズムの維持
– 家族とのコミュニケーション時間の確保
– 適度な運動・ストレッチ
– 趣味や読書などのリラックス時間
– 近隣住民との情報交換(適度な距離を保ちながら)
在宅避難の体験談と実践例
東日本大震災での在宅避難体験
実際に在宅避難を経験された方々の声を聞くと、事前の備えの重要性がよく分かります。
Aさん(宮城県在住、当時4人家族)の体験:
「地震直後は電気も水道も止まりましたが、事前に1週間分の水と食料を備蓄していたので、なんとか自宅で過ごすことができました。特に役立ったのは、カセットコンロとガスボンベです。温かい食事が取れることで、家族の精神的な支えになりました。
ただ、情報収集には苦労しました。スマホの電池は大切に使わないといけないので、手回しラジオが大活躍。地域の詳しい状況や給水車の情報など、生活に密着した情報はラジオの方が早くて正確でした。」
台風被害での在宅避難事例
Bさん(千葉県在住、夫婦+高齢母の3人家族)の体験:
「台風で長期停電になった時、避難所への移動が困難だった高齢の母を抱えて在宅避難を選択しました。備蓄していた携帯トイレが本当に助かりました。普段から母のトイレの回数を把握していたので、必要な個数を正確に用意できていました。
防災アプリも併用していたのですが、停電復旧の見込みや給水所の開設情報など、リアルタイムの情報はとても助かりました。ただ、バッテリーの消費を考えて、基本的な情報収集はラジオで行い、必要な時だけスマホを使うようにしていました。」
豪雨災害での在宅避難判断
Cさん(熊本県在住、小学生2人の4人家族)の体験:
「豪雨で近くの川が氾濫危険水位に達した時、ハザードマップで自宅が浸水想定区域外であることを確認して在宅避難を決めました。子どもたちは慣れない避難所生活よりも、自宅の方が落ち着いて過ごせていました。
事前に子どもたちと一緒に防災について話し合っていたので、停電しても慌てることなく、LEDランタンをつけたり、非常食を温めたりと、子どもたちも手伝ってくれました。家族で協力することで、不安な気持ちも和らいだと思います。」
在宅避難時の注意点と危険信号
避難所への移動を検討すべきタイミング
在宅避難中でも、状況によっては避難所への移動を検討する必要があります。
避難所移動を検討すべき状況:
1. 建物の安全性に変化があった場合
– 何度も震度5弱以上の余震が発生し、本震では倒壊しなかった住家が、その余震で倒壊した事例もありました
– 亀裂や損傷の拡大
– 異常な音やにおい
2. ライフラインの長期停止
– 水道の復旧見込みが1週間以上
– 下水道の機能停止
– ガス漏れの危険性
3. 健康状態の悪化
– 持病の悪化
– 高齢者・乳幼児の体調不良
– 精神的な不安の増大
4. 物資不足の深刻化
– 食料・水の不足
– 医薬品の不足
– 燃料の不足
近隣住民との協力体制
在宅避難をした場合でも、足りない物資は自治会・町内会などでまとめて、地域防災拠点に受け取りに行く場合があります。そのため、普通から近隣住民との関係性を築いておくことが大切です。
近隣協力のポイント:
– 日頃からの挨拶・コミュニケーション
– 防災訓練への積極的な参加
– 情報共有のルール作り
– 助け合いのネットワーク構築
在宅避難を成功させるための事前準備
家の安全性確保
在宅避難の前提となる「自宅の安全性」を事前に確保しておくことが最も重要です。
【建物の安全対策】
– 耐震診断や耐震補強を行う 令和6年能登半島地震では、耐震化が進んでいない住宅の被害が目立ちました
– 建物の耐震化、家具の転倒防止などを行い、安全な環境づくりを心がけましょう
– 家具の固定やレイアウトを工夫 転倒防止グッズを活用して家具類を固定しましょう
– 大きな地震の後、電力が復旧した際の起こる通電火災を防ぐための感震ブレーカーの設置
ハザードマップの確認と避難計画
居住地の災害のリスクや防災情報が掲載されているハザードマップを入手し、自宅周辺がどのような災害でどの程度の被害を受けると予想されているかを確かめましょう。
事前確認項目:
– 洪水・土砂災害・津波の危険性
– 最寄りの避難所・避難場所
– 安全な避難経路の確認
– 家族の集合場所の決定
– 緊急連絡先の共有
定期的な防災グッズの点検
「防災点検の日」は3月1日・6月1日・9月1日・12月1日となっており、これは1923年9月1日に発生した関東大震災をきっかけに制定されました。
点検項目:
– 食料・水の賞味期限チェック
– 乾電池の残量確認
– 医薬品の使用期限
– 機器の動作確認
– 家族構成の変化に応じた見直し
在宅避難を支える地域・自治体の取り組み
自治体の在宅避難サポート
多くの自治体が在宅避難者への支援体制を整備しています。
【支援内容例】
– 目黒区では、避難所への避難が必要な想定避難者の分だけではなく、在宅避難者の分も考慮して、食料・飲料水を備蓄しています。避難所で生活をしていなくても、備蓄物資を避難所で受け取ることができますので、ご安心ください
– 断水時には東京都が整備した震災対策用応急給水槽や給水所を給水拠点(災害時給水ステーション)とし、応急給水が行われます
– 在宅避難者向けの情報提供
– 巡回型の支援サービス
共助の重要性
皆さんが在宅避難をすると、地域防災拠点の混雑が緩和されます。これは、どうしても地域防災拠点に避難しないといけない人たちのストレス軽減になるため、結果的に「共助」につながるんですよ。
在宅避難は個人や家族の選択ですが、地域全体の防災力向上にも貢献する取り組みと言えるでしょう。
まとめ:在宅避難で家族の安全を守るために
在宅避難は、災害時の重要な選択肢の一つです。しかし、その成功は事前の準備と正しい判断にかかっています。
在宅避難成功の5つのポイント:
1. 安全性の確保:建物の耐震性と家具の固定
2. 十分な備蓄:最低3日分、理想は1週間分の食料・水・生活用品
3. 情報収集手段の確保:ラジオとスマホアプリの使い分け
4. 衛生環境の維持:特にトイレ対策の徹底
5. 地域との連携:近隣住民や自治体との協力体制
災害はいつ起こるか分かりません。災害はいつ起こるか分かりません。いざという時に備えて、避難経路の確認なども事前に行い、在宅避難できるよう今から準備を始めましょう!
家族の笑顔と安全を守るために、今日から少しずつでも準備を始めてみませんか。完璧を目指さず、できることから一歩ずつ。それが防災の基本です。
皆さんとご家族が、いつまでも安全で健康に過ごせることを心から願っています。何か不安なことや分からないことがあれば、お住まいの自治体の防災担当課に相談してみてくださいね。一緒に災害に備えて、安心できる暮らしを築いていきましょう。