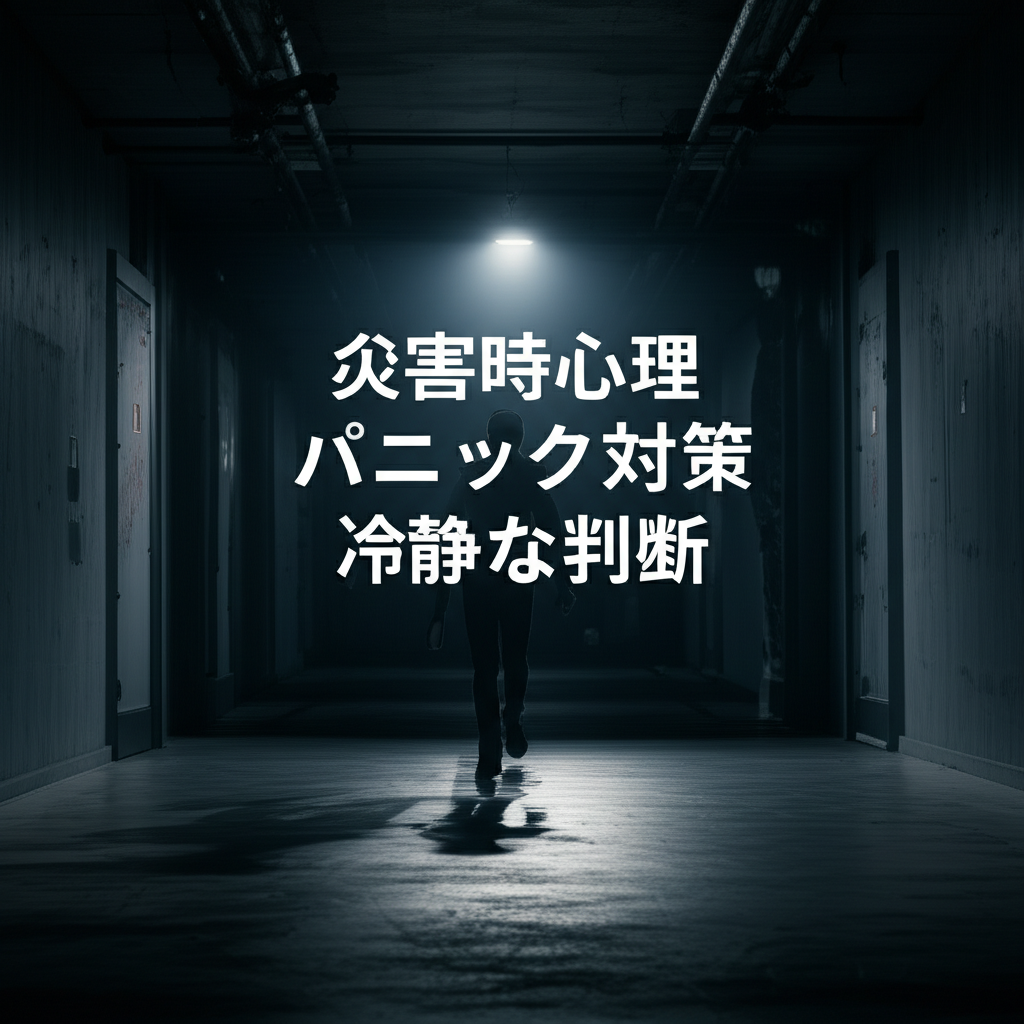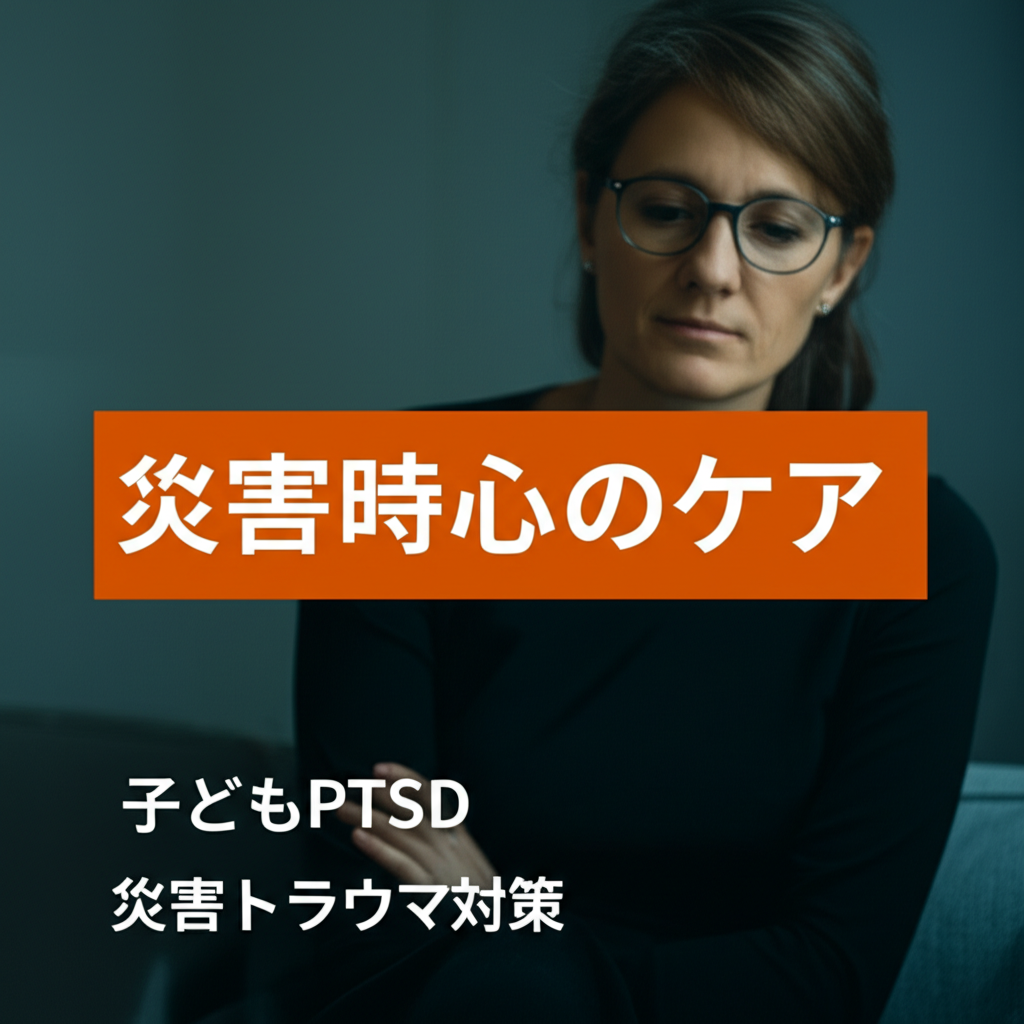
はじめに:災害が子どもに与える見えない傷について
こんにちは。災害大国日本で暮らす私たちにとって、地震や台風、豪雨などの自然災害はいつ身に降りかかってもおかしくない現実です。そんな中、多くのご家庭では防災グッズの準備や避難場所の確認など、物理的な備えには力を入れていらっしゃることでしょう。
しかし、災害時に忘れがちなのが「心のケア」です。特に子どもたちは大人以上に災害の心理的影響を受けやすく、適切な対応をしなければ長期的なトラウマやPTSD(心的外傷後ストレス障害)につながる可能性があります。
大規模災害などでの平均的なPTSDの発症率は約10%と考えられており、大規模災害などの後1年後にPTSDの診断を完全にみたす人の割合、部分的にみたす人の割合はそれぞれ10%程度とされています。これは決して珍しいことではなく、どの家庭にも起こりうる問題なのです。
今日は、災害時の子どもの心のケアについて、専門的な知識を交えながら、実際にご家庭で実践していただける方法をお伝えしたいと思います。
災害時に子どもが受ける心理的影響とは?
子どもは大人よりもダメージを受けやすい
子どもは大人に比べて精神的機能が未発達なため、外傷の影響が深刻になりやすいのが特徴です。これは、子どもの脳がまだ発達段階にあり、強いストレスに対する対処能力が十分に備わっていないためです。
災害時、子どもは特に脆弱です。子どもは年齢によって直面する困難や危険も異なりますし、災害時の混乱などの中で、身体的虐待、性的虐待、ネグレクトなどの被害に遭う危険性も高まります。
子どもが示す災害後の症状
災害を経験した子どもたちには、以下のような症状が現れることがあります:
幼児期(小学2年生程度まで)の症状
– ぼーっとしている
– 物事に関わりたがらない
– 危険が去ったことを理解できない
– ぐずる、眠るのを怖がる
– 両親から離れられない
– 赤ちゃん返り(退行症状)
小学生の症状
– 遊びの中で災害体験を再現する
– 悪夢を見る
– 学校に行きたがらない
– 集中力の低下
– イライラしやすくなる
中高生の症状
– 抑うつ状態
– 不安感の増大
– 友人関係の回避
– 将来への絶望感
– 身体症状(頭痛、腹痛など)
大きな自然災害や事件・事故に子どもが遭遇すると、恐怖や喪失体験などにより心に傷を受け、その時のできごとを繰り返し思い出したり、遊びの中で再現すなどの症状に加え、情緒不安定、睡眠障害などが現れ、生活に大きな支障を来すことがあります。
PTSDとは?子どもにも起こりうる深刻な症状
PTSDの基本的な理解
PTSDとは、Post Traumatic Stress Disorderの頭文字をとったもので心的外傷後ストレス障害といいます。通常の範囲を超えた極端なストレスがかかったり、トラウマ体験といった圧倒的かつ衝撃的な出来事を体験した後に、その出来事が自分の意志とは無関係に思い出され現在も被害が続いているかのように感じる病気のことです。
PTSDとは決して珍しい病気ではなくWHO世界保険調査の日本データによれば、一生の間に生死に関わる体験 (トラウマ体験)をす確率は約60%であり、PTSDの生涯有病率は1.3%とされています。つまり約100人に1人が抱えている「ありふれた精神疾患」ということになります。
PTSDの4つの主要症状
PTSDの主な診断方法は下記の4つです。①侵入(再体験):思い出したくない辛い記憶が時折蘇る。悪夢に出る。②過覚醒:神経が張り詰めた状態にあり不眠になる。③回避:必要以上にその出来事を考えないようにする。④認知と気分の陰性の変化:自分自身を責める。喜怒哀楽が無くなる。
1. 侵入症状(再体験)
– フラッシュバック:災害の記憶が突然蘇る
– 悪夢:災害に関する怖い夢を見る
– 子どもは記憶が遊びに表現されることも多いです。
2. 回避症状
– 災害を思い出させる場所や話題を避ける
– 関連する人や物事から距離を置く
3. 認知や気分の否定的変化
– 過度に自分や他人を責める
– 楽しみや興味を失う
– 感情が麻痺したような状態
4. 覚醒と反応性の変化
– 不眠、イライラ
– ビクビクして落ち着かない
– 些細なことで驚く
急性ストレス障害とPTSDの違い
一般に症状が、一ヶ月以上続く時にはPTSD、一ヶ月以下の時にはASDと診断されます。ASDは、ストレスが起きた時から1ヶ月以内に発症します。一般に、PTSDは、外傷後3ヶ月以内に発症しますが、外傷後何年もたってから発症することもあります。
つまり、災害直後から1か月間の症状は「急性ストレス障害(ASD)」と呼ばれ、1か月以上症状が続く場合にPTSDと診断されます。
家庭でできる災害時の子どもの心のケア方法
1. 安心できる環境づくり
災害時の心のケアで最も重要なのは、子どもに「安心感」を与えることです。
具体的な方法:
– 「今はもう大丈夫だよ」「ここは大丈夫で安全だよ」「みんなで守ってあげるから大丈夫だよ」ということをしっかり伝えながら、質問や疑問には、できるだけ簡潔に説明してください。
– 家族が一緒にいる時間を増やす
– いつものルーティンをできるだけ維持する
– 子どもの話を否定せずに聞く
注意点:
まだ言葉を発していなかったり、言葉によるコミュニケーションができない子どもたちにも、同じように声をかけてください。みなさんの表情や仕草が、子どもたちに安心感を与えます。
2. 遊びを通したケア
「遊び」は子どもたちの大切な「日常」です。家、避難所、テント、体育館、教室、広場など、「安全」が確保できれば、どんな場所でも結構です。おもちゃや遊び道具として使えるものを用意し、子どもたちが苦しい状況を忘れられるよう、子どもたちの相手をしてください。
効果的な遊び:
– 手遊び歌や指相撲
– お絵描きや粘土遊び
– 絵本の読み聞かせ
– 簡単なカードゲームやボードゲーム
遊びの中で注意すべきサイン:
上記のような行動や様子、「ごっこ遊び」が数週間続くようなら、子どもがうまく気持ちの処理をできていない可能性があります。専門家の助けを求めてみましょう。
3. 子どもの話を聞く技術
効果的な聞き方:
– 子どもの話を遮らない
– 「大丈夫」「心配しないで」などの否定的な言葉は避ける
– 子どもの感情を受け止める「怖かったね」「不安だったね」
– 年齢に応じた説明をする
避けるべき対応:
– 感情を否定する
– 「男の子だから泣いちゃダメ」などの性別による制限
– 大人の不安を子どもにぶつける
– 詳細を無理に聞き出そうとする
4. 日常生活のリズムを整える
災害後は生活リズムが乱れがちですが、可能な限り規則的な生活を心がけることが重要です:
– 決まった時間に食事をする
– 十分な睡眠時間を確保する
– 適度な運動をする
– 学習時間も徐々に戻していく
年齢別:子どもの心のケア対策
幼児期(0~6歳)のケア方法
特徴:
これまで「安全であった世界」がそうでなくなったと感じており、安全であることを確認しようとします。そのため、家族への依存が強くなり、赤ちゃん返りなどの症状が表れます。
対応方法:
– 抱っこやスキンシップを多くする
– 赤ちゃん返りを受け入れる
– 簡単な言葉で状況を説明する
– お気に入りのぬいぐるみやおもちゃを手元に置く
注意点:
退行現象(赤ちゃん返り)は正常な反応です。叱ったりせず、温かく受け入れてあげてください。
小学生(7~12歳)のケア方法
特徴:
– 災害の内容をある程度理解できる
– 遊びの中で災害体験を表現することがある
– 学校生活への影響が大きい
対応方法:
– 年齢に応じた正確な情報を伝える
– 学校との連携を密にする
– 友達との交流を支援する
– 災害に関する質問に丁寧に答える
遊びの活用:
子どもの場合、体験したことが遊びの中に再現されることがあります。遊びを通して不安や恐怖などの感情を表現することで、それらを克服し、続発する精神医学的な問題が起こることを一定程度予防することができると考えられています。
中高生(13~18歳)のケア方法
特徴:
– 大人と同じような症状が現れる
– 将来への不安が強くなる
– 友人関係や学習への影響が深刻
対応方法:
– 一人の人格として尊重して接する
– 進路や将来についての不安に寄り添う
– 同世代との交流機会を作る
– 必要に応じて専門的なカウンセリングを検討する
専門的な治療が必要なサインと対処法
専門医療機関への相談が必要なサイン
以下の症状が1か月以上続く場合は、専門機関への相談を検討してください:
– 不眠や悪夢が続く
– 食欲不振が続く
– 学校や日常活動に参加できない
– 激しい感情の起伏
– 自傷行為や自殺をほのめかす言動
– 幻覚や妄想のような症状
PTSDの専門的治療法
子どものPTSDの治療法は大きく分けて3つあると言われています。1.精神療法 2.行動療法 3.選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)のほか、ときに抗アドレナリン作動薬
1. 精神療法(カウンセリング)
– 支持的精神療法
– トラウマフォーカスト認知行動療法(TF-CBT)
2. 行動療法
– 曝露療法:恐怖を段階的に克服していく方法
– リラクゼーション技法
3. 薬物療法
PTSDにはSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)という種類の抗うつ薬が有効で、副作用が少ないことから第一選択薬とされています。
心理的応急処置(PFA)の基本
心理的応急処置(PFA;Psychological First Aid)という方法が提唱されています。これは専門家でなくても実践できる支援方法です:
– 指示的な対応を控え、患者さんが自分自身で問題を解決できるように接する
– 助けを求めていない人に支援を押し売りしない
– 敬意をもった安心できる方法で支援を終わらせる
災害前にできる心の準備と家族での取り組み
1. 災害について家族で話し合う
災害が起きる前から、家族で災害について話し合っておくことが重要です:
話し合うべき内容:
– 災害の種類と対処法
– 避難場所と避難経路
– 家族の集合場所
– 緊急連絡方法
– それぞれの役割分担
災害への備えでは、子どもの視点も取り入れる必要があります。その際、子どものものを親や大人だけで準備したり、一方的に教えたりするだけではなく、子どもと一緒に準備して、一緒に考えることが大切です。
2. 子ども向けの防災教育
効果的な防災教育の方法:
– 年齢に応じた分かりやすい説明
– 実際の避難訓練を体験する
– 防災グッズの使い方を教える
– 災害時の心構えを話し合う
注意点:
過度に不安を煽らないよう、前向きな姿勢で教育することが重要です。
3. 家族の絆を深める日常的な取り組み
災害時の心のケアの基盤は、普段からの家族の絆です:
– 日常的なコミュニケーションを大切にする
– 家族で過ごす時間を確保する
– お互いの気持ちを尊重し合う
– 困ったときは相談できる関係を築く
4. 子どもの心のケアグッズの準備
災害時に避難する場合に備えて準備する非常用持ち出し袋の中に、どんなものを入れたらよいでしょうか。服や薬など、子どもに必要なものにくわえて、子どもが普段一緒に遊んでいるぬいぐるみや、お気に入りの毛布など落ち着けるものも忘れずに。
心のケアに効果的なアイテム:
– お気に入りのぬいぐるみ
– 家族の写真
– 好きな音楽やおもちゃ
– 慣れ親しんだ毛布やタオル
– 大切にしている本
支援者(家族)のメンタルヘルス対策
親や家族のストレス管理
子どものケアをするためには、まず支援者である家族自身が心身ともに健康である必要があります:
自己ケアの方法:
– 十分な休息を取る
– バランスの取れた食事を心がける
– 信頼できる人に相談する
– 必要に応じて専門機関のサポートを受ける
復興に携わる人たちのメンタルヘルスを守ることは、復興を進めていくためにも重要であり、社会的な認識を高め、対策をとることが重要といえるでしょう。
家族全体でのサポート体制
– 役割分担を明確にする
– お互いの負担を理解し合う
– 外部の支援も積極的に活用する
– 定期的に家族の状況を確認し合う
地域社会との連携とサポート体制の構築
学校や地域との協力
子どもの心のケアは家族だけでは限界があります。学校や地域社会との連携が不可欠です:
連携のポイント:
– 担任教師や養護教諭との情報共有
– 地域の子育て支援センターとの連携
– 近隣住民との相互支援体制の構築
– 専門機関の情報収集と活用
専門機関の活用方法
相談できる専門機関:
– 市町村の児童相談所
– 病院の小児科や精神科
– 学校のスクールカウンセラー
– 地域の心理相談室
相談のタイミング:
災害が発生してから1ヶ月程度(災害によってこの時期は異なります)の間に、子どもたちが適切なケアを受けられると、精神医学的な問題が起こることを一定程度予防することができると考えられています。
早期の介入が重要ですので、心配な症状があれば躊躇せず専門機関に相談しましょう。
まとめ:愛する家族の心を守るために今できること
災害は私たちの生活を一瞬にして変えてしまう恐ろしいものですが、適切な知識と準備があれば、その影響を最小限に抑えることができます。特に子どもの心のケアについては、親として、家族として、できることがたくさんあります。
今日からできること:
1. 家族での対話を大切にする
– 日常的なコミュニケーションの充実
– 災害についての年齢に応じた話し合い
– 子どもの不安や疑問に真剣に向き合う
2. 心のケアグッズの準備
– 防災グッズに子どもの心を支えるアイテムも含める
– 家族の写真やお気に入りのものを避難用品に追加
3. 専門知識の習得
– PTSDや災害トラウマについて正しい知識を身につける
– 支援機関の情報を事前に収集しておく
4. 地域とのつながりを深める
– 近隣住民との交流を大切にする
– 学校や地域の防災活動に積極的に参加する
災害時の子どもの心のケアは、決して特別なことではありません。日頃からの愛情深い関わりと、適切な知識があれば、どんな家族でも実践できることです。
「安らぎ」は「心のケア」の第一歩。その「第一歩」が子どもの回復力を左右します。子どもの心に落ち着きを与え、トラウマ(心的外傷)の傷口を最小限にするため、専門家やボランティアではなく、普段から一番身近にいるあなたにしかできないことがあります。
私たち親にできる最も大切なことは、子どもたちに「あなたは一人じゃない」「家族がいつも守ってくれる」という安心感を伝えることです。この安心感こそが、災害という試練を乗り越える最大の力になるのです。
災害はいつ起こるかわかりません。だからこそ、今この瞬間から、家族の心の絆を深め、いざという時に支え合える関係を築いていくことが何よりも重要です。
愛する家族の笑顔を守るために、一緒に災害時の心のケアについて学び、準備していきませんか。きっと、その知識と愛情が、家族の明るい未来を切り開く力となるはずです。