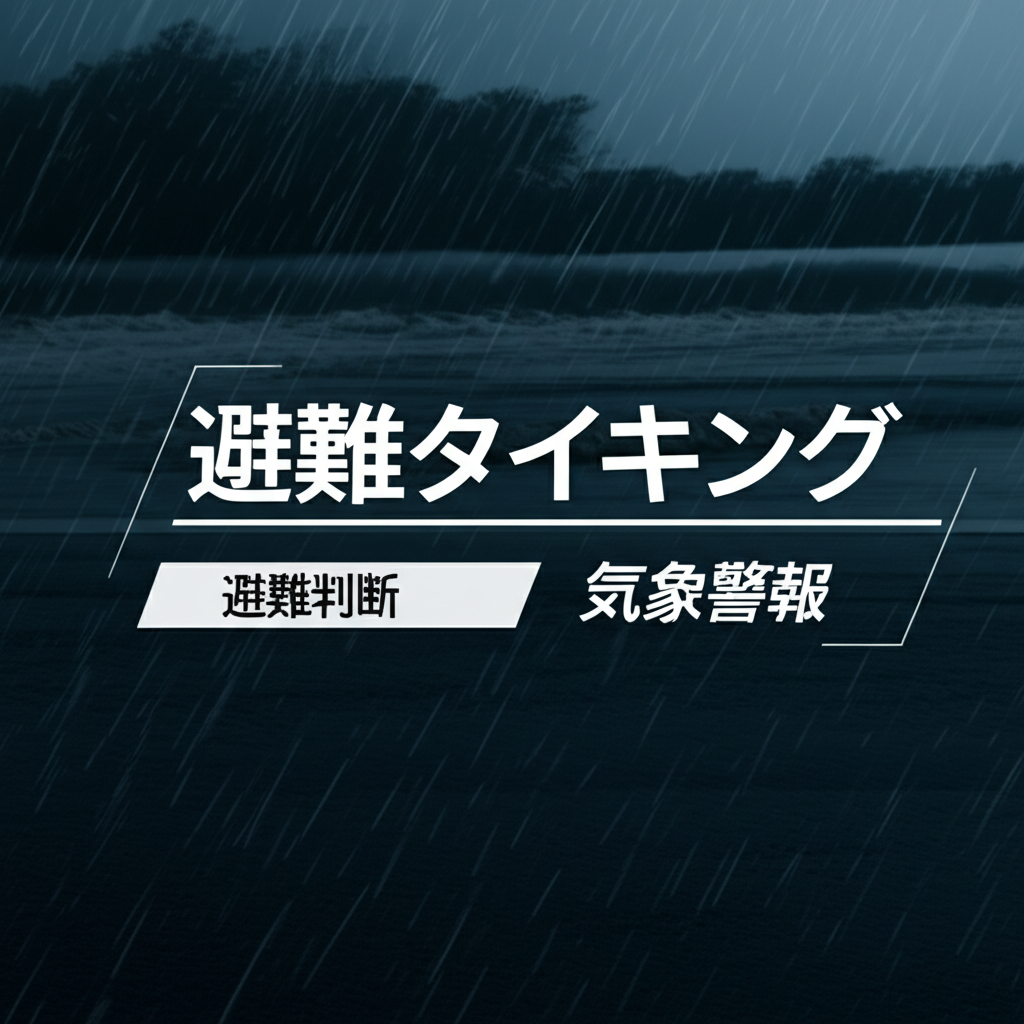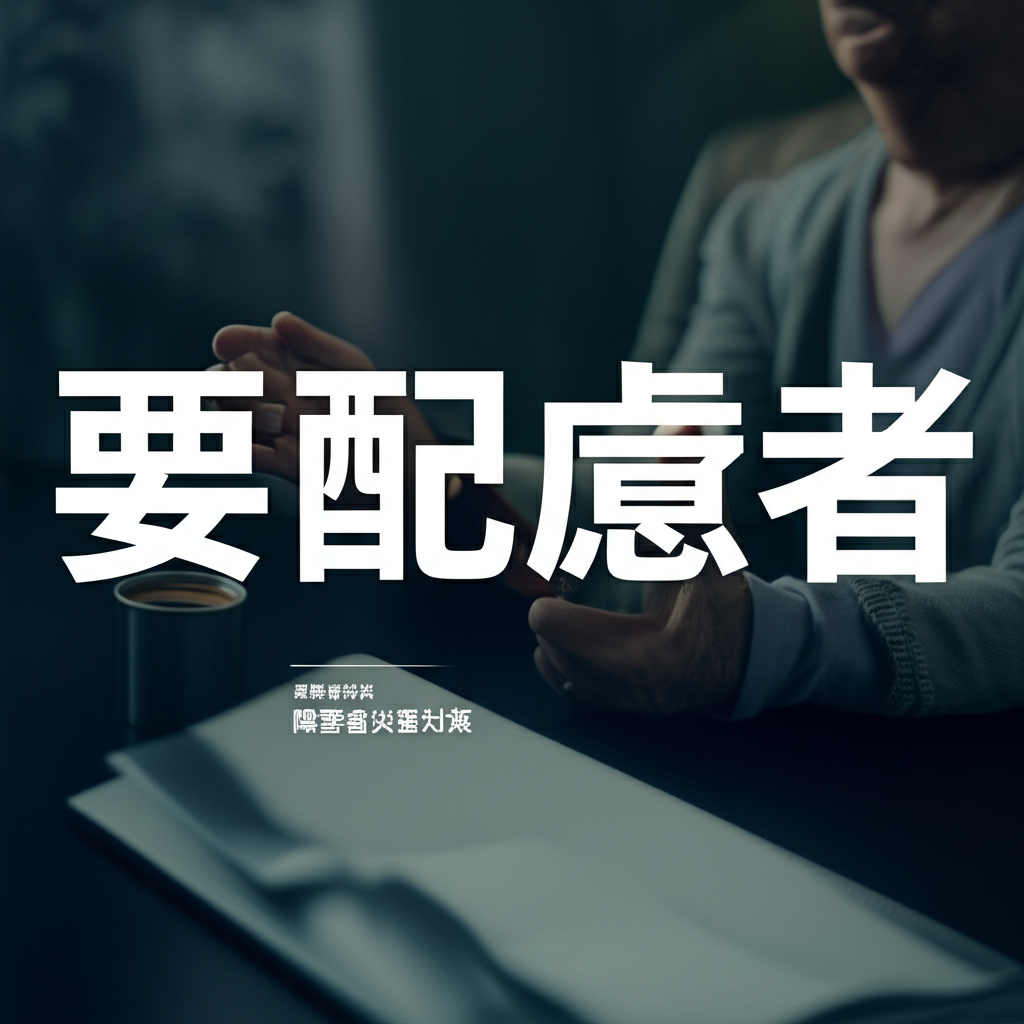なぜ今、高齢者防災が注目されるのか?
近年の災害において、高齢者の被害が深刻な問題となっています。災害による死者のうち、65歳以上の高齢者の割合は令和2年7月豪雨で約79%にも上り、高齢者の災害時における脆弱性が浮き彫りになっています。
防災の必要性を感じる人の割合は、年齢が上がるほど増加し、60〜70代では8割近くに達しているものの、実際の準備となると課題が多いのが現状です。
災害大国である日本で暮らす私たちにとって、高齢のご家族を持つ主婦の皆さんが直面する不安は深刻です。「いざという時、どうやって高齢の親を守ればいいの?」「介護が必要な家族がいる場合の避難方法は?」そんな疑問にお答えするため、この記事では高齢者防災から介護防災、要支援者避難まで、実践的な対策をご紹介していきます。
高齢者が直面する災害時の3つの大きな課題
1. 身体機能の低下による避難の困難
高齢者の災害時避難が困難な理由の一つが、身体機能の低下にあります。歩行が困難な方、車椅子を使用している方、視覚や聴覚に障害のある方など、それぞれ異なる支援が必要です。
具体的な課題:
– 避難指示の情報を聞き取れない(聴覚障害)
– 避難経路を視認できない(視覚障害)
– 長距離の歩行が困難(歩行障害)
– 階段の昇降ができない(下肢筋力低下)
2. 薬物治療の継続問題
多くの高齢者が複数の慢性疾患を抱え、日常的に薬物治療を受けています。災害時にはこれらの薬剤の確保が大きな問題となります。
主な懸念事項:
– 高血圧薬、糖尿病薬などの継続服用の必要性
– かかりつけ医との連絡困難
– 薬剤の在庫切れ
– お薬手帳の紛失
3. 認知症による避難行動の複雑化
高齢者の住宅改善に対する意識は低く、地域全体の耐震化の遅れが懸念される状況に加え、認知症の方の避難行動には特別な配慮が必要です。
認知症特有の課題:
– 避難の必要性を理解できない
– 慣れない環境での混乱
– 徘徊のリスク
– 服薬管理の困難
介護防災の具体的な準備方法
基本的な防災グッズの準備
一般的な防災グッズに加えて、介護が必要な方向けの特別な準備が重要です。
介護防災グッズチェックリスト:
医療・薬関連
– 常用薬(最低7日分)
– お薬手帳のコピー
– かかりつけ医の連絡先
– 血圧計、血糖値測定器
– 体温計
食事関連
高齢者でも食べられる介護食を準備し、とろみ剤を備蓄することが重要です。
– 介護食(ソフト食、ミキサー食)
– とろみ剤
– ストロー付きコップ
– 使い捨て食器
衛生・介護用品
– 大人用紙おむつ(1週間分)
– ウェットティッシュ(大容量)
– 使い捨て手袋
– 清拭シート
– 口腔ケアグッズ
電力確保対策
電動ベッドや吸引機などの在宅介護機器には手動で動かす機能が備わっているため、事前に操作方法を学んでおくことが大切です。
電力対策の具体例:
– ポータブル電源の準備
– 車のインバーター活用法の習得
– 手動操作方法の練習
– 予備バッテリーの常備
情報収集・連絡手段の確保
連絡網の整備:
– 家族間の連絡方法の確認
– 近隣住民との連携
– ケアマネジャーとの連絡体制
– 避難所の障害者対応状況の確認
要支援者避難計画の立て方
個別避難計画の重要性
令和3年の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者について個別避難計画を作成することが市町村の努力義務とされました。しかし、実際の策定状況は課題が多いのが現状です。
策定済みが7.9%と不十分な状況であるため、家族自身でも準備を進める必要があります。
個別避難計画作成のステップ
ステップ1:基本情報の整理
– 要支援者の詳細な身体状況
– 必要な介護の程度
– 使用している福祉用具
– 服薬状況
ステップ2:避難支援者の確定
– 家族内での役割分担
– 近隣住民への協力依頼
– ケアマネジャーとの連携
– 民生委員との情報共有
ステップ3:避難経路・場所の選定
– 複数の避難経路の確認
– 車椅子対応の経路選択
– 福祉避難所の事前確認
– 一時避難場所の設定
ステップ4:必要物品の準備
– 避難時持参品リスト作成
– 分散配置による紛失対策
– 定期的な点検・更新
地域連携の構築方法
福祉専門職の参画を促進するため、県・市町村単位で設置されている福祉専門職の団体に働きかけることが有効です。
地域連携のポイント:
– 自治会・町内会への参加
– 民生委員との関係構築
– 地域包括支援センターとの連携
– 福祉専門職との連携強化
避難所生活での高齢者への配慮
避難所での課題と対策
避難所生活での不安点は「トイレ」「プライバシー」「衛生面」の3つが多く、「トイレ」への不安は60〜70代をメインに年々高まっている状況があります。
トイレ問題への対策:
– 簡易トイレの持参
– 排泄介助用品の準備
– プライバシー確保グッズ
– 感染症対策用品
福祉避難所の活用
福祉避難所の特徴:
– バリアフリー対応
– 医療機器の電源確保
– 専門スタッフの配置
– 個室またはパーティション区画
事前確認事項:
– 所在地とアクセス方法
– 受け入れ条件
– 設備・サービス内容
– 連絡先・手続き方法
日常的な備えと訓練の実践
定期的な防災訓練の実施
家族防災訓練の内容:
– 避難経路の実際の歩行
– 車椅子での移動練習
– 非常用品の使用方法確認
– 連絡方法の実践
地域防災訓練への参加
個別避難計画の内容をもとに避難訓練に取り組んでいるのは8市町村(18.2%)と少ないため、積極的な参加が重要です。
参加のメリット:
– 実際の避難手順の確認
– 地域住民との顔の見える関係構築
– 問題点の早期発見
– 計画の見直し機会
情報収集体制の整備
多重化した情報収集:
– 防災無線の確認
– 防災アプリの活用
– テレビ・ラジオの備え
– 近隣住民との情報網
「防災無線はない+あるかどうかはわからない」が54%を占め、20〜30代は6割を超えている状況を踏まえ、複数の情報源を確保することが重要です。
実際の災害事例から学ぶ教訓
能登半島地震からの学び
能登半島地震では、最新の建築基準(2000年基準)を満たした住宅の被害は、わずかに留まった可能性が指摘されている一方で、高齢者の住宅の耐震化の遅れが問題となりました。
教訓と対策:
– 住宅の耐震診断の実施
– 家具の固定と安全な配置
– 寝室の安全確保
– 避難経路の障害物除去
過去の災害における高齢者被害の分析
主な被害パターン:
– 避難情報の伝達不足
– 避難支援者の不在
– 福祉避難所の不足
– 医療継続の困難
対策の改善点:
– 複数の情報伝達手段
– 支援者の多重化
– 事前の受け入れ先確認
– 医療情報の共有
費用を抑えた防災対策のコツ
優先順位をつけた段階的準備
第1段階(最優先):
– 服薬中の薬の予備確保
– 基本的な介護用品の備蓄
– 緊急連絡先の整理
– 避難経路の確認
第2段階:
– 非常食の充実
– 電源確保対策
– 福祉用具の予備
– 地域連携の構築
第3段階:
– 住宅の安全対策
– 訓練の本格実施
– 計画の詳細化
– 継続的な見直し
公的支援の活用
利用可能な制度:
– 日常生活用具給付事業
– 住宅改修費助成
– 防災用品購入補助
– 避難行動要支援者支援制度
地域資源の活用
活用できる地域資源:
– 社会福祉協議会のサービス
– ボランティア団体の支援
– 近隣住民との相互扶助
– 専門職のアドバイス
まとめ:今日からできる高齢者防災アクション
高齢者防災は一朝一夕にはできませんが、小さな一歩から始めることが大切です。まずは以下の5つのアクションから始めてみましょう。
今日からできる5つのアクション:
1. お薬手帳のコピーを作成
常用薬の情報を複数箇所に保管し、災害時の医療継続に備える
2. 緊急連絡先リストの作成
家族、医療機関、ケアマネジャー、行政機関の連絡先を整理
3. 避難経路の実際の確認
車椅子や歩行器を使用して、実際に避難経路を歩いてみる
4. 介護用品の備蓄開始
紙おむつやウェットティッシュなど、最低3日分から始める
5. 地域との接点づくり
自治会や民生委員との関係構築を始める
高齢者防災は、要支援者ご本人だけでなく、ご家族や地域全体で取り組む課題です。完璧を目指さず、できることから少しずつ始めて、継続的に改善していくことが何より重要です。
災害に対して不安を感じている人が全体で74.4%いる中で、実際に行動に移すことで、その不安を具体的な安心に変えていくことができます。
あなたの大切なご家族を災害から守るために、今日からできることから始めてみませんか?一人ひとりの小さな準備が、災害に強い地域社会をつくる大きな力となるのです。