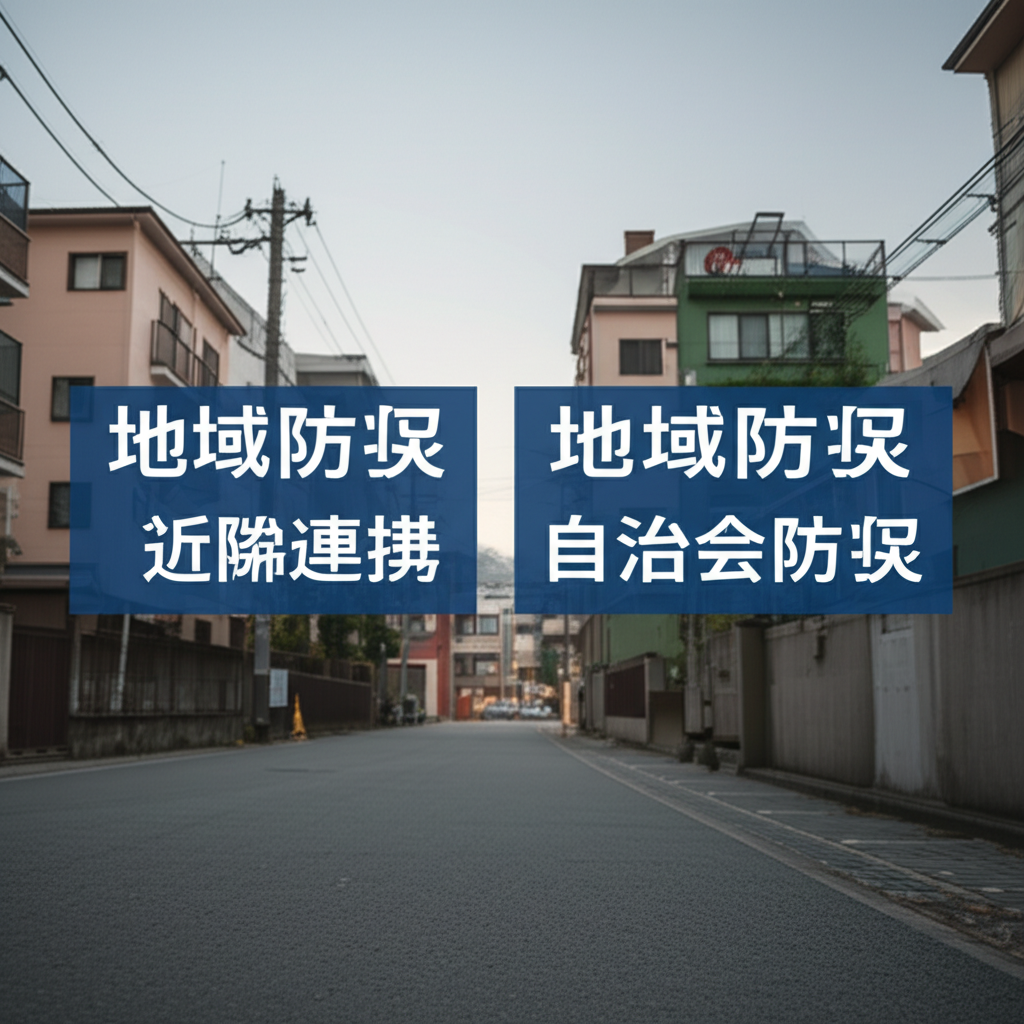
災害大国日本では、いつ何時大きな災害に見舞われるかわかりません。そんな中、私たち主婦にとって最も心配なのは、災害時に家族の安全をどうやって守るかということですよね。
実は、災害発生から72時間は「黄金の72時間」と呼ばれ、自衛隊などの救助が来るまでの間、同じ地域の住民同士でお互いに助け合う「共助」の精神が必要になる重要な時間なのです。この期間、行政の支援は追いつかず、私たちは地域のコミュニティの力に頼らざるを得ません。
しかし「近所付き合いが薄くて心配」「自治会の活動に参加したことがない」という方も多いのではないでしょうか。今回は、地域防災における近隣連携の重要性と、主婦でも無理なく始められる共助体制の作り方について、具体的な事例とともにお話しします。
なぜ地域防災での共助が今注目されているのか
現代の防災事情と共助の重要性
近年、気象災害・土砂災害等が多発しています。また、今後、発生が危惧されている首都直下地震、南海トラフ地震等の大規模広域災害に備え、自助・共助の役割の重要性が高まっています。
特に注目すべきは、東日本大震災において、自助、共助及び公助が連携することによって大規模広域災害後の災害対策がうまく働くことが強く認識されたことです。これを受けて、平成25年の災害対策基本法では、自助及び共助に関する規定が追加されました。
72時間の壁と地域コミュニティの力
災害時の「72時間の壁」について、多くの方がご存じないかもしれません。特に水害や土砂崩れなどが起きた場合、生命のリミットとして知られる72時間、地域住民同士で声掛けや協力をし合うことで、助けられる生命が少なくありません。
この期間中、道路の寸断や通信障害により、消防や警察、自衛隊などの公的支援が十分に届かない可能性が高いのです。だからこそ、日頃からの近隣連携が家族の命を守る重要な鍵となるのです。
従来の防災組織が抱える課題
一方で、従来、地域防災力向上のために活躍していた、消防団、自主防災組織等は少子高齢化等、社会の変化に伴い活動が縮小している等の問題が発生しており、このような状況を踏まえ、地域コミュニティにおける共助による防災活動を強化する必要があります。
このような背景から、私たち一人ひとりが地域防災により積極的に関わることが求められているのです。
自治会・町内会防災活動の実態と可能性
自治会と町内会の防災における役割
まず基本的なことから確認しましょう。自治会と町内会は違う団体なのかと思われがちですが、地域によって呼び方が違うだけで同じ団体のことです。これらの組織は、地域防災において中核的な役割を果たしています。
町内会・自治会の活動内容は地域や会によってさまざまですが、主な活動のひとつが「防犯や地域安全活動、災害時の対応」です。具体的には、防火・防犯パトロール、防災訓練や防災マップの作成、災害時の緊急連絡などがあります。
自主防災組織の結成と運営
自主防災組織を結成する場合、既にある団体を活用し自主防災組織として兼ねることも可能で、自治会や町内会等が自主防災組織を兼ねることが一般的とされています。
実際の組織形態については、重複型(町内会などの代表者、役員が自主防災組織の代表者、役員を兼ねる)、下部組織型(町内会などの下に独自の代表者、役員をもつ自主防災部門をつくる)、別組織型(町内会とは別個に自主防災組織を結成する)などがあり、地域の実情に合わせて選択できます。
成功事例:静岡市大岩二丁目の取り組み
具体的な成功事例を見てみましょう。静岡市大岩二丁目では、平常時のボランティア活動を、防災活動と連携化させることで、自主防災会への参加者が、町内住民の20%近くにまで達する、町内ぐるみの防災活動となっている素晴らしい取り組みが行われています。
この地域では、大工等、建築関係の技能を持つ住民が、高齢者住宅の一部補修を行う、医者などの参加する医療班が町内在住の高齢者の健康診断を行う、消火班が温泉の宅配サービスを行うなど、日常的な助け合いと防災活動を巧妙に組み合わせています。
近隣連携を成功させる7つのコツ
1. 挨拶から始める関係作り
地域防災の第一歩は、日常的なコミュニケーションです。地域の人と人との繋がりこそが、最大の防災力になります。普段からのあいさつといった些細なコミュニケーションが、いざという時の繋がりをつくります。
毎朝のゴミ出しや子どもの送り迎えの際に、積極的に近所の方に挨拶することから始めてみましょう。顔見知りになることで、災害時の安否確認や助け合いがスムーズになります。
2. 防災訓練への積極的参加
自治会や町内会で行う避難訓練を通じて、災害時における安全意識が高まり、住民全体の防災意識が向上します。実際の避難経路を確認し、避難行動を体験することで、災害時に迅速かつ的確に行動できるようになります。
また、住民同士や自治会、行政、消防などとの連携を強化し、災害時に円滑な情報共有と協力ができるようになります。訓練は貴重な顔合わせの機会でもあるのです。
3. スキルの共有と活用
静岡市の事例のように、それぞれが持つスキルを防災に活かすことが重要です。看護師の経験がある方は救護班に、料理が得意な方は炊き出し班に、といったように、日常のスキルが災害時の大きな力となります。
自分にどんなスキルがあるか、そして近所の方がどんなスキルを持っているかを把握し、災害時に活用できる体制を作りましょう。
4. 要支援者の把握と見守り体制
住民がそれぞれ高齢者の担当となって、避難時には担当の高齢者へも声をかける仕組みを作りましたという大船渡市の事例のように、地域の高齢者や体の不自由な方への支援体制を整えることが重要です。
日頃から近所の一人暮らしの高齢者や、小さなお子さんがいる家庭の状況を把握し、災害時にお互いに声をかけ合える関係を築いておきましょう。
5. 情報共有システムの構築
災害時の情報を迅速かつ正確に伝達する方法を学びます。無線通信の訓練、非常時連絡網の確認、地域内での情報共有方法の確認を行います。
SNSのグループやメーリングリストを活用した情報共有システムを構築することで、災害時に迅速な情報伝達が可能になります。
6. 備蓄品の相互補完
各家庭でも食料や飲料水などを防災備蓄品として常備しておくことで、自治会、町内会で備蓄している食料や飲料水の不足を軽減する事ができます。
家庭での備蓄に加えて、地域全体で備蓄品を相互補完する仕組みを作ることで、より安心な備えが可能になります。
7. 定期的な見直しと改善
防災訓練は年に一度や数回しか行われないことが多く、訓練の間隔が長いために住民の意識が薄れがちという課題があります。
定期的な防災会議や見直しの機会を設けることで、常に最新の情報や課題を共有し、改善を続けることが大切です。
実際の災害時に機能した地域コミュニティの事例
台風14号での諸塚村の成功事例
令和4年度に発生し、大きな被害をもたらした台風14号での事例です。面積の95%を森林が占める小さな村では、予め地形に対応したハザードマップと支援が必要な人のリストを作成。また、公民館単位で1年に1度の避難訓練も実施していました。
この村では、集落が点在しているという村の状況を鑑みて16の自治公民館がそれぞれ組織運営をしして、自助・共助を進める取り組みにより、離れたところに住んでいる人も逃げ遅れることのない体制を作っており、「諸塚方式」と呼ばれています。
区長の声かけが命を救った事例
最初は「大したことにはならないだろう」と考えていた住民もいたとのことで、区長の声かけによって意識が高まり、共助に繋がりました。コミュニケーションによって多くの人命が救われた例です。
この事例からわかるのは、地域のリーダーシップの重要性と、普段からのコミュニケーションがいかに大切かということです。
大船渡市の継続的な取り組み
チリ地震津波を経験した大船渡市では、平成7年に公民館役員の提案で自主防災組織を立ち上げました。普段から「緊急時要援護者マップ」を作成し、住民がそれぞれ高齢者の担当となって、避難時には担当の高齢者へも声をかける仕組みを作りました。
さらに、毎年5月に避難、炊き出し、救出・搬送、消火の訓練や、児童へ津波体験談を話す日を設けています。防災用品も全世帯に配布して災害に備えていましたという継続的な取り組みが行われています。
主婦でも無理なく始められる参加方法
段階的な参加アプローチ
いきなり自治会の役員になったり、大きな責任を負ったりする必要はありません。まずは以下のステップで段階的に参加してみましょう:
第1段階:観察と情報収集
– 自治会の掲示板や回覧板をしっかりと確認する
– 防災訓練の見学から始める
– 近所の方との日常会話で防災について話題にする
第2段階:軽い参加
– 防災訓練に参加者として参加する
– 地域の清掃活動に参加する
– 防災関連の講習会に参加する
第3段階:積極的な関与
– 防災訓練の企画や準備に協力する
– 近隣の要支援者の見守りを引き受ける
– 防災に関する情報共有の役割を担う
子育て世代特有の参加方法
小さなお子さんがいる場合は、子どもと一緒に参加できる活動から始めましょう。子ども向けにはクラフト系のワークショップがおすすめです。
親子で防災を学ぶことで、非常時の備えや行動について、改めて考えるきっかけになるだけでなく、他の子育て世代との交流も深まります。
働く主婦の時間管理術
フルタイムで働いている場合でも、参加方法は工夫次第です:
– 土日の活動を中心に参加する
– オンラインでの情報共有や会議に参加する
– 家族で分担して参加する(夫が訓練、妻が情報共有など)
– 職場での防災知識を地域に還元する
人見知りの方向けのコミュニケーション術
「人見知りで積極的に話しかけるのが苦手」という方も多いでしょう。そんな方には以下のアプローチがおすすめです:
– まずは同世代や同じような境遇の方を見つける
– 防災グッズや備蓄品の話題から会話を始める
– 子どもや ペットを通じた自然な交流を図る
– 得意分野での貢献から始める(料理、パソコンなど)
地域防災計画への参画方法
地区防災計画制度の活用
平成25年の災害対策基本法では、自助及び共助に関する規定が追加されました。市町村内の一定の地区の居住者及び事業者が行う自発的な防災活動に関する「地区防災計画制度」が新たに創設されました。
この制度を活用することで、地域住民が主体となって防災計画を立てることができます。地区防災計画ガイドラインは、地区居住者等が、地区防災計画について理解を深め、地区防災計画を実際に作成したり、計画提案を行ったりする際に活用できるようになっています。
計画策定プロセスへの参加
地区防災計画の策定は、専門家だけが行うものではありません。むしろ、日常生活を送る住民の視点が最も重要です。
住民参加のポイント:
– 地域の危険箇所の把握(主婦目線での生活道路の課題など)
– 避難時の課題の洗い出し(子どもや高齢者の移動支援など)
– 日常生活との両立方法の提案
– 継続可能な活動内容の検討
ワークショップやまちあるきへの参加
防災計画とは、自治体と住民が、まちあるきや意見交換をしながら一緒につくる計画のことです。このような住民参加型の取り組みに積極的に参加することで、地域の実情に合った実効性のある計画作りに貢献できます。
よくある課題と解決策
参加者の固定化問題
多くの地域で「いつも同じ人ばかりが参加している」という課題があります。この解決策として:
新しい参加者を増やす工夫:
– 防災以外のイベントと組み合わせる(バーベキュー、お祭りなど)
– 防災トランプなど、ゲーム要素を取り入れた学習方法を導入する
– 子ども向けの企画を充実させることで、親世代の参加を促す
– SNSやアプリを活用した現代的な情報共有方法を取り入れる
世代間の意識格差
高齢世代と若い世代では防災に対する意識や方法に違いがあることがあります:
世代をつなぐ工夫:
– 各世代の得意分野を活かした役割分担
– 伝統的な防災知識と最新技術の融合
– 世代間での経験談の共有機会を設ける
– 若い世代の技術力と高齢世代の経験を組み合わせた企画
継続性の確保
防災訓練は年に一度や数回しか行われないことが多く、訓練の間隔が長いために住民の意識が薄れがちという課題に対しては:
継続性を高める方法:
– 季節ごとの小規模な活動を企画する
– 日常生活に防災を組み込む工夫をする
– 成果を可視化して達成感を共有する
– 楽しみながら学べる要素を継続的に取り入れる
費用負担の問題
自治会の予算枠として、防災活動の予算枠が確保されており、その中から温泉宅配サービスの活動費や、炊き出し用の材料費などが手当てされている成功例もありますが、費用の問題は多くの地域で課題となっています。
費用負担を軽減する工夫:
– 自治体の補助金制度を積極的に活用する
– 地元企業との連携により資材や場所の提供を受ける
– 家庭にある物を持ち寄る形での訓練を企画する
– 無料でできる活動(情報共有、見回りなど)を充実させる
地域企業や商店との連携方法
地域経済との防災連携
最近では、地元企業が地域コミュニティと連携し、備蓄品を提供したり、施設を開放したりという事例も増えてきました。その活動の源泉となるのは、地元への愛着心です。
地域の商店や企業と連携することで、より充実した防災体制を構築できます:
連携の具体例:
– 薬局:救急用品の提供や応急処置の指導
– スーパー:災害時の食料調達協定
– ガソリンスタンド:災害時の燃料確保
– 建設会社:災害時の復旧作業支援
– 医療機関:救護活動の支援
災害時協定の重要性
町内会として非常時の食糧供出について町内の米屋・スーパーと協定を結んでいる静岡市大岩二丁目の事例のように、災害時の支援協定を結ぶことが重要です。
これらの協定は、行政だけでなく住民組織でも結ぶことができ、より身近で迅速な支援体制を構築できます。
防災訓練を楽しく効果的にする工夫
従来の防災訓練の課題
例えば、夜間や悪天候時の避難訓練は行われないことが多いです。さらに、自治会や町内会には限られた資材や機材しかなく、十分な設備や資機材を揃えることが難しいこともありますという課題があります。
楽しみながら学べる防災活動
ゲーム要素を取り入れた訓練:
– 防災トランプは、ゲームを通じて防災について学べるトランプです。ババ抜きやポーカー、大富豪などのトランプゲームを実施し、カードに記載されている防災に関するお題に沿って会話をすることで、防災について学べる
– 防災クイズ大会の開催
– 宝探しゲーム形式での避難経路確認
– VRを活用した災害体験
体験型の学習活動:
– 消火活動体験は、消防署が実施することが一般的です。消防署のなかには、初期消火、応急処置・救命、非常食などを体験できる防災イベントを実施した例もあります
– 段ボールベッドや間仕切りの組み立て体験
– 非常食の試食会
– 応急処置や心肺蘇生法の実技訓練
家族ぐるみで参加できる企画
子どもと一緒に学べる活動:
– 子ども向けにはクラフト系のワークショップがおすすめです
– 防災グッズ作りワークショップ
– 子ども防災リーダー制度の導入
– 防災標語コンテスト
多世代交流の促進:
– 高齢者の災害体験談を聞く会
– 若い世代による高齢者へのスマホ防災アプリ指導
– 世代を超えた防災知識の共有会
まとめ:今日から始める地域防災への第一歩
災害はいつ起こるかわかりません。しかし、だからこそ日頃からの備えと、地域での支え合いが重要なのです。
防災のために地域コミュニティでの取り組みは必要不可欠となっています。そして、市町村地域防災計画の一部として、地区居住者等が行う自発的な防災活動に関する計画(地区防災計画)が明確に位置付けられました。この点から見ても、今後の防災対策には地域コミュニティの存在が欠かせません。
今日からできる具体的なアクション
明日からすぐに始められること:
1. 近所の方への挨拶を心がける
2. 自治会の掲示板や回覧板を注意深く確認する
3. 家族で避難経路を確認し、近所の方とも共有する
4. 防災グッズの確認をしながら、近隣との情報交換をする
1か月以内に挑戦したいこと:
1. 地域の防災訓練に参加する
2. 自治会や町内会の会合を見学する
3. 近所の高齢者や子育て世帯の状況を把握する
4. 地域の危険箇所を家族で確認し、近隣と情報を共有する
3か月以内に目指したいこと:
1. 地域の防災活動に継続的に参加する
2. 自分のスキルを活かした貢献方法を見つける
3. 近隣との緊急時連絡網を構築する
4. 地区防災計画策定への参画を検討する
最後に:共助の心が生む安心の輪
地域防災は、決して特別な人だけが行うものではありません。私たち一人ひとりが、できることから始めることで、家族の安全と地域の安心を守ることができるのです。
自分たちの地域は自分たちで守る、という機運が高まれば、さらに地域の防災は実効性のあるものとなるでしょう。そして、その第一歩は、今日のあなたの行動から始まります。
災害時に「あの時、地域の人たちとのつながりを作っておいて良かった」と思えるように、今から少しずつでも地域防災への参加を始めてみませんか。あなたの小さな一歩が、家族と地域の大きな安心につながるはずです。
防災は「備えあれば憂いなし」。しかし、それ以上に「つながりあれば安心あり」なのです。今日から始める地域防災への参加が、あなたと家族の未来を守る第一歩となることを願っています。





