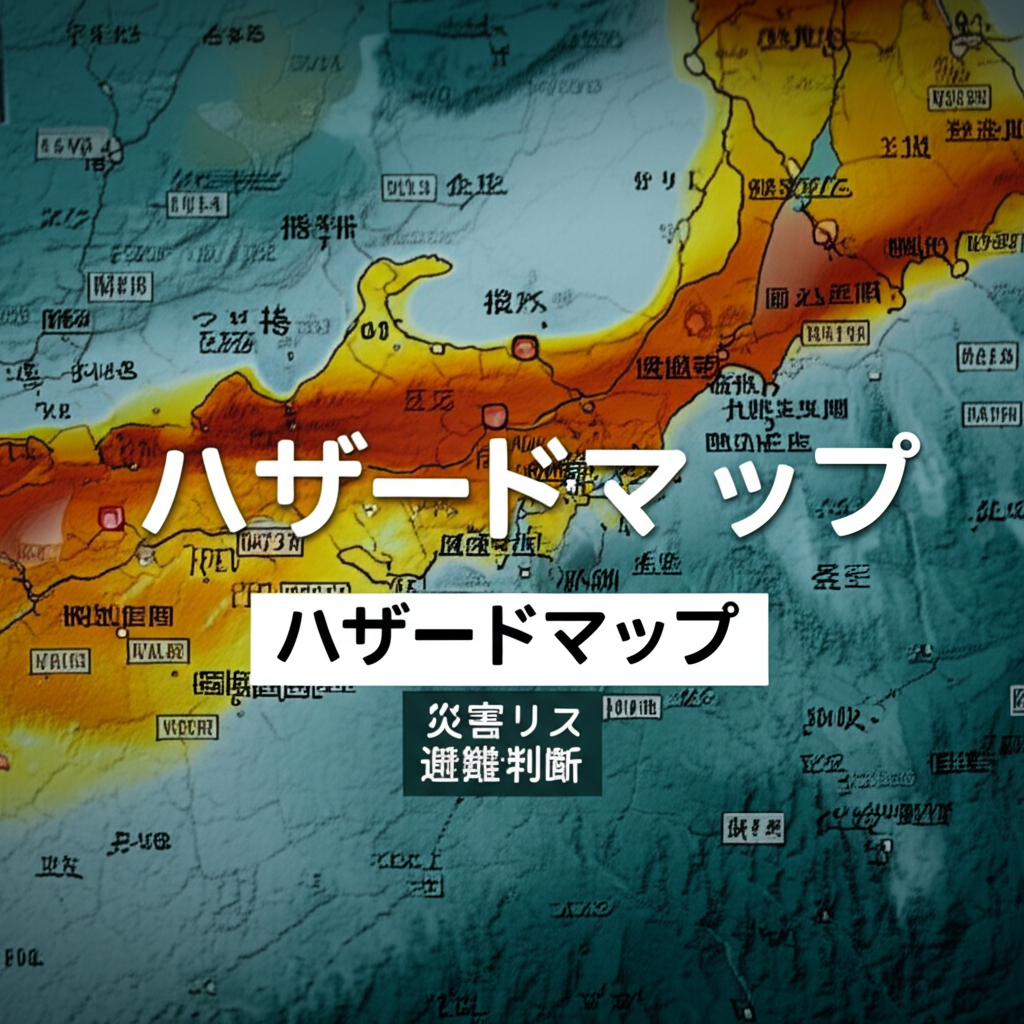はじめに:防災グッズの重要性が高まる日本
災害大国日本において、防災グッズの備えは家族の命と安全を守る重要な要素です。地震・火災などの災害への対策を考えたとき、防災セットは必ず用意しておくべき商品です。
近年、自然災害の頻発により、防災グッズの需要は急速に高まっています。しかし、実際に災害に遭遇した人の体験談を聞くと、「用意したけど使わなかった」「本当に必要なものが足りなかった」といった声も多く聞かれます。
本記事では、実際の被災者の声や防災士のアドバイスを元に、防災グッズで絶対に必要な最強アイテムをランキング形式でご紹介し、失敗しない防災グッズの選び方を詳しく解説していきます。
実際に役立った防災グッズ レビュー【TOP20】
1位:飲料水・保存水
飲料水は防災グッズのなかでも特に重要なアイテムです。1日に必要な飲料水の量の目安は成人で約3リットルであるため、自宅には1人あたり「3リットル×3日分」の飲料水(保存水)をストックしておきましょう。
実際の使用レビュー:
3.11で被災されたママ防災士・リサさんも、ご自宅の水道が止まってしまい、水を求めて近所の公園を回られたそうです。
選び方のポイント:
– 500mlペットボトルは持ち運びやすく、衛生的
– 10年保存水なら交換頻度が少なく経済的
– スポーツドリンクも併用すれば塩分補給も可能
2位:非常食・保存食
飲料水は2本と少なめですが、給水バッグ付きで水の確保がしやすいのも便利です。災害時の食事は栄養補給だけでなく、精神的な支えにもなります。
おすすめの非常食:
1. アルファ化米(おにぎり、チャーハンなど)
2. 缶詰(さば、ツナ、焼き鳥など)
3. レトルト食品(カレー、スープなど)
4. 乾パン・クッキー類
実際の使用レビュー:
水が不要でそのまま食べられるため調理の手間がかからず、ガスや電気が止まっても食べられます。
3位:携帯トイレ・簡易トイレ
ライフライン寸断で一番困るのは「トイレ」。人によってトイレに行く回数は異なりますが、1日5〜8回が一般的です。
使用量の目安:
– 1人1日:5〜8回
– 家族4人×3日分:60〜96回分
実際の使用レビュー:
個装になっていないのと凝固剤がこぼれやすいので、100均のジッパー付袋A6に入れました。使いやすさを向上させる工夫が大切です。
4位:懐中電灯・ランタン
懐中電灯は手持ちのものより据え置き型やヘッドライトなど、両手が空くものが便利です。
おすすめタイプ:
– ヘッドライト(両手が使える)
– ランタン(360度照明)
– 手回し充電式(電池不要)
5位:モバイルバッテリー・充電器
続いてモバイルバッテリーです。現在スマホは情報収集や連絡手段として絶対に欠かすことができないもので、緊急時にはライトにもなる一台数役の万能アイテム。
選び方のポイント:
– 容量10,000mAh以上推奨
– 複数ポート対応
– ソーラー充電機能付きが理想
6位:ラジオ
災害時のデマが増加している傾向があります。避難情報などは命に関わることもあるので、正しい情報が受け取れるラジオは手元に備えておきたい防災グッズのひとつです。
実際の使用レビュー:
とくにラジオは音もよくて、スマホの手回し充電ができるのはすごいと思いました。
7位:マスク・衛生用品
コロナ禍を経験した今、マスクは必需品です。避難所では感染症リスクが高まるため、十分な量を準備しておきましょう。
必要な衛生用品:
– マスク(1人1日3枚×7日分)
– ウェットティッシュ
– 消毒液
– 歯磨きシート
8位:防災リュック・避難袋
計30点の防災アイテムを備えた、ロングセラー商品です。持ち運びやすさは、比較したなかでもトップクラス。
選び方のポイント:
– 耐水・耐火性能の確認
– 容量と重量のバランス
– 反射材の有無
9位:タオル・ブランケット
着替え時の目隠しに便利だったという声もありました。多用途に使えるアイテムです。
活用方法:
– 防寒対策
– 目隠し・着替え用
– 止血・応急処置
– 濡れた物の拭き取り
10位:軍手・作業用手袋
瓦礫撤去や避難時の怪我防止に重要なアイテムです。
選び方のポイント:
– 滑り止め加工
– 耐切創性能
– サイズの確認
11位:救急セット
災害時には軽いケガに見舞われることもあるため、絆創膏や包帯などのアイテムも準備しておきましょう。
基本セット内容:
– 絆創膏各種
– 包帯・ガーゼ
– 消毒薬
– 痛み止め
12位:ブルーシート
ブルーシートは、床に敷いたり、風よけに使ったりと避難生活でとても役立ったという経験談も。
活用方法:
– 雨漏り対策
– 寝床の確保
– 荷物の保護
– 目隠し・間仕切り
13位:ラップ・アルミホイル
ラップ自体は、食器の汚れ防止以外にも、防寒や傷口の保護や細くより合わせて紐替わりにするなど、防災グッズとしてとても優秀。
14位:ガムテープ・養生テープ
応急修理や物の固定に重宝します。
15位:現金・小銭
災害時は電子決済が使えない場合があります。千円札と小銭を用意しておきましょう。
16位:常備薬・お薬手帳
持病がある方は、お薬手帳や普段飲んでいる薬などを手に取れる範囲に置いておくことをおすすめします。
17位:着替え・下着
下着や防寒具、雨具、防災手袋など、必要最低限のものだけを準備してください。
18位:マッチ・ライター
火起こしに必要な基本アイテムです。
19位:紙類(新聞紙・ティッシュ)
ティッシュペーパーを防災グッズとして用意するのであれば、水に溶けるタイプのものを選びましょう。
20位:ビニール袋・ゴミ袋
医療向け開発から生まれた、不快臭を防ぐゴミ袋です。様々な用途に活用できます。
実際に「いらなかった」防災グッズ【要注意リスト】
1位:コンパス・方位磁石
コンパスは方角を知りたい時に使用できる防災グッズですが、実のところ方角を知ったところであまり役に立ちません。
いらない理由:
– 避難所までの道のりを教えてくれない
– スマホのGPS機能で代用可能
– 重量とスペースの無駄
2位:ロープ
ロープは人命救助や瓦礫撤去の際に便利な防災グッズですが、素人がいきなり使用しようとしても上手に扱えません。
いらない理由:
– 専門的な知識・技術が必要
– 二次災害のリスク
– 代替品(紐・ビニール紐)で十分
3位:カップ麺・インスタントラーメン
カップ麺は保存食としても優秀で災害時にも役立ちそうに思えますが、お湯がないと作れないという致命的な欠点があります。
いらない理由:
– お湯を沸かせない環境では無意味
– 水を大量消費
– かさばる
4位:浄水器
ペットボトルの水があれば浄水する必要はありません。むしろ、浄水器を常備するなら水そのものを備蓄しておくのが賢明。
5位:手回しラジオ(一部製品)
手回しラジオは直近の情報収集に便利ですが、回し続けるのがとにかく大変との声が多くあります。
防災グッズの選び方【失敗しない5つのポイント】
1. 避難スタイルに合わせて選ぶ
防災時の避難には大きく分けて、「1次避難」と「2次避難」の2種類があります。
1次避難(緊急避難):
– 命を守る最低限のアイテム
– 軽量・コンパクト重視
– 持ち出し時間:数分
2次避難(避難所生活):
– 3日間程度の生活に必要なもの
– 快適性も考慮
– 持ち出し時間:数十分
2. 家族構成・人数を考慮する
防災グッズを用意する際には、まずは避難する人数を明確にすることが大切です。
人数別の目安:
– 1人用:基本セット + 個人的必需品
– 2人用:基本セット×2 + 共用品
– 家族用:人数分 + 子供・高齢者向け専用品
3. 保存期間と管理方法を確認する
食品だけでなく、電池も古くなると液漏れなどを起こし、いざというときに使えません。
管理のポイント:
– 定期的な点検・交換
– ローリングストック法の活用
– 使用期限の明記
4. 実用性を最優先に選ぶ
防災グッズは、災害下での避難生活の質を保つためのもの。命を救うだけでなく、命が助かった後の3つの「不」を解決することで、心のゆとりが生まれ、元気を生み出す。
3つの「不」とは:
– 不便:当たり前にあるものがない
– 不快:衛生面や環境の悪化
– 不自由:普段できることができない
5. 収納場所を事前に決める
「備蓄品はパントリーなど食料品や生活用品をストックする場所があれば、まずはそこで管理を。消費期限が分かるよう日付の付箋などを貼り、古い順に普段の生活で消費するローリングストックで備蓄しておきましょう。
防災グッズ購入時の注意点とコツ
1. 防災セットの選び方
防災セットには、食料品や衛生用品、情報収集ツールなど、生活に必要なものが入っています。自分で防災グッズを一から準備する場合、足りないものがあったり用意するのを忘れていたりする恐れがあります。
チェックポイント:
– 内容物の詳細確認
– 必要なものの過不足
– 品質と価格のバランス
2. 100均活用のコツ
ダイソーの防災グッズ・防災セットの新商品が登場!おすすめの避難グッズや防災用品をリストでチェック。
100均で購入できるもの:
– 簡易トイレ
– 保存袋
– 懐中電灯
– 電池
– マスク
3. 通販サイトの活用方法
アマゾンなどの通販サイトは、24時間いつでも注文ができ、種類も豊富な点が大きな魅力です。特にamazonや楽天では、レビューを参考に選ぶことができるため、商品の品質を見極めやすいです。
年代・性別別の防災グッズ選び
女性向け必需品
女性向けグッズで絶対必要なグッズNo1は生理用品・衛生用品です。特に、生理用品はほかの防災グッズで代用できないので、必要不可欠。
女性特有の必需品:
– 生理用品(1か月分)
– 化粧品(基礎化粧品)
– 着替え用ケープ
– 防犯ブザー
子供向け必需品
小さな子供がいる家庭では、大人用とは異なる準備が必要です。
子供向けアイテム:
– おむつ・おしりふき
– 粉ミルク・離乳食
– 着替え(多めに)
– おもちゃ・絵本
高齢者向け必需品
高齢者向けの防災グッズの優先度は、実際人によりけりです。大事なのは必要最低限のものだけを準備して荷物を軽くすること。
高齢者特有の必需品:
– 常用薬(1週間分)
– 入れ歯用品
– 老眼鏡
– 歩行補助具
防災グッズの保管・メンテナンス方法
保管場所の選び方
備蓄品は複数の場所に分散させることも大事。庭の倉庫や車庫など、直射日光が当たらず、温度変化も少ない場所に万一の備蓄品を置けるとベター。
理想的な保管場所:
– 玄関近く(1次避難用)
– 寝室(枕元用)
– パントリー(備蓄用)
– 車内(外出時用)
定期点検のスケジュール
防災グッズの効果を維持するためには、定期的な点検が欠かせません。
点検スケジュール:
– 毎月:電池残量、賞味期限確認
– 半年:内容物の総点検
– 年1回:全体の見直し・更新
災害別の防災グッズ選び
地震対策
– 家具固定器具
– ガラス飛散防止フィルム
– 避難用スリッパ
水害対策
– 土嚢袋
– 防水バッグ
– 長靴・レインコート
台風対策
– 養生テープ
– 防風ネット
– 予備の窓ガラス
停電対策
– ポータブル電源
– ろうそく・マッチ
– カセットコンロ
防災グッズの予算と優先順位
予算別おすすめプラン
最低限プラン(1万円以下):
– 水・食料(3日分)
– 懐中電灯・ラジオ
– 簡易トイレ
– 基本的な救急用品
充実プラン(3万円以下):
– 防災セット(1人用)
– 追加の備蓄品
– 衛生用品一式
– 暖房・調理器具
完全プラン(5万円以上):
– 家族分の防災セット
– ポータブル電源
– 本格的な備蓄品
– 家具固定器具
優先順位の決め方
災害時は備品が不足することが多く、日常とは異なる環境で生活する必要があります。そのため、不測の事態を考慮し、防災グッズを十分に用意しなければなりません。
優先順位:
1. 命に関わるもの(水・食料・医薬品)
2. 情報収集・通信手段
3. 衛生・健康管理
4. 快適性向上アイテム
実際の被災者からのアドバイス
東日本大震災の教訓
東日本大震災、熊本地震で被災し、2020年の水害では自宅避難した防災士の柳原志保さんに、本当に必要だった防災グッズと、非常持ち出し品をそろえるコツをお聞きしました。
熊本地震の体験談
熊本地震ではカップ麺の配給もあったようですが、ガス・水道・電気のライフラインが停止している状態では作れないと苦情があったそうです。
実用的なアドバイス
プロは防災リュックは買わない!?という観点から、市販品に頼りすぎず、自分の生活スタイルに合わせたカスタマイズが重要です。
防災グッズの最新トレンドと技術
最新技術を活用した防災グッズ
現代の防災グッズには、最新技術が取り入れられています。
注目のアイテム:
– ソーラー充電器
– 浄水ボトル
– 多機能ラジオ
– 圧縮食品
環境配慮型防災グッズ
環境に配慮した防災グッズも注目されています。
エコな選択肢:
– 再利用可能な容器
– 生分解性の食器
– 省エネ機器
まとめ:本当に役立つ防災グッズの選び方
災害はいつ発生するか分からないため、事前の準備が何より重要です。災害は突然起こるものだから、日々の備えが大切です。大きな震災から大雨、雷など、災害の規模を問わずあったら便利なものも多いので、普段から使えるものを防災グッズとして備えておくのがおすすめです。
防災グッズ選びの最重要ポイント
1. 実用性を最優先に選ぶ
– 実際の被災者の声を参考にする
– 理想より現実的な選択を
2. 継続的な管理を怠らない
– 定期点検の実施
– ローリングストックの活用
3. 家族構成に合わせてカスタマイズする
– 年齢・性別・健康状態を考慮
– 個人の特性に合わせた準備
4. 段階的に準備する
– 最重要品から優先的に
– 予算に応じた計画的な購入
防災グッズは、災害がいつ起こるかわからない現代において、私たちの命や安全を守るために欠かせないアイテムです。
今日からできる防災対策
1. 現在の備蓄状況をチェック
– 家にあるものをリストアップ
– 不足品の洗い出し
2. 最優先アイテムの購入
– 水・食料・トイレ用品
– 情報収集ツール
3. 保管場所の確保
– アクセスしやすい場所の確保
– 分散保管の実施
4. 家族との情報共有
– 避難計画の確認
– 連絡方法の決定
最後に
防災グッズは「備えあれば憂いなし」の精神で準備することが大切です。しかし、ただ揃えるだけでなく、実際に使えるかどうかを考えながら選ぶことが重要です。
「持ち出し用」「自宅避難用」「持ち歩き用」によって、防災グッズを使用するタイミングは異なるため、必要なものや用意する量が異なります。
本記事で紹介した情報を参考に、あなたの家族に最適な防災グッズを選んで、災害に備えた安心できる生活を送りましょう。災害対策は一度で終わりではなく、継続的な取り組みが必要です。定期的に見直しを行い、常に最新の状態を保つことを心がけてください。
家族の安全を守るために、今日からできることから始めていきましょう。