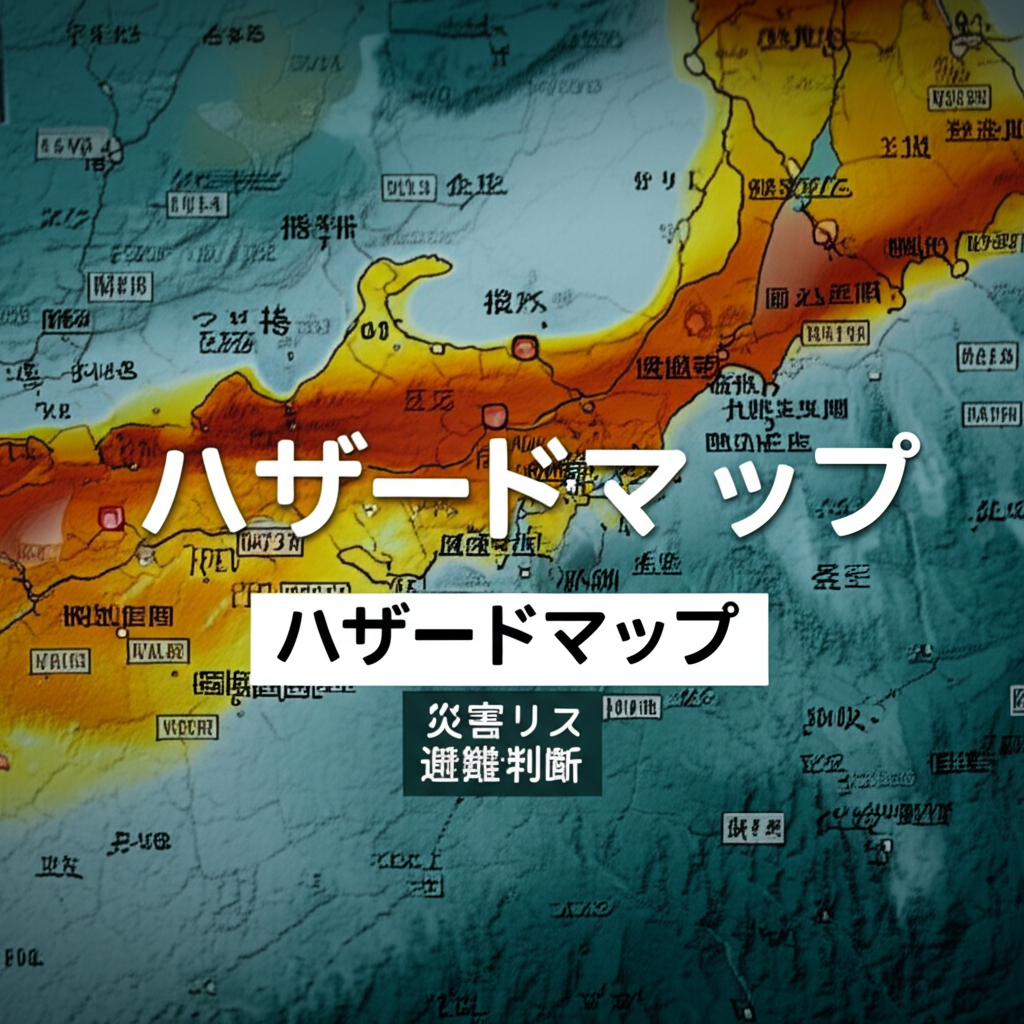災害復旧期間はどれくらい?家族を守るための基本知識
こんにちは!災害対策マニュアル編集部です。台風や地震などの自然災害が発生すると、「いつ日常生活に戻れるの?」と不安になりますよね。
2011年の東日本大震災では47万人、2016年の熊本地震では18万人以上が避難者になりました。ひとたび大きな地震が起これば、間違いなくライフラインはストップし、それまで通りの生活は続けられません。
災害復旧の現実を知ることで、適切な備えができるようになります。この記事では、停電対策・断水対策から避難所生活まで、災害復旧期間中に家族を守るための7つのポイントを詳しく解説します。
災害復旧期間の実態:思った以上に長期化する現実
ライフライン復旧までの期間
1995年の阪神淡路大震災、2011年の東日本大震災での、各ライフラインの復旧までの日数を見ると、復旧の順序は以下のようになっています:
1. 電気:比較的早く、数日~1週間程度
2. 水道:1~2週間程度
3. ガス:1~2ヶ月程度
内閣府による首都直下地震等による東京の被害想定によれば、各ライフラインの復旧目標日数は、電気で6日、上水道で30日、ガス(都市ガス)で55日となっています。
復興の心理的フェーズ
地震発生から最初の1ヵ月程度が【応急対応期】です。短時間のうちにさまざまな心理的イベントが続けざまに起きて、ただひたすらその対応に追われます。一方、1ヵ月を過ぎると、これまでの目まぐるしさとはうって変わって時間が進むのがゆっくりと感じられ、一日が長く感じられる【復旧・復興期】に入ります。
この心理的な変化を理解しておくことで、長期間の災害復旧期間にも精神的に備えることができます。
【ポイント1】停電対策:電気のない生活を乗り切る方法
停電が起こる理由と対策
浄水処理場の停電も原因の一つ。浄水処理場が台風や地震で停電すると、給水機能が停止する場合があります。停電は他のライフラインにも影響を与えるため、最優先で対策を講じる必要があります。
停電対策に必要なアイテム
照明関連
– LEDランタン(最低3個)
– 懐中電灯(一人1本)
– 単三・単四電池(各20本以上)
– 充電式LEDライト
電源確保
– モバイルバッテリー(大容量10,000mAh以上)
– 手回し充電器
– ソーラーパネル式充電器
– 車載インバーター
調理・暖房
– カセットコンロ
– カセットボンベ(1週間分)
– 保温シート・毛布
– 使い捨てカイロ(冬季)
停電時の行動で注意すべきこと
停電復旧時の電力サージによる家電の故障を防ぐため、主要な家電製品のコンセントは抜いておきましょう。冷蔵庫は扉を開けずに保冷効果を維持させることが重要です。
【ポイント2】断水対策:水不足を回避する備蓄方法
断水が起こる原因
地震による断水の原因は、水道管の破損や損傷です。水道管は地中に埋められており、地震による地面の揺れで継手部分が外れるなどして破損することがあります。
台風では川の水が溢れて水道管が壊れたり破裂することで、地域一帯への水道提供ができなくなる状態に。
断水対策の基本:必要な水の量
飲料水
– 一人1日3リットル×家族分×最低7日分
– 例:4人家族なら84リットル(2リットルペットボトル42本)
生活用水
– 一人1日20リットル×家族分×最低3日分
– 例:4人家族なら240リットル
断水対策グッズ
水の確保
– 給水タンク(20リットル以上)
– 給水袋(複数枚)
– 折り畳み式ウォータージャグ
– 浄水器・浄水タブレット
衛生用品
– ウェットティッシュ(大容量)
– 体拭きシート
– 手指消毒液
– 水のいらないシャンプー
トイレ対策
– 災害用トイレ(家族分×7日分)
– トイレットペーパー(多めに)
– 消臭剤・除菌剤
断水時のトイレ使用の注意点
断水時のトイレ使用はNGという情報もありますが、これは下水道システムの状況によります。集合住宅では特に注意が必要で、上階からの排水による逆流リスクもあります。
【ポイント3】避難所生活:長期化に備えた準備と心構え
避難所生活の実情
避難所の開設期間は災害発生後から7日間が基本です。しかし、実際には災害の収束後も自宅に戻ることができず、何ヶ月もの間避難所での生活を強いられている人が少なくありません。
例えば、熊本県を襲った豪雨災害から3ヶ月が経過した2020年10月4日時点では、被害を受けた人吉市、球磨村、八代市、芦北町、あさぎり町から避難してきた被災者、約700人が県内各所の避難所での生活を送っているのです。
避難所生活での5つの課題
1. 食事の問題
避難所では平時のように誰もが満足できる食事はすぐに用意できないことが実状であることも確かです。
2. 衛生面の問題
株式会社ネオマーケティングが2019年12月に実施した「避難所での宿泊経験者500人に聞く「災害時の避難所に関する調査」によると、回答者のうち297人、じつに59.4%もの人が避難所のトイレで悩みを感じた
3. プライバシーの問題
避難者にとって、最もストレスになることの1つがプライバシーの問題です。避難所生活では、見ず知らずの他人と一緒に生活することが前提となります。
4. 生活空間の狭さ
避難所は、体育館やホールなどの広いスペースを大人数で使用します。そのため、多くの方が生活空間の狭さを感じます。
5. 心理的ストレス
避難所生活では被災したショックにより不安がつきまといます。人によって被災の状況は違うとはいえ、大きな喪失感や環境の変化へのストレスを感じ、心のケアが必要になるかもしれません。
避難所生活を快適にするための持ち物
個人の快適性確保
– 耳栓・アイマスク
– 小さな枕やクッション
– 膝掛け・ブランケット
– 着替え(1週間分)
– 下着・靴下(多めに)
衛生用品
– 基礎化粧品・歯ブラシ
– 生理用品(女性)
– 薬(持病がある場合)
– マスク(感染症対策)
ストレス軽減用品
– 本・雑誌
– 音楽プレーヤー(イヤホン付き)
– 家族写真
– 好きな香りのアロマオイル
【ポイント4】災害後生活:復旧期間中の家族の健康管理
避難所生活での健康管理
避難所生活で健康に過ごすため、以下の点にご注意ください。(1) 水分・塩分補給をこまめに (2) 手を清潔に (3) 食中毒に注意 (4) 体の運動 (5) うがい・歯磨き (6) 十分な睡眠・休息 (7) マスクを着用 (8) 薬で困っている場合は相談を
子どもの心のケア
災害後の子どもは以下のような反応を示すことがあります:
– 夜泣きや悪夢の増加
– 食欲不振
– 甘えが強くなる
– 落ち着きがなくなる
これらは正常な反応であり、時間をかけて向き合うことが大切です。
高齢者への配慮
避難所生活では高齢者への特別な配慮が必要です:
– 薬の管理(お薬手帳のコピー)
– 介護用品の確保
– 栄養バランスの維持
– 適度な運動の継続
【ポイント5】避難所運営:自治で快適な環境を作る方法
避難所自治の重要性
避難所にいる人たちが、自分たちで自治をすることが挙げられます。いつまでも行政に頼っていると行政の支援の範囲でしか生活は変わらないので、『みんなの生活を改善していきたい』という気持ちをもって、ある程度自分たちで避難所内の生活環境を整えるような行動をします。
具体的な自治の方法
レイアウトの改善
体育館に避難をすると、来た順にそれぞれの場所が決まっていきます。そうではなく、『外への出入りが多い子ども連れの人は入り口の近くにしましょう』とか、トイレへ行くのに人を乗り越えて行くのだとしたら『ここに通路をつくりましょう』というように、少しでも生活がしやすいように、自分たちで改善していくことです。
役割分担の明確化
– 清掃当番
– 食事配布
– 情報収集・伝達
– 子どもの世話
– 高齢者・障がい者のサポート
避難所でのルールとマナー
避難所でのルールとマナー 避難所運営や避難所生活では、ルールを守ることが重要。避難者同士の助け合い・協力が不可欠で、要配慮者への心配りも必要。
【ポイント6】長期復旧に備える:災害用備蓄の見直し方法
備蓄の重要性
復旧までの期間を乗り越えられる備蓄が用意できているかどうかが避難生活の明暗を分けるということです。甚大な災害では、支援物資が運ばれるはずの道路が激しく損傷することも想定されます。そうなれば当然、水や食糧の供給は滞ります。
ライフライン別の備蓄戦略
電気復旧までの備蓄
電気はライフラインの中で、比較的早く復旧することから、ガスコンロの代替品となるIHクッキングヒーターやIH対応調理器具、電気ポットがあると便利です。
水道復旧までの備蓄
水に関しては、水道が復旧しない間も給水車から水をもらうために、給水タンクや給水袋が必須となります。
ガス復旧までの備蓄
ガスの復旧は遅くなることから、カセットコンロ利用のためのガスボンベを多く備蓄しておく必要があります。
備蓄品の管理方法
ローリングストック法
– 普段使いできるものを多めに買い置き
– 古いものから順番に使用
– 使った分だけ補充する
備蓄品のチェックリスト
– 賞味期限の確認(年2回)
– 電池の交換(年1回)
– 薬の期限確認(年4回)
– 子どもの成長に合わせた衣類の見直し(年1回)
【ポイント7】復興期の心構え:災害から立ち直るための精神的準備
復興のフェーズを理解する
フェーズ0【失見当期】(101/災害発生〜10時間)災害が発生すると、突然の出来事に誰もが自分の周囲で何が起こっているのかを客観的に判断できなくなってしまう状態に陥ります。
災害発生後の心理的な変化を理解することで、自分や家族の状況を客観視できるようになります。
家族との絆を深める機会として
災害という困難な状況を家族で乗り越えることで、より強い絆が生まれることも多くあります。普段はスマートフォンやテレビに気を取られがちですが、災害時には家族との会話や協力が増えるという側面もあります。
地域コミュニティとの関係構築
避難所生活や復旧作業を通じて、普段は交流のない近隣住民との関係が深まることもあります。これは将来の防災対策にもつながる貴重な財産となります。
災害復旧期間を乗り切るための具体的な行動計画
発災前の準備(平時)
家族会議の実施
– 避難場所の確認
– 連絡方法の決定
– 役割分担の決定
– 備蓄品の確認
地域の情報収集
– ハザードマップの確認
– 避難所の場所・設備確認
– 地域の防災訓練への参加
– 近隣住民との顔合わせ
発災直後の行動(72時間以内)
安全確認
– 家族の安否確認
– 自宅の被害状況確認
– 近隣の被害状況確認
– 避難が必要か判断
情報収集
– 公的機関からの情報収集
– ライフラインの復旧見込み確認
– 支援物資の配布情報確認
– 避難所の開設状況確認
長期化対応(1週間以降)
生活の安定化
– 定期的な生活リズムの確立
– 子どもの教育継続
– 仕事・収入の確保
– 心のケア
復旧・復興への参加
– 地域の復旧作業への協力
– 避難所運営への参加
– 行政手続きの実施
– 将来の生活設計
まとめ:災害復旧期間を家族全員で乗り越えるために
災害復旧期間は想像以上に長期化する可能性があります。特に、東日本大震災では復旧に5か月以上要した地域もあり、十分な備えが必要です。
今回ご紹介した7つのポイントを参考に、以下の行動を実践しましょう:
1. 停電対策:照明・電源・調理器具の準備
2. 断水対策:水の備蓄・給水用品・衛生用品の確保
3. 避難所生活:快適性確保・健康管理・コミュニケーション
4. 災害後生活:健康管理・子どもと高齢者への配慮
5. 避難所運営:自治への参加・ルールとマナーの遵守
6. 長期復旧対策:備蓄品の見直し・管理方法の確立
7. 復興期の心構え:精神的準備・地域との関係構築
現代社会に生きる私たちにとって、電気が使えないことは「不便」で片付けられるものでなく、命にかかわること、文字通り「死活問題」になっているのです。
だからこそ、普段からの備えが何より大切です。災害は必ず起こるものと考え、家族みんなで防災意識を高めていきましょう。
「備えあれば憂いなし」という言葉がありますが、適切な備えをすることで、災害が発生しても家族を守り、一日も早く日常生活に戻ることができます。
今日からでも遅くありません。まずは家族で話し合い、備蓄品のチェックから始めてみませんか?あなたの行動が、愛する家族の命と未来を守ることにつながります。
この記事が、あなたとご家族の防災対策の一助となれば幸いです。災害に負けない、強い家族を一緒に築いていきましょう。