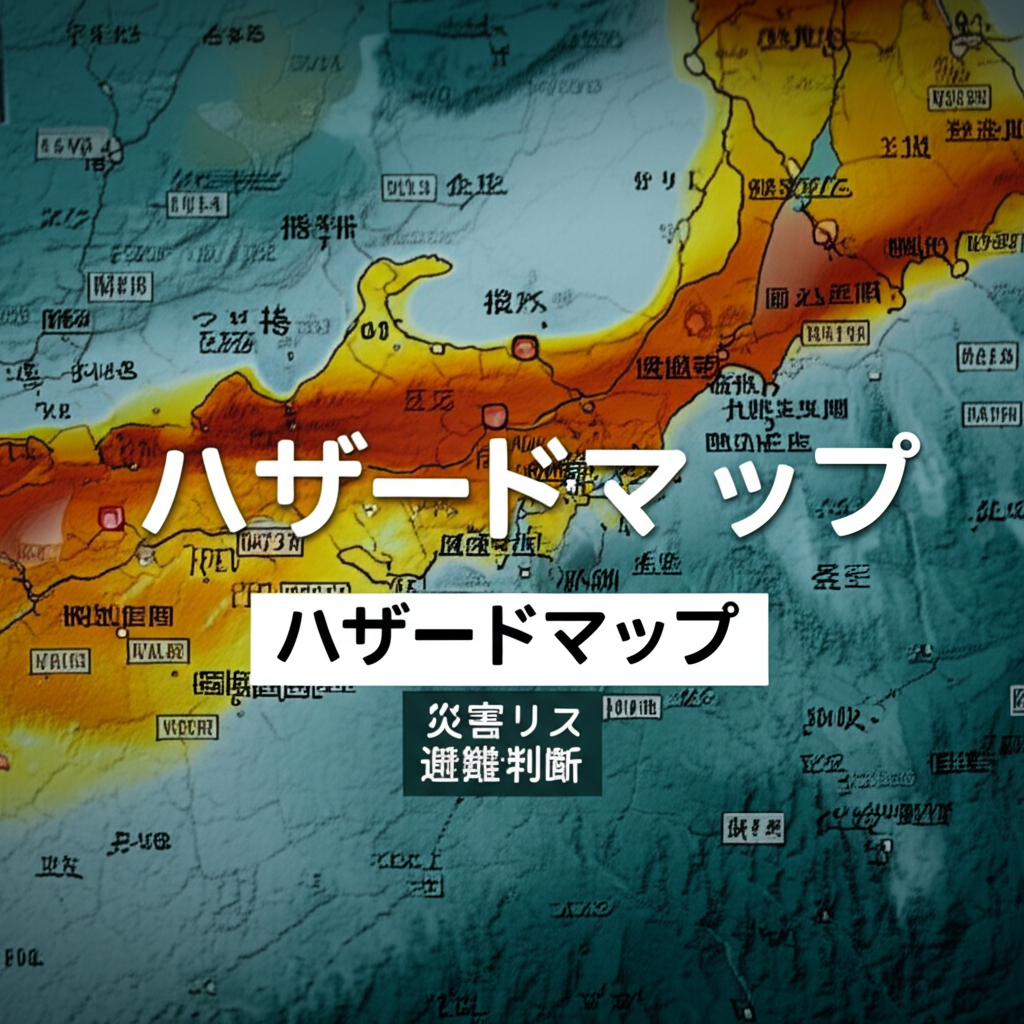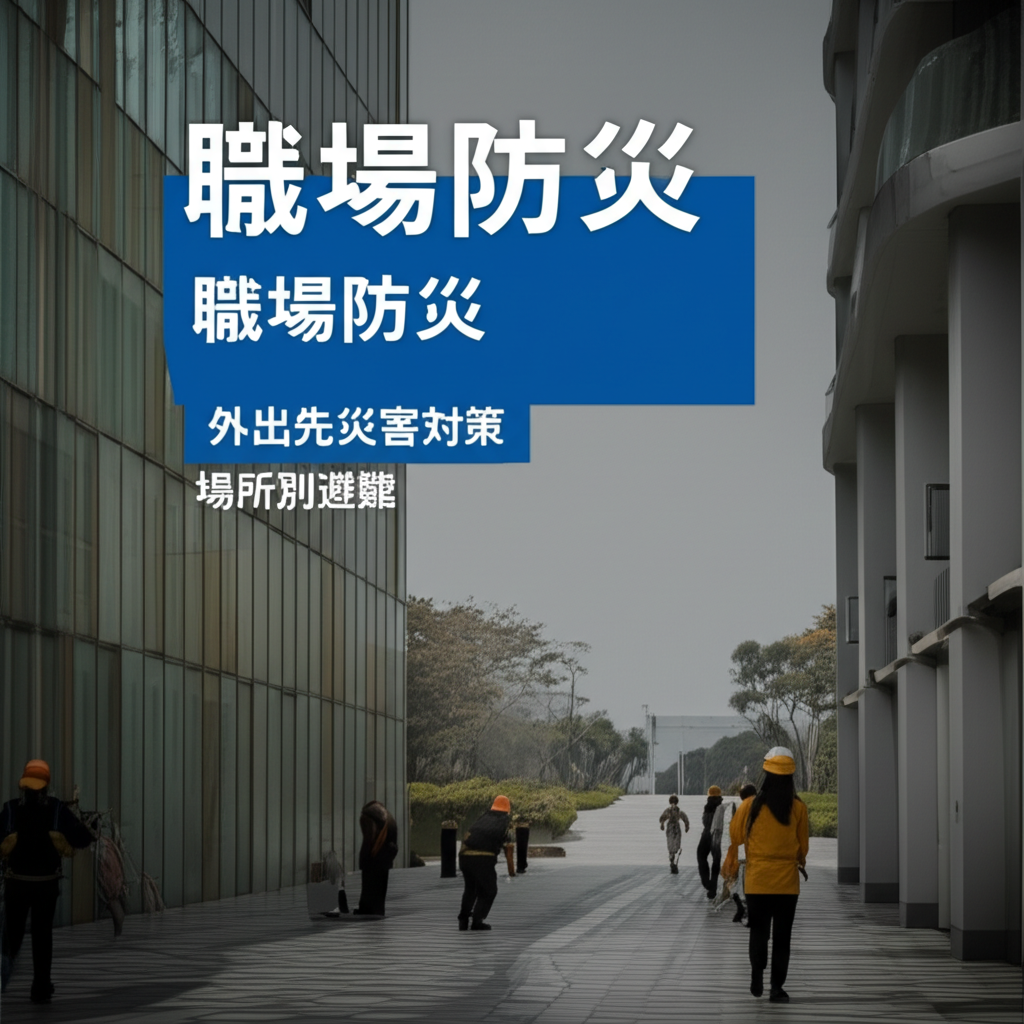はじめに:なぜ災害時の情報収集・安否確認が生死を分けるのか
災害大国日本に住む私たちにとって、いつ大きな災害が襲ってくるかわからない状況は当たり前となってしまいました。しかし、多くの家庭で見落とされがちなのが、「災害時の情報収集と安否確認の備え」です。
時系列別に情報収集に利用した手段をみると、発災時から復旧期までの期間を通じて携帯通話の利用が最も多く、次いで地上波放送、SNS(LINE(家族・友人・知人等))となっているという過去の災害データからもわかるように、災害時の情報収集手段は多様化しています。
しかし、「災害時にスマートフォンや携帯電話などの通話機能が使用できなくなった場合、代替の連絡手段があるか」という質問に関しては「ない」と回答した方が95.6%を占めていましたという現実があります。
今回は、災害時の情報収集から通信障害時の対策まで、家族の安全を守るために本当に必要な知識を、具体的な方法とともにお伝えします。
災害時の情報収集:命を守る4つの情報源とその活用方法
1. 公的機関からの正確な情報を最優先に
災害時の情報収集で最も重要なのは、正確性です。デマや憶測に惑わされず、確実な情報源から情報を得ることが家族の安全につながります。
主要な公的情報源
– 気象庁:地震情報、気象警報・注意報
– 国土交通省:河川水位、道路情報
– 各自治体の公式サイト:避難情報、避難所開設状況
– 消防庁:被害状況、緊急対応状況
災害情報 2025年08月21日令和7年8月大雨による土砂流出推定範囲と土砂・流木推定量 -鹿児島県姶良市・霧島市周辺を公開しましたのように、災害発生後も継続的に詳細情報が公開されるため、定期的なチェックが重要です。
2. テレビ・ラジオ:停電時も頼りになる情報源
災害時には、テレビ・ラジオ・行政無線が発信する被災者情報を聞き取りましょう。特にラジオは、停電時でも電池で動作するため、災害時の重要な情報収集手段です。
災害時のテレビ・ラジオ活用のコツ
– 手回し充電式のラジオを防災グッズに常備
– スマートフォンのラジオアプリも併用
– 地域のコミュニティFM局の周波数を事前確認
– 停電に備えて乾電池式ラジオも準備
3. SNS・インターネット:リアルタイム情報の宝庫
X(旧Twitter)は、リアルタイムで情報共有ができるSNSです。この特徴を活かせば、災害時の情報収集にも活用できますが、情報の真偽を見極める目が必要です。
SNS活用時の注意点
– 公式アカウント(自治体・警察・消防)をフォロー
– 情報の出所を必ず確認
– 拡散前に複数の情報源で裏取り
– デマ情報は拡散しない
4. 防災アプリ:オールインワンの情報収集ツール
最近では、複数の情報源を統合した防災アプリが充実しています。災害時、電話やメールが使えない状況でも、専用アプリならインターネット経由で情報確認ができます。
おすすめの防災アプリ機能
– プッシュ通知による緊急情報配信
– ハザードマップとの連携
– 避難所情報の自動更新
– 家族間の位置情報共有
災害時の安否確認:家族とつながる7つの確実な方法
方法1:災害用伝言ダイヤル(171)- 音声で伝える確実な手段
「災害用伝言ダイヤル171」は、NTT東日本・西日本が大規模災害発生時に設置する伝言サービスです。震度6弱以上の地震が発生した際に自動開設される、最も確実な安否確認手段の一つです。
使用方法
1. 「171」をダイヤル
2. ガイダンスに従って操作
3. 被災地の電話番号をキーに登録
4. 30秒以内でメッセージを録音
事前に家族で決めておくべきこと
– キーとなる電話番号(通常は自宅の固定電話)
– 暗証番号の設定(プライバシー保護のため)
– 毎月1日の体験利用で操作方法を確認
方法2:災害用伝言板(Web171)- インターネット経由の文字情報
災害用伝言板(web171)の提供がスタートし、スマホ対応や伝言登録の通知機能など現代に合った機能が追加されています。文字でのやり取りができるため、詳細な状況を伝えやすいのが特徴です。
Web171の利点
– 写真付きメッセージの送信可能
– 災害用伝言ダイヤルとの連携
– 複数の連絡先への同時通知
– パソコンからも利用可能
方法3:携帯電話会社の災害用伝言板サービス
各携帯電話会社が独自に提供するサービスも重要な安否確認手段です。
NTTドコモ
ドコモの携帯電話やスマートフォンからご自身の状況を登録できます。登録された安否情報は全世界から確認できます
au(KDDI)
KDDI(au)・沖縄セルラーでは、災害時の家族・友人・知人の安否確認サービス(災害用伝言板)を提供しています
ソフトバンク
同様の災害用伝言板サービスを提供し、安否情報の登録・確認が可能
方法4:LINE安否確認 – 最も身近な連絡手段
LINEの国内利用者数は、約9,600万人以上(2024年1月現在)と国内で最も多く利用されているSNSです。災害時には特別な機能が自動的に表示されます。
LINE安否確認の特徴
– 震度6以上の災害で自動表示
– ワンタップで安否報告可能
– プロフィールに安否ステータス表示
– 位置情報の共有機能
家族のLINEグループ活用術
– 事前に家族専用のグループを作成
– 位置情報共有の方法を練習
– 既読機能を活用した安否確認
– 写真での現在状況報告
方法5:SMS(ショートメッセージ)- 災害に強い通信手段
インターネットではなく電話の信号線を使用するSMSは災害に強いため、実際に東日本大震災の際にも問題なくつながった実績があります。
SMS活用のメリット
– メールアドレス変更の影響なし
– 迷惑メール判定されにくい
– 高い到達率と開封率
– 携帯電話番号のみで送信可能
方法6:公衆電話 – 停電時も使える確実な手段
公衆電話はNTTから独自の電力供給を受けているため、停電が起きたとしても電話が通じます。災害時には無料開放される場合もあります。
公衆電話の種類と使い方
– デジタル公衆電話(グレー・緑):災害時は硬貨不要で利用可能
– アナログ公衆電話(黄色・ピンク):10円硬貨またはテレホンカードが必要
事前準備
– 自宅・職場周辺の公衆電話の場所を確認
– テレホンカードの準備
– 10円硬貨の常時携帯
方法7:企業の安否確認システム – 職場と家族の両方をカバー
勤務先の企業が、家族の安否も確認できる安否確認システムを導入していのなら、積極的に活用しましょう。
企業システム活用のメリット
– 家族情報の事前登録
– 自動一斉配信機能
– セキュリティ管理の徹底
– 職場と家族への同時連絡
通信障害対策:つながらない時の代替手段と事前準備
通信障害が発生する理由と対策
災害時には、固定電話や携帯電話が一部の被災地の回線に集中するため「輻輳(ふくそう)」という状態になり、電話がつながりにくくなってしまいます。
通信障害の主な原因
1. 回線の混雑(輻輳):一斉に電話をかけることによる回線パンク
2. 基地局の被災:地震や津波による物理的な破壊
3. 停電:電力供給停止による通信設備の機能停止
4. 設備の故障:災害による通信機器の破損
通信障害時の代替手段
1. データ通信の活用
スマートフォンや携帯話による通話は回線を占有していますが、パケット通信は1つの回線をシェアするため、災害時の利用が推奨されています。音声よりもデータ量が少ない「SMS」などのショートメールを使用しましょう。
2. 公衆無線LAN(Wi-Fi)の利用
– 避難所や公共施設の無料Wi-Fi
– 000000JAPAN(災害時無料開放)
– コンビニエンスストアのWi-Fi
3. 衛星通信の活用
– 衛星電話(レンタル可能)
– 衛星インターネット
– 災害対策用衛星通信サービス
家庭でできる通信障害対策
電源確保対策
20,000mAhの大容量モバイルバッテリーでも、スマホの充電回数は4~5回と長く持ちません。ソーラーパネルとのセットならコンセントなしでポータブル電源を充電できます。
推奨する電源確保グッズ
– 大容量ポータブル電源(500Wh以上)
– ソーラーパネル(折り畳み式)
– 手回し充電器
– 乾電池式携帯充電器
通信機器の多様化
– メイン端末(スマートフォン)
– サブ端末(タブレット、ガラケー)
– ラジオ(AM/FM/短波対応)
– 無線機(特定小電力トランシーバー)
実践的な事前準備:家族で取り組む災害時情報収集・安否確認計画
家族会議で決めるべき7つのポイント
災害が起こったとき、どのように連絡を取り合うか家族と事前に話し合っておくことが大切です。
1. 連絡手段の優先順位決定
1位:LINE(普段使い慣れている)
2位:災害用伝言ダイヤル(171)
3位:SMS(ショートメッセージ)
4位:各携帯会社の災害用伝言板
5位:公衆電話
2. 集合場所の指定
– 第1避難場所:近所の一時避難場所
– 第2避難場所:校区の避難所
– 第3避難場所:広域避難場所
– 県外親戚宅の連絡先
3. 重要連絡先の共有
– 家族全員の携帯電話番号
– 勤務先・学校の緊急連絡先
– 県外の親戚・知人(中継役)
– かかりつけ医の連絡先
4. 情報収集ルールの策定
– 担当者の決定(情報収集、連絡調整)
– 情報源の優先順位
– デマ対策のルール
– 定期連絡のタイミング
5. 子どもの迎えに関する取り決め
お子さんがいらっしゃる場合、通っている幼稚園や学校などでは災害時にどのような対応を取るのか確認しておきましょう。
6. 外出時の対応方法
– 職場での待機判断基準
– 帰宅ルートの複数確保
– 徒歩帰宅時の連絡方法
– 公共交通機関停止時の対応
7. 特別な配慮が必要な家族への対応
– 高齢者・要介護者への支援方法
– ペットの避難計画
– 常用薬の確保方法
– 医療機器使用者の電源確保
定期的な訓練と見直し
月1回の確認事項
– 防災アプリの動作確認
– 連絡先情報のアップデート
– 充電器・バッテリーの点検
– 非常時持ち出し袋の確認
年4回の訓練実施
– 災害用伝言ダイヤル(171)の体験利用
– 避難経路の歩行訓練
– 家族間の連絡訓練
– 情報収集手段の実際の使用
年1回の計画見直し
– 家族構成の変化への対応
– 新しい情報収集手段の検討
– 避難場所情報の更新
– 連絡先リストの整理
情報収集・安否確認のための防災グッズリスト
通信関連グッズ
– スマートフォン(防水ケース付き)
– 携帯用充電器・ケーブル類
– ポータブル電源(容量500Wh以上)
– ソーラー充電器
– 手回し充電ラジオ
– 特定小電力トランシーバー
– 筆記用具・メモ帳
情報収集グッズ
– 電池式テレビ
– 短波ラジオ
– 防災アプリインストール済みタブレット
– 地域ハザードマップ(防水加工)
– 家族連絡先リスト(ラミネート加工)
その他必需品
– 現金(公衆電話用10円硬貨含む)
– テレホンカード
– 身分証明書のコピー
– 保険証のコピー
– 家族写真(はぐれた時の確認用)
災害時情報収集の成功事例と失敗から学ぶ教訓
成功事例:東日本大震災における情報収集の工夫
事例1:複数手段の併用で家族全員の安全確保
宮城県の田中家(仮名)では、地震発生直後から以下の手順で情報収集と安否確認を実施:
1. immediate phase(発災直後):ラジオで基本情報収集
2. Short term(30分後):災害用伝言ダイヤルで安否報告
3. Medium term(2時間後):避難所でのテレビ情報確認
4. Long term(6時間後):携帯電話復旧後にLINE活用
この家庭では、事前に情報収集手段の優先順位を決めていたため、パニックになることなく適切な行動が取れました。
事例2:地域コミュニティとの情報共有
万が一連絡がとれない場合のことも考えて、最終的に家族で落ち合う場所を決めておくことも必要ですという準備をしていた家庭では、近所の方々との情報共有が功を奏しました。
失敗事例から学ぶ重要な教訓
失敗事例1:単一手段への依存
「スマートフォンがあれば大丈夫」と考えていたB家では、基地局の被災により全く連絡が取れない状況に。事前に複数の連絡手段を準備していなかったため、家族の安否確認に丸一日かかってしまいました。
教訓:一つの通信手段だけに頼らず、最低3つの異なる方法を準備する
失敗事例2:デマ情報による混乱
SNSで拡散された「○○地域で大規模火災発生」という未確認情報を信じ、不要な避難行動を取ってしまったC家。実際にはデマ情報で、余計な体力消耗と時間ロスを招きました。
教訓:情報源の確認と複数ソースでの裏取りを必ず実施する
熊本地震から学ぶ現代的な対応方法
熊本地震では、発災時から復旧期までいずれの時期においても携帯通話や携帯メール、SNSなど携帯電話やスマートフォンによって利用する情報収集手段が多く活用されている。
現代の災害対応では、従来の手段に加えてデジタルツールの活用が不可欠となっています。しかし、デジタル偏重ではなく、アナログ手段とのバランスが重要です。
まとめ:災害時に家族を守るための情報収集・安否確認の心得
災害時の情報収集と安否確認は、事前の準備が全てを決めると言っても過言ではありません。地震は、いつ何処で起こるか正確に予測することはできません。普段から家族で話し合い、緊急時の行動を決めておくことが大切です。
今すぐ実践すべき5つのアクション
1. 家族会議の開催:今週末に必ず実施し、連絡手段と集合場所を決定
2. 防災アプリのインストール:家族全員のスマートフォンに同じアプリを導入
3. 災害用伝言ダイヤルの練習:毎月1日の体験利用を家族で実施
4. 連絡先リストの作成:ラミネート加工して各自が常に携帯
5. 通信機器の充電状況確認:毎日のバッテリーチェックを習慣化
継続的に取り組むべき3つのポイント
1. 情報の定期更新:連絡先、避難場所情報を年4回見直し
2. 新技術への対応:新しい防災アプリや通信手段の情報収集
3. 地域との連携強化:自治体の防災訓練への積極的参加
災害時の情報収集と安否確認は、技術の進歩とともに手段が多様化していますが、基本的な考え方は変わりません。「複数の手段を準備し、家族で共有し、定期的に練習する」この3つの原則を守ることで、いざという時に家族の安全を守ることができるのです。
いざというときに迷わず使えるように、災害用伝言サービスを体験しておきましょう。明日起こるかもしれない災害に備えて、今日から準備を始めましょう。
あなたの家族の安全は、今この瞬間の準備にかかっています。この記事を読んだ後は、必ず家族と災害時の情報収集・安否確認について話し合ってください。それが、愛する家族を守る第一歩となります。