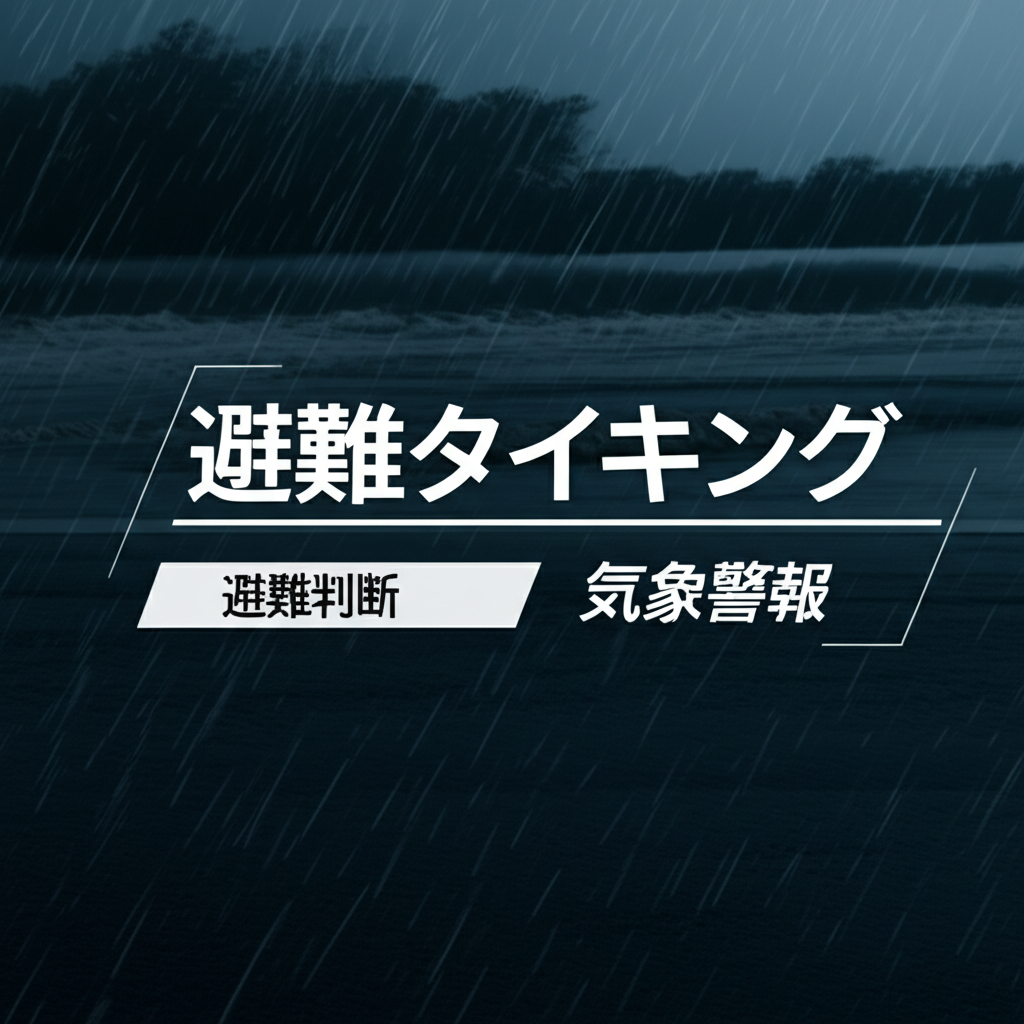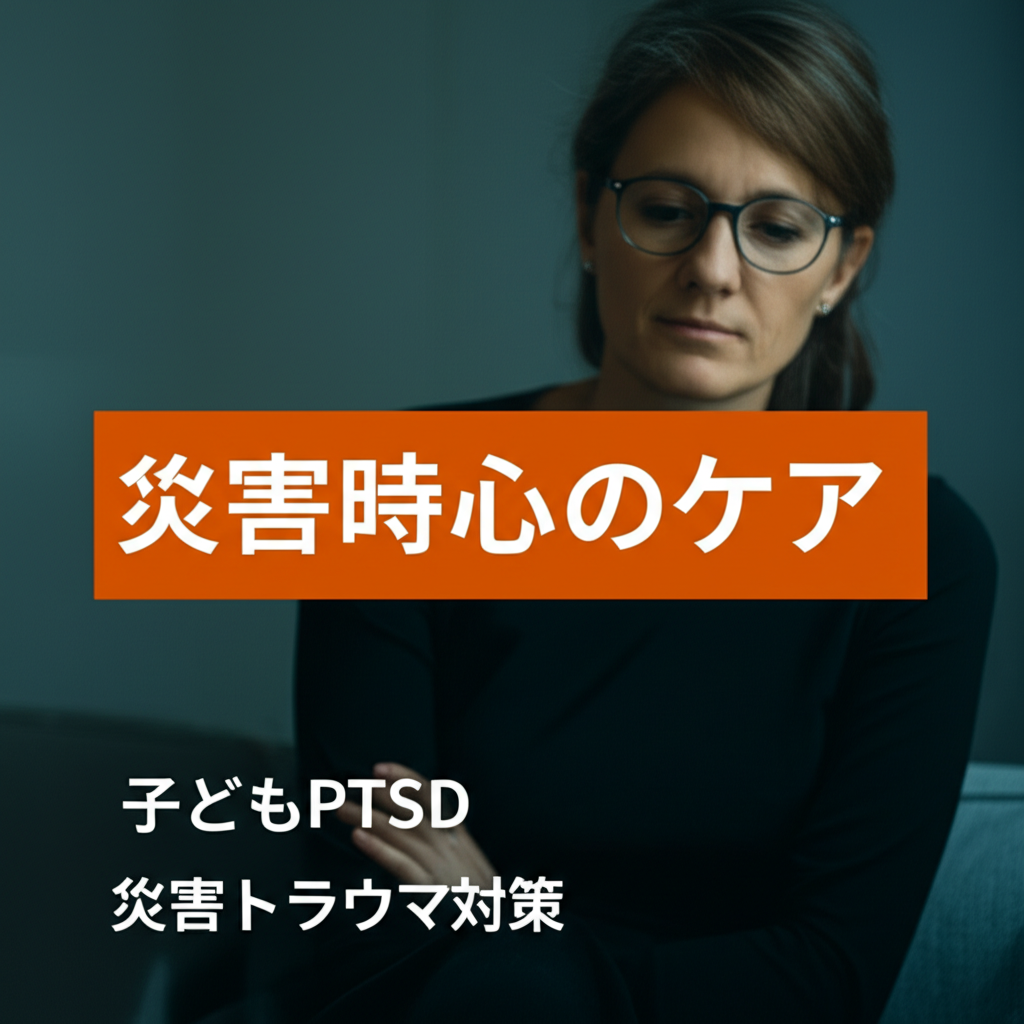災害時こそ見直したい、女性のための防災対策
災害はいつ起こるかわからない——。そんな現実に直面する日本で暮らす私たち女性にとって、一般的な防災対策だけでは十分ではありません。緊急避難中に人口の約6%が生理用品を必要としていますという統計が示すように、女性特有のニーズへの備えは決して「あれば良い」レベルのものではなく、命と健康を守る必需品なのです。
東日本大震災や熊本地震の教訓から浮き彫りになったのは、”防災担当部署に女性職員が1人もいない状況”による女性のニーズの見落としでした。こうした現実だからこそ、私たち女性自身が主体的に防災について学び、準備していく必要があります。
この記事では、災害大国日本で家族を守る主婦として、また一人の女性として知っておくべき女性防災の重要ポイントを、具体的かつ実践的にお伝えしていきます。
統計で見る女性防災の現状と課題
災害時の女性特有の困りごとは想像以上に深刻
生理用品を用意している方が約9割という調査結果があるものの、その一方で災害時の女性支援は十分とは言えない状況が続いています。
災害時に起こる犯罪は通常の3倍とも言われています。被災女性向けに開設されたホットラインには震災後、暴力や強姦などの相談が数百件寄せられたそうです。これは単なる生活の不便さを超えた、女性の生命と安全に関わる深刻な問題です。
備蓄の現実と理想のギャップ
多くの女性が生理用品の重要性を理解している一方で、経血量が多いために、支給された生理用品では足りなかったのです。そもそも経血の量には個人差がありますという現実があります。画一的な備蓄では、実際の避難生活で十分な対応ができないのが実情です。
生理用品備蓄の基本:何をどのくらい準備すべきか
必要量の計算方法と備蓄のコツ
個人差もありますが、生理期間が7日間として、一日5~6枚取り換えた場合、35~42枚になりますが基本的な計算ですが、災害時には交換頻度が下がる可能性も考慮する必要があります。
実際の備蓄では以下の点を考慮しましょう:
1. 通常使用量の1.5倍を基準とする
– 普段より大きめサイズを含める
– いつもよりワンサイズ大きいナプキンを用意しておくと安心です
– 夜用ナプキンは交換回数を減らせるため多めに備蓄
2. 個人差を考慮した備蓄
– 経血量が多い方は通常の2倍量を目安に
– 生理周期が不安定な方は3周期分を準備
– 家族内での女性の人数×個別必要量で計算
3. 保管方法の工夫
密閉袋に入れることで湿気やホコリの影響を少なくし、生理用品の品質を維持しやすくなりますことから、防水性のある密閉袋での保管は必須です。
ローリングストック法で新鮮な備蓄を維持
生理用品などの衛生用品は常に1周期分多めに買うローリングストック法を活用しましょう。未開封の状態でナプキンは約3年、タンポンは約5年で使い切ることが推奨されていますため、定期的な入れ替えが重要です。
進化する生理用品:月経カップと吸水ショーツの災害時活用法
月経カップの災害時メリット
最新の生理用品として注目される月経カップは、災害時に特に威力を発揮します:
災害時における月経カップの優位性:
– 最長で12時間連続使用が可能でトイレ回数を削減
– 小さくて繰り返し使えるので、荷物がかさばらず持ち運びやすく、さらに臭いも気にならない
– 長期間の避難生活でも生理用品が尽きる心配がない
使用時の注意点:
繰り返し使うことが可能ですが交換時に水で洗う必要があります。災害中、水道が止まってしまった場合には使用するのが少し難しいかもしれませんが、ウェットティッシュや清浄綿などがあるとシリコン製のカップなので、拭いて使用することができます
吸水ショーツの活用術
吸水ショーツ(吸収型サニタリーショーツ)とは?生理2日目など経血量が多い日は、ナプキンや月経カップとの併用をおすすめしているメーカーがほとんどです。
災害時の吸水ショーツのメリット:
– ナプキン交換の頻度を減らせる
– 下着の汚れを防ぎ、洗濯できない状況でも衛生的
– 生理時以外でも、尿もれやおりものが気になる時にもおすすめです
最適な組み合わせ:
月経カップ+吸水ショーツを組み合わせた生理期間の過ごし方が、災害時の最強の組み合わせです。カップで経血をキャッチし、吸水ショーツが万が一の漏れをカバーする二重の安心が得られます。
避難所生活での健康管理とプライバシー対策
女性特有の健康リスクと対策
女性は、清潔な状態を保てないことや、冷えやストレスが原因で、生理不順になったり、膀胱炎になるなど、身体の不調が出やすいと言われていますため、以下の対策が重要です:
1. 清潔保持のための備え
– デリケートウェットシートを使うことをおすすめします
– パンティライナーの活用で下着交換頻度の軽減
– キリで6か所程度穴を開けたペットボトルのフタを用意しておくと、非常時に役立ちます(簡易洗浄ボトル作成)
2. 防寒とストレス対策
– 体を冷やさない衣類の準備
– プライバシー確保のためのマスク活用
– 使い慣れた生理用品の備蓄
プライバシー確保と安全対策
避難所では全て周りの人に見える環境です。発災から2ヶ月経つまで女性用の更衣室がなかったという状況も珍しくありません。
自衛策として備えておくべきもの:
– 防犯ブザーや笛を常に持ち歩く・寝るときもそばにおいておく
– 着替え用の大判タオル
– 黒などの濃い色で、においが出にくい厚めの袋(汚物処理用)
安全確保のための行動指針:
避難所で人目の少ない場所に行く必要があるときは、必ず周りに声を掛け合い、単独で動かないようにしてください
災害時のストレス管理と心理的ケア
女性が抱えやすい精神的負担
災害がもたらす心理的影響は大きく3つに分けて考えると理解しやすいでしょう。恐怖や直後の記憶が突然蘇ったり、思い出さないように関連する刺激を避けたり、あるいは気が高ぶって些細な刺激に過敏に反応するといったトラウマ反応に加えて、女性特有のストレスが重なります。
女性特有のストレス要因:
– 生理への不安と恥ずかしさ
– 清潔への強いこだわりと現実のギャップ
– 子どもや高齢者への責任感
– 女性はメイクができないことがストレスにつながる場合も
心理的負担を軽減する準備
1. 精神的支えになるアイテムの準備
– 最低限のメイク用品(口紅、眉ペンシルなど)
– 香り付きのウェットティッシュ
– 普段使用している鎮痛剤
2. 情報とコミュニケーション手段
“避難所の運営が男性だけに任された場合などに女性の意見が取り入れられなかった”状況を避けるため、女性同士のネットワーク構築が重要です。
コンパクトで効率的な女性防災用品の収納術
防災リュック内での生理用品収納のコツ
限られたスペースを有効活用するための工夫:
1. 圧縮保存の活用
ナプキンは、圧縮袋を活用するとコンパクトに収納できます。ジッパー付きの圧縮袋を使用することで、防水効果も期待できます。
2. 多目的アイテムの選択
– 生理用ナプキンはハンカチよりも衛生的で肌に優しく吸収力が抜群なので、避難所まで逃げる途中などにケガをしてしまった場合には応急手当(止血)として大活躍します
– タンポンと月経カップの併用で必要個数を削減
3. 段階的な準備
– 持ち出し用(1-2日分)
– 備蓄用(1週間分)
– 長期避難用(1ヶ月分)
家族全体での女性防災対策
家族内での情報共有
– 女性の生理周期や特性を家族が把握
– 避難時の役割分担の明確化
– 子どもへの年齢に応じた説明
地域コミュニティとの連携
– 女性防災リーダーの育成
– 避難所運営への女性参加の推進
– 生理用品の融通システム構築
実体験から学ぶ:被災者の声と教訓
東日本大震災での実際の困りごと
外出の予定があったのですが、目的地が家から近かったため「短時間で済むだろ」と、生理用品を何も持たずに出かけてしまい、その出先で地震が起きたのですという実体験は、日常の「まさか」への備えの重要性を物語っています。
避難所での現実的な課題:
– 経血量が多いために、支給された生理用品では足りなかった個人差への対応不足
– 汚れたお手洗で着替えるしかありませんでした。汚いトイレでとても毎日着替える気にはなれず、下着さえも毎日交換できずに生理用品を使用している方もいましたプライバシーの欠如
避難所運営の改善に向けて
女性ならではの視点を積極的に要望に出し、避難所の環境を整えていく意識を持ちましょうことが、将来の災害対応改善につながります。
女性が声を上げるべきポイント:
– 生理用品配布場所のプライバシー確保
– 女性専用更衣室の設置
– 授乳室や母子避難スペースの確保
– 女性による避難所運営への参加
まとめ:今すぐ始められる女性防災対策
災害時の女性防災は、単なる「備え」を超えた生命と尊厳を守る重要な取り組みです。”生理”。最近やっとナプキンが買えない生理の貧困や災害時の生理用品の必要性など、さまざまな場面でクローズアップされ、女性が困らずに過ごせる社会の実現に向けての働きかけが活発になってきましたという変化の中で、私たち女性自身がより積極的に防災に取り組む必要があります。
今すぐできる行動リスト:
1. 現在の生理用品備蓄量をチェックし、個人に合った必要量を計算
2. 月経カップや吸水ショーツの導入を検討
3. 防災リュックに女性特有のアイテムを追加
4. 家族や地域コミュニティとの情報共有
5. 避難所や避難経路の確認(女性の視点から)
災害は待ってくれません。しかし、適切な準備と知識があれば、女性特有の困難も乗り越えることができます。この記事でお伝えした内容を参考に、あなた自身と大切な家族を守る女性防災対策を今日から始めてください。
一人ひとりの女性が備えることで、災害時の社会全体の女性への配慮も向上していきます。私たち女性の力で、災害に負けない安心で安全な社会を作っていきましょう。