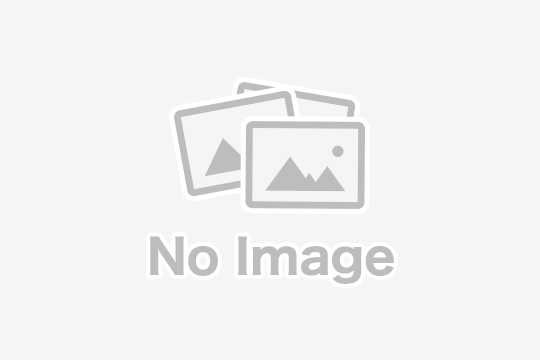家族を守るための防災準備、何から始めればいい?
災害大国日本に住む私たちにとって、防災グッズの準備は避けて通れない課題ですよね。特に小さなお子さんがいるご家庭では、いざという時に何が必要なのか不安に感じることも多いのではないでしょうか。実は防災グッズ選びに「正解」はなく、家族構成やライフスタイルによって必要なものは変わってきます。この記事では、防災初心者の方でも迷わず準備できる本当に必要な防災グッズをご紹介します。
防災グッズを準備する前に知っておきたい3つのポイント
防災グッズを揃える前に、まずは基本的な考え方を押さえておきましょう。これを知っているだけで、無駄な買い物を避けられますよ。
1. 「72時間」を生き抜くための準備を
大規模災害が発生した場合、公的支援が本格的に始まるまでに約72時間(3日間)かかると言われています。この「72時間の壁」を自力で乗り越えるための準備が必要なんです。
我が家でも東日本大震災の時、テレビで被災地の様子を見ながら「うちは大丈夫かな」と不安になったことを今でも覚えています。あの時は本当に何も準備していなくて…。でも、実際に必要なのは高価な専門装備ではなく、日常生活の延長線上にある物が多いんですよ。
2. 家族構成に合わせたカスタマイズが重要
市販の防災セットは便利ですが、必ずしも家族全員に合ったものとは限りません。特に小さなお子さんがいるご家庭では、おむつや粉ミルクなど特別な準備が必要です。
うちの子が小さかった頃、防災袋を見直したら、子どもの成長に合わせて中身を全部入れ替えなきゃいけないことに気づいて愕然としたことがあります。子どもの成長スピードって本当に速いですよね。定期的な見直しが欠かせないんです。
3. 日常で使えるものを選ぶ
防災グッズは「買って終わり」ではなく、定期的なメンテナンスが必要です。できるだけ普段の生活でも使えるものを選べば、ローリングストック(使った分を補充する方法)が実践しやすくなります。
私も最初は「防災専用」と考えていましたが、結局使わないまま賞味期限が切れてしまうことが多くて…。今では普段使いできる品を意識的に選んでいます。例えば、LEDランタンは停電時だけでなく、キャンプやベランダでの夕涼みにも活躍しています。
初心者が最初に揃えるべき防災グッズ15選
では、実際に準備すべき防災グッズを見ていきましょう。初心者の方は、まずはこの15アイテムから始めてみてください。
水と食料(3日分)
何といっても最優先すべきは水と食料です。特に水は生命維持に直結します。
1. 飲料水:1人1日3リットルを目安に。我が家では2リットルのペットボトルを家族分×3日分、キッチンの下と寝室のクローゼットに分散して保管しています。賞味期限が近づいたら普段使いして、新しいものと入れ替えるようにしています。
2. 非常食:調理不要で長期保存可能なものを。アルファ米、レトルト食品、缶詰、乾パンなどがおすすめです。子どもが好きな味のものを入れておくと、ストレスの多い避難生活でも食べてくれますよ。うちの子はカレー味のアルファ米が大好きで、キャンプの時にも喜んで食べてくれます。
安全確保と情報収集のためのアイテム
災害時には情報が命です。また、二次災害から身を守るための道具も重要です。
3. 懐中電灯・ランタン:停電時の行動に必須。手回し充電式や電池式など、複数の種類を用意しておくと安心です。寝室、リビング、玄関など、家の複数箇所に配置しておくのがポイントです。
4. 携帯ラジオ:災害時はスマホが使えない場合も。手回し充電式のラジオがあると情報収集に役立ちます。最近のものはスマホの充電もできる多機能タイプが多いですね。
5. モバイルバッテリー:スマホの充電切れは現代の災害時には致命的。大容量のものを選びましょう。我が家では10,000mAh以上のものを常に満充電で保管しています。
6. ヘルメット・防災ずきん:頭部を保護するためのアイテム。特に就寝中の地震に備えて、枕元に置いておくと良いでしょう。子ども用のかわいいデザインのものもあるので、防災訓練を兼ねて時々被せてみると、いざという時に抵抗なく使えますよ。
衛生管理と応急処置のためのアイテム
災害時は衛生環境が悪化します。健康を維持するための準備も忘れずに。
7. 救急セット:絆創膏、消毒液、包帯、常備薬などを含む基本的な救急セット。家族の持病がある場合は、処方薬の予備も忘れずに。私は花粉症の薬を切らしたことがあって大変な思いをしたので、今は予備を防災バッグに入れています。
8. ウェットティッシュ・除菌シート:水が制限される中での手指消毒や体の清拭に。赤ちゃんがいる家庭では多めに準備しておきましょう。コロナ禍で使い慣れた方も多いと思いますが、災害時にはさらに重宝します。
9. 簡易トイレ:断水時のトイレ問題は深刻です。凝固剤付きの簡易トイレを人数分用意しておきましょう。我が家では1人5回分×家族の人数×3日分を目安に準備しています。
その他の必需品
10. 現金:災害時は電子決済が使えないことも。小銭を含めた現金を用意しておきましょう。我が家では3万円程度を千円札と小銭に分けて防災バッグに入れています。
11. 防寒シート・アルミブランケット:体温保持に役立ちます。コンパクトで軽量なので、複数枚あると便利です。冬場の災害や避難所での就寝時に本当に助かります。
12. 軍手・ワークグローブ:ガラスの破片など危険物を扱う際の手の保護に。子ども用サイズも忘れずに。
13. マスク:粉塵対策や感染症予防に。使い捨てタイプを多めに用意しておきましょう。
14. 家族の写真・連絡先リスト:はぐれた時の確認用に。スマホが使えない状況を想定して、紙に印刷しておくことが大切です。特に子どもの写真は最新のものを定期的に更新しておくと安心です。
15. 筆記用具とメモ帳:情報記録用に。ボールペンは寒さに弱いので、鉛筆も用意しておくと良いでしょう。
家族構成別・追加で準備したい防災グッズ
基本の15アイテムに加えて、家族構成に応じて追加すべきものをご紹介します。
乳幼児がいる家庭
小さなお子さんがいるご家庭では、日常的なケアアイテムが災害時にも必要になります。
– 粉ミルク・液体ミルク:最近は常温保存可能な液体ミルクも販売されているので、併せて準備しておくと便利です。
– 哺乳瓶・乳首:洗浄が難しい状況を想定して、使い捨てタイプも検討してみてください。
– おむつ・おしりふき:最低3日分。サイズアウトしないよう定期的にチェックを。
– 子どもの好きなおもちゃ・絵本:非日常の環境でも安心できるよう、お気に入りのものを。
うちの子が小さかった頃は、おむつのサイズがすぐに変わるので、少し大きめのサイズを防災用に入れていました。大きすぎても応急的には使えますからね。それと、子どもの好きなキャラクターのお菓子を少し入れておくと、不安な時の気分転換になりますよ。
高齢者がいる家庭
高齢の方がいらっしゃるご家庭では、健康管理に関するアイテムが重要です。
– 常備薬・お薬手帳のコピー:最低1週間分の薬と、薬の情報がわかるものを。
– 老眼鏡・補聴器の予備:予備の電池も忘れずに。
– 入れ歯洗浄剤:衛生状態を保つために。
– 持病に関する医療情報メモ:かかりつけ医の連絡先や病名、注意点などを記載したもの。
義母が高血圧の薬を飲んでいるのですが、一度旅行先で薬を忘れて大変だったことがあります。それ以来、お薬手帳のコピーと3日分の予備薬を防災バッグに入れるようにしています。
ペットがいる家庭
大切な家族の一員であるペットの防災対策も忘れずに。
– ペットフード:3日分以上。できれば普段食べているものと同じものを。
– 水:ペット用の飲料水も必要です。
– リード・キャリーケース:避難時の移動用に。
– トイレ用品:猫用トイレ砂や犬用シートなど。
– ペットの写真と情報カード:はぐれた時のために。
我が家の猫は缶詰しか食べないので、缶切りも一緒に防災バッグに入れています。また、普段使っているキャリーバッグは取り出しやすい場所に置いておくようにしていますよ。
防災グッズの収納と管理のコツ
せっかく揃えた防災グッズも、適切に管理しないと意味がありません。効果的な収納と管理のポイントをご紹介します。
分散保管が鉄則
全ての防災グッズを一箇所にまとめておくのはリスクがあります。家の複数箇所に分けて保管しましょう。
私の場合、リュックタイプの防災バッグを玄関に、水や食料の一部をキッチンに、もう一セットを寝室のクローゼットに保管しています。これは、地震で家具が倒れて一箇所にアクセスできなくなるリスクを考慮してのことです。
また、車の中にも最小限の防災グッズ(水、非常食、ブランケット、モバイルバッテリーなど)を入れています。外出先で被災した場合に役立ちますよ。
定期的なチェックと更新を忘れずに
防災グッズは「用意して終わり」ではありません。定期的なメンテナンスが必要です。
– 食料・飲料水:賞味期限をチェックし、期限が近いものは日常で消費して新しいものと交換。
– 電池・モバイルバッテリー:3〜6ヶ月に一度は充電状態を確認。
– 衣類・タオル:季節や家族の成長に合わせて入れ替え。
– 医薬品:使用期限をチェックし、定期的に更新。
我が家では防災の日(9月1日)と春分の日の年2回、防災グッズの総点検をする習慣にしています。子どもと一緒に中身を確認することで、防災意識も高まりますよ。
リュックタイプの防災バッグがおすすめ
防災グッズをまとめるなら、両手が使えるリュックタイプがおすすめです。選ぶ際のポイントは以下の通り。
– 容量:20〜30リットル程度が扱いやすい
– 重量:満タンで10kg以内に収まるよう調整
– ポケット:小物を整理しやすい多ポケット設計
– 反射材:夜間の視認性を高めるもの
– 防水性:雨天時の避難も想定して
最初は何を入れるべきか迷って、とにかく詰め込んでいたら、持ち上げるのも一苦労…なんてことがありました。実際に背負ってみて、「これなら持って避難できる」という重さに調整することが大切です。
防災グッズの予算別おすすめリスト
予算に応じた防災グッズの揃え方をご紹介します。無理なく段階的に準備していきましょう。
予算5,000円でできる最低限の準備
まずは本当に必要最小限のものから始めましょう。
– 飲料水(2Lペットボトル×6本):約1,000円
– アルファ米(5食分):約1,000円
– 携帯ラジオ(乾電池式):約1,500円
– LEDライト:約800円
– 簡易トイレ(5回分):約700円
これだけでも、いざという時の最初の一歩としては十分です。我が家も最初はこのくらいからスタートしました。特に水と食料、そして情報収集手段は最優先で確保しておきたいものです。
予算15,000円で揃える基本セット
少し予算に余裕があれば、以下のアイテムを追加しましょう。
– 上記の最低限セット:約5,000円
– モバイルバッテリー:約3,000円
– 防災ずきん:約2,000円
– 救急セット:約1,500円
– 防寒シート(2枚):約800円
– ウェットティッシュ・マスク:約1,000円
– 軍手・簡易雨具:約700円
– 笛(ホイッスル):約500円
– 予備の乾電池:約500円
このセットがあれば、72時間の初期対応はかなりカバーできます。特に情報収集と連絡手段の確保、そして最低限の衛生管理ができるようになります。
予算30,000円で家族全員分の本格的な準備
さらに予算に余裕があれば、家族全員分の本格的な防災セットを準備しましょう。
– 上記の基本セット:約15,000円
– 家族分の追加飲料水と非常食:約5,000円
– 家族それぞれの着替え一式:約3,000円
– 簡易トイレの追加(家族3日分):約2,000円
– 多機能ラジオ(ソーラー充電・手回し充電機能付き):約3,000円
– 寝袋または防災マット:約2,000円
– 家族構成に応じた追加アイテム:約5,000円
我が家では、最初は基本セットから始めて、少しずつ追加していきました。一度に全部揃えようとすると大変ですが、毎月の予算に少しずつ組み込んでいけば、半年〜1年で十分な備えができますよ。
防災グッズを実際に使ってみることの大切さ
いざという時に慌てないためには、日頃から防災グッズを実際に使ってみることが大切です。
家族で防災訓練を実施してみよう
年に1〜2回、家族で防災訓練を行ってみましょう。例えば以下のようなことを試してみてください。
– 防災バッグを持って実際に避難場所まで歩いてみる
– 非常食を実際に食べてみる
– 停電を想定して、電気を使わない夜を過ごしてみる
– 簡易トイレを組み立ててみる
うちでは去年、「防災キャンプ」と称して、リビングに寝袋を広げて非常食だけで一晩過ごしてみました。子どもはゲーム感覚で楽しんでいましたが、大人は「これが数日続くと相当きついな」と実感。でも、事前に体験しておくことで、いざという時の心構えができました。
日常生活に取り入れられる防災習慣
特別なことをしなくても、日常生活の中で防災意識を高める習慣を取り入れることができます。
– お風呂の水を一晩ためておく習慣をつける
– 帰宅時に水や非常食を一つずつ買い足す
– スマホの充電を80%以上に保つよう心がける
– 季節の変わり目に防災バッグの中身を見直す
我が家では「買い物ついでに防災一品運動」と呼んで、スーパーに行くたびに防災に使えるものを一品買い足す習慣をつけています。負担にならない程度に続けることで、いつの間にか十分な備えができていきますよ。
まとめ:今日からできる防災準備のステップ
防災グッズの準備は一日にしてならず。今日からできる具体的なステップをご紹介します。
まずは3日分の水と食料から
何よりもまず、3日分の水と食料を確保しましょう。これだけでも、いざという時の安心感が全く違います。
水は1人1日3リットル×3日分、食料は調理不要で長期保存可能なものを選びましょう。次のスーパーでの買い物時に、少し多めに購入するところから始めてみてはいかがでしょうか。
次に情報収集と安全確保のためのアイテム
水と食料の次は、懐中電灯、ラジオ、モバイルバッテリーなど、情報収集と安全確保のためのアイテムを揃えましょう。
これらは日常でも使える機会が多いので、普段使いしながら非常時に備えるという観点で選ぶと良いですね。
家族で防災について話し合う時間を持とう
物の準備と同じくらい大切なのが、家族での話し合いです。避難場所や連絡方法、それぞれの役割などを事前に決めておきましょう。
子どもも含めた家族会議で、「もしも」の時のルールを決めておくことで、パニックになりにくくなります。我が家では夕食時に時々「もしも今地震が起きたら」というテーマで話し合いをしています。
定期的な見直しと更新を習慣に
最後に、準備した防災グッズは定期的に見直し、必要に応じて更新することを習慣にしましょう。
カレンダーに「防災グッズチェックの日」を設定しておくと忘れにくいですよ。我が家では防災の日と春分の日を点検日にしています。
防災準備は完璧を目指すものではなく、できることから少しずつ進めていくものです。この記事が皆さんの防災への第一歩になれば嬉しいです。家族の安全を守るために、今日からできることから始めてみませんか?