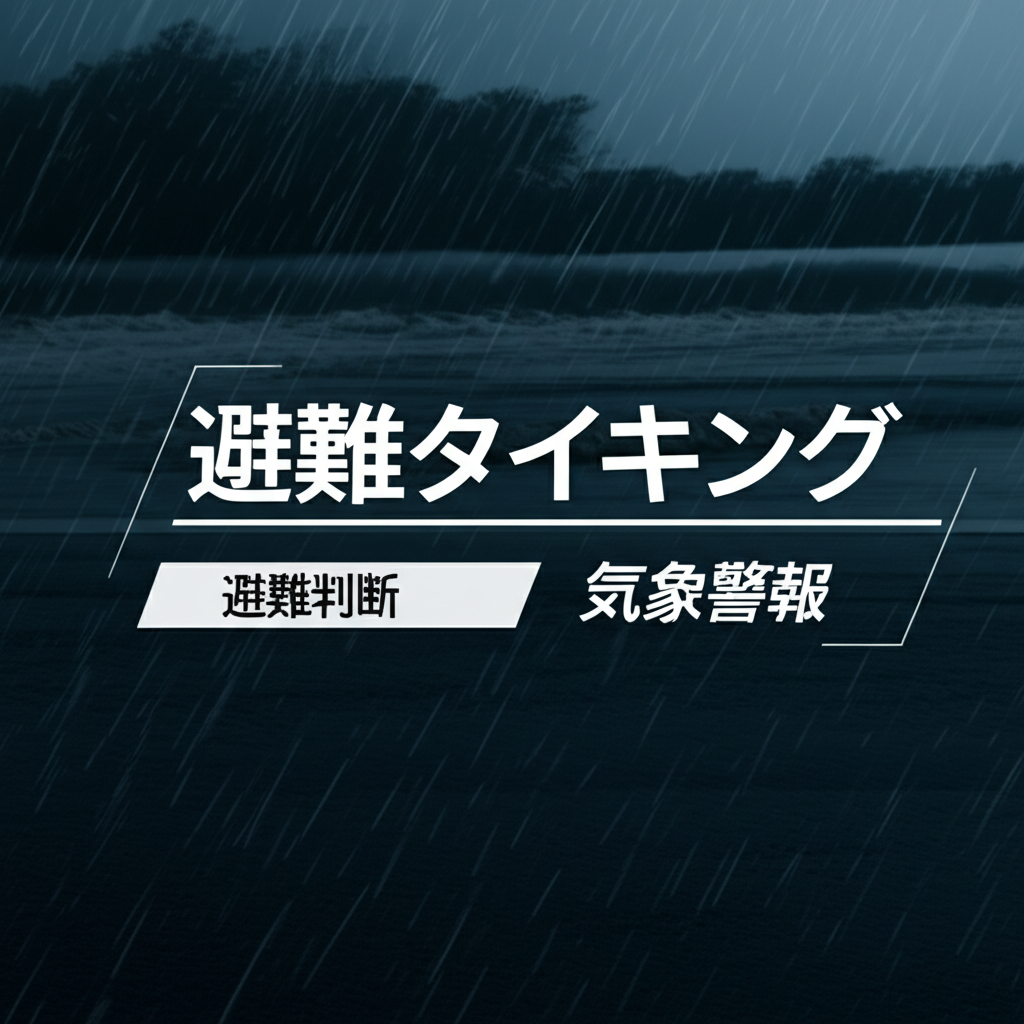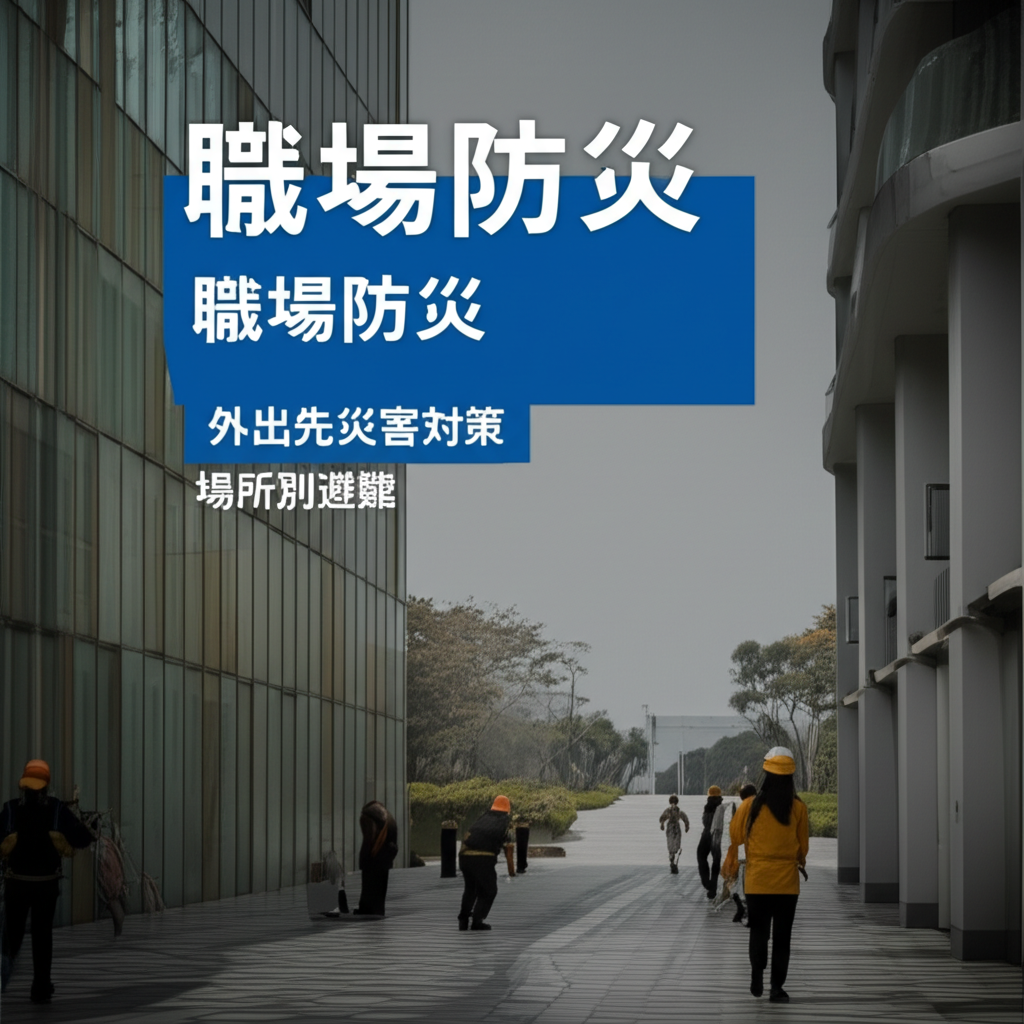はじめに:なぜ今、ローリングストックが注目されるのか?
災害大国日本で暮らす私たちにとって、食料備蓄は家族を守るための必須の備えです。しかし、従来の備蓄方法では「気づいたら賞味期限切れ」「いざという時に食べられない」といった問題が数多く報告されています。
そんな中、注目を集めているのが「ローリングストック」という画期的な備蓄方法です。普段から少し多めに食材、加工品を買っておき、使ったら使った分だけ新しく買い足していくことで、常に一定量の食料を家に備蓄しておく方法をローリングストックと言います。
この方法は、災害大国である日本で生まれた考え方で、「ローリングストック法」や、日本語で「循環備蓄」と表記されることもあります。そして現在では、農林水産省「災害時に備えた食品ストックガイド」として農林水産省がその効果や実践方法について詳しく解説されているように、国も推奨している方法の一つです。
災害時の備蓄というと、多くの方が乾パンや缶詰といった長期保存の非常食をイメージされるかもしれません。しかし、規模の大きな災害では、救援物資が到着して行き渡るまで数日から数週間、ライフラインの復旧に1か月以上かかることもあります。その間を乾パンや缶詰などの非常食だけで賄うには、備蓄量も足りず、栄養バランスの点でも十分とは言えません。
そこで今回は、主婦の皆さんが7日間で完全にマスターできるローリングストックの実践方法を、失敗しないコツとともに詳しくお伝えします。
ローリングストックとは?基本概念を徹底理解
ローリングストックの定義と仕組み
ローリングストックとは日常的に食べる食品を多めに買って取り置いておき、使うたびに使った分を新しく補充する(買い足す)備蓄方法です。この方法の最大の特徴は、日常生活で消費しながら備蓄することです。
具体的な仕組みを見てみましょう。1)最初に、非常食を通常備蓄が必要な倍の量購入します。2)月に1回1食非常食を食べます。3)購入した非常食が半分くらいになったら、減ったぶんを買い足します。この循環を繰り返すことで、常に新鮮な食料が手元に残り続けるのです。
従来の備蓄方法との違い
従来の備蓄方法は、「災害用の備蓄は期限の長いものを買って、何かあるまで触らずに置いておく」という備蓄方法でした。しかし、この方法には以下のような問題がありました:
1. 賞味期限切れのリスク:備蓄品の管理を忘れがち
2. 食べ慣れない味:いざという時に食べにくい
3. 栄養バランスの偏り:非常食だけでは栄養が偏る
4. 経済的負担:使わずに廃棄することが多い
一方、ローリングストックでは、普段の生活で使う食料(もちろん非常食でもOK)や日用品を、もしもの場合備えて多めに買っておき、ストックされたもののうち古いものから順に日々の生活の中で使い、その使った分を買い足すことで、常に新しいものが保存(備蓄)されていくのです。
ローリングストックが解決する3つの問題
1. 賞味期限切れの防止
日々の生活の中で古いものから消費し、新しいものを買い足していくので、備蓄品の「期限切れ」を防ぐことができます!
2. 食べ慣れた食事の提供
災害が発生した場合でも、普段から食べ慣れたもの、使い慣れたものを食べたり使用したりできます!
3. 災害関連死の防止
ローリングストックは、災害発生時に快適に過ごせるというだけでなく、災害関連死の防止のためにも重要となる考え方です。災害関連死とは、地震発生時に起きた家屋の倒壊や津波などの直接的な被害で死亡したのではなく、長引く避難生活における負担が原因で死亡に至ってしまうケースです。
7日で完全マスター!ローリングストック実践スケジュール
【1日目】現状把握と目標設定
まず初日は、ご自宅の食料備蓄の現状把握から始めましょう。
作業内容:
1. キッチンや食品庫にある食料品をすべてチェック
2. 賞味期限をリストアップ
3. 家族の人数と必要な備蓄量を計算
必要な備蓄量の目安:
一般的には、災害支援物資は災害が起きてから3日ほどで到着することが多いです。しかし、大地震などの大規模な災害の場合には、1週間以上かかるケースも少なくありません。
米を中心に、上記の食料品を組み合わせ、3日分であれば9食、1週間分であれば21食を確保することが目安となります。
【2日目】備蓄品カテゴリーの決定
2日目は、ローリングストックに適した食品カテゴリーを決めましょう。
主食系:
– 主食はエネルギー源となるため、ストックしておきたい食品の1つです。なかでもご飯は、昔から日本人に好まれている主食であり、食べ飽きることもないでしょう。
– パックごはん、パスタ、即席麺類
おかず系:
– レトルトパウチ食品とは、完成された状態の料理が、空気や光を通さず熱にも強い特殊な袋に詰められ、加圧加熱殺菌された食品です。カレーや肉じゃがなど種類も豊富なうえに、温める又はそのままの状態で食べられます。
– 缶詰は密封後、加圧加熱殺菌を施しているため、保存料を使用せずに3年ほどもちます(※製品による)。
【3日目】買い物リストの作成と初回購入
3日目は具体的な買い物リストを作成し、初回購入を行います。
農林水産省推奨の1週間分備蓄例(大人2人):
・水…2L×6本×4箱(※飲用と調理で、1人1日約3L使用する)・カセットコンロ…カセットボンベ12本(※1人あたり1週間で6本程度使う)・米…2kg×2袋(※1人1食75g程度)・カップ麺類…6個・乾麺(うどん、そば、そうめん、パスタなど)…そうめん300g×2袋、パスタ600g×2袋・パックごはん…6個など、詳細なリストが参考になります。
購入時のポイント:
1. 普段食べているブランドを選ぶ
2. 賞味期限の長いものから選ぶ
3. 家族の好みを考慮する
【4日目】収納と管理システムの構築
4日目は効率的な収納システムを構築します。
収納の基本ルール:
備蓄する食料が古くなってしまわないよう、消費の際には、必ず一番古いものから使うようにしましょう。新しいものを右側に配置し、左側の古いものから使っていく、というようにそれぞれ合った備蓄方法で上手に循環させることが大切です。
おすすめの収納方法:
1. FIFO法(First In, First Out)の採用:古いものから使う
2. 見える化:賞味期限を前面に表示
3. 分散保管:災害発生時にパントリーに入れない場合も考え、備蓄品は複数の場所に分散させることも大事。
【5日目】消費ルールの設定
5日目は継続可能な消費ルールを設定します。
消費ルールの例:
1. 定期消費日の設定:定期的に消費する日を決めておくと、スムーズに循環させやすくなります。
2. 半分ルール:購入した非常食が半分くらいになったら、減ったぶんを買い足します。
3. 補充タイミング:消費した量を必ず買い足すようにしましょう。ちょっと補充を怠ったタイミングで災害が来る可能性もありますから、消費した分の補充は必ず直後に行いましょう。
【6日目】実際の消費と補充の実践
6日目は実際にローリングストックの食品を使って食事を作り、補充作業を行います。
実践のポイント:
1. 家族の感想をヒアリング
2. 調理方法の確認
3. 必要に応じて商品の変更
【7日目】システムの最終調整と継続計画
最終日はシステム全体を見直し、継続するための計画を立てます。
継続のためのチェックポイント:
1. 管理が負担になっていないか
2. 家族が協力できる体制になっているか
3. 経済的に継続可能か
ローリングストック成功の5つの秘訣
秘訣1:家族の好みを最優先に考える
ローリングストック成功の最大の秘訣は、家族が「美味しい」と感じる食品を中心に備蓄することです。「食べながら備える」という形になるため、非常食と比較すると賞味期限が短いレトルト食品も備蓄品に入れられます。種類が限られた非常食よりも好みのレトルト食品を非常時に食べられることは、健康維持だけではなく精神的な支えにもなるでしょう。
秘訣2:管理方法をシンプルにする
最初のうちに、備蓄食品の名前と賞味期限をリスト化し、台所やリビングなど目のつくところに貼っておくと確認忘れを防げます。確認する際に数も記入しておくと、在庫もわかり補充もスムーズに行えます。
秘訣3:段階的に始める
ローリングストック用の備蓄食品は、食べなれたものであるため、普段の買い物と一緒にできます。「普段1つ購入するものを、3つに増やそう」や「いつもより、少し多めに買っておこう」くらいの気軽さで行えるのです。
秘訣4:日用品も含めて考える
ローリングストックは、食料だけでなく、日常使いできる生活用品にも応用することできます。日常的に使用する保存食、飲料水、ウエットタオル、カセットボンベ、乾電池、使い捨てカイロなどは、常に一定量、家庭に置いておくようにすると、突然の災害にも対応しやすいです。
秘訣5:定期的な見直しを習慣化する
「防災点検の日」は3月1日・6月1日・9月1日・12月1日となっており、これは1923年9月1日に発生した関東大震災をきっかけに制定されました。定期的に防災グッズをチェックする習慣を付けることで、防災意識の向上にも繋がり自身や家族の安全に繋がります。
実践者の成功事例と失敗談
成功事例:Aさん一家(4人家族)の場合
Aさんは3ヶ月前からローリングストックを始めました。最初は「面倒そう」と思っていましたが、実際に始めてみると意外に簡単で、災害はいつ起きてもおかしくないですが、それに怯えて生活するよりも、備えているから安心という思いで暮らしていきたいですよね。という心境になったそうです。
Aさんの工夫:
– 月1回の「ローリングストック料理デー」を設定
– 子どもたちも巻き込んで賞味期限チェックをゲーム化
– 買い物の際は必ずスマホのメモ機能で在庫確認
失敗談から学ぶ注意点
よくある失敗パターン:
1. 過度な備蓄:最初に張り切りすぎて大量購入→消費が追いつかない
2. 管理の複雑化:細かすぎるルールを作って継続困難
3. 家族の協力不足:一人だけで管理して負担が集中
ローリングストックは常時消費と買い足しを繰り返す方法です。消費したら近日中の買い物で購入しなければならず、消費量の管理や買い足しそのものが大変だという人もいました。
このような場合には、ローリングストックが難しい場合はほかの備蓄方法を考えましょう。たとえば長期的な保存食をそろえ、場所を決めて保管しておく方法があります。
おすすめ商品カテゴリー別完全ガイド
主食系のおすすめ
パックごはん
テーブルマーク株式会社のパックごはん「国産こしひかり」は、賞味期限が製造から12カ月と長期保存が可能なため、備蓄食品としても最適です。カセットコンロがあれば、湯煎したり鍋で煮たり、フライパンで温めたりすると食べられます。
レトルト食品
レトルト食品には丼、カレー、ハヤシライス、パスタソースなどがあります。タンパク質を多く含み、食事のメインになる食材です。調理不要で温めずにそのまま食べられるレトルト商品もあり、ストックしておくと便利です。
缶詰系のおすすめ
魚の缶詰
さばのトマト煮は、さばとジャガイモ、タマネギ。オリーブをトマトベースで仕上げた洋風の缶詰です。そして「さばのトマト煮」は、「災害食大賞2021」の缶詰部門で、60品の中から最優秀賞に選ばれました。
調理器具・熱源
カセットコンロとガスボンベ
1週間を想定した上で重要となる防災グッズの中でも必需品としてセットしておきたい防災グッズが「カセットコンロ」です。過去の被災者の多くは、災害後の避難生活の際に”温かい物”が食べたかったと語っています。
よくある疑問とその解決方法
Q1: どのくらいの量を備蓄すれば良いの?
A1: これまで、備蓄は3日分あれば十分と言われていましたが、非常に広い地域に甚大な被害が及ぶ可能性のある南海トラフ巨大地震では、「1週間以上」の備蓄が望ましいとの指摘もあります。
家族の人数×1週間分(21食)を基本として、段階的に増やしていくことをおすすめします。
Q2: 賞味期限の管理が大変そう…
A2: 管理方法をシンプルにすることが重要です。スマートフォンのアプリを活用したり、見える場所にリストを貼ったりして、家族全員で管理する体制を作りましょう。
Q3: 経済的な負担が心配
A3: ローリングストックは決して経済的負担を増やすものではありません。普段の食費の一部を前倒しで購入するイメージです。むしろ、賞味期限切れによる食品ロスを防げるため、経済的にもメリットがあります。
Q4: 特別な配慮が必要な家族がいる場合は?
A4: 赤ちゃんや子ども、お年寄り、アレルギーや慢性疾患・身体障害などのある家族がいる場合は、備蓄すべきものが異なります。家族全員の暮らしに関わるものを見直し、必要なものを備蓄しておくようにしましょう。
収納と管理の実践テクニック
効率的な収納方法
パントリー活用法
「備蓄品はパントリーなど食料品や生活用品をストックする場所があれば、まずはそこで管理を。消費期限が分かるよう日付の付箋などを貼り、古い順に普段の生活で消費するローリングストックで備蓄しておきましょう。
分散保管の重要性
ただ、災害発生時にパントリーに入れない場合も考え、備蓄品は複数の場所に分散させることも大事。庭の倉庫や車庫など、直射日光が当たらず、温度変化も少ない場所に万一の備蓄品を置けるとベターです」
日用品のローリングストック
食料品だけでなく、日用品もローリングストックで管理することで、より包括的な備えができます。
食品だけではなく、日用品も定期的に消費しながら買い足して管理すると効率的です。食品と同じように、普段使い慣れている物をストックしす。ライフラインの確保はもちろん、お店で品薄になりやすいものを選ぶのが大事です。
日用品のローリングストック対象:
– トイレットペーパー
– ウェットティッシュ
– 生理用品
– 乾電池
– 使い捨てカイロ
– カセットボンベ
まとめ:今日から始める防災の新習慣
ローリングストックは、単なる防災対策を超えて、日常生活をより豊かで安心なものにする生活習慣です。非常食というと「気が付いたら消費期限が大幅に過ぎていて全て廃棄した」といった失敗が起こりがちです。ローリングストック法は日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法。この方法なら普段から食べているものが災害時の食卓に並び、安心して食事を採ることができるはずです。
今すぐできる3つのアクション
1. 現状把握:今日から1週間、家族が何を食べているかメモを取る
2. リスト作成:よく食べるもの、日持ちするものをリストアップ
3. 少量スタート:いつもの買い物で「1つ多く」買ってみる
長期的な目標設定
– 1ヶ月目:基本的なローリングストックシステムの構築
– 3ヶ月目:システムの最適化と家族全員での運用
– 6ヶ月目:1週間分の完全な備蓄達成
– 1年目:日用品も含めた包括的なローリングストック完成
災害はいつ起こるかわかりません。備えはいつ始めても、早すぎるということはありません。ぜひ!このページを読んだ今日から、取組みを始めましょう!
ローリングストックは、家族の安全を守りながら、日々の生活も豊かにする素晴らしい方法です。完璧を目指さず、できることから少しずつ始めることで、必ず継続できる防災習慣が身につくはずです。
あなたの大切な家族を守るため、そして毎日を安心して過ごすために、今日からローリングストック生活を始めてみませんか?