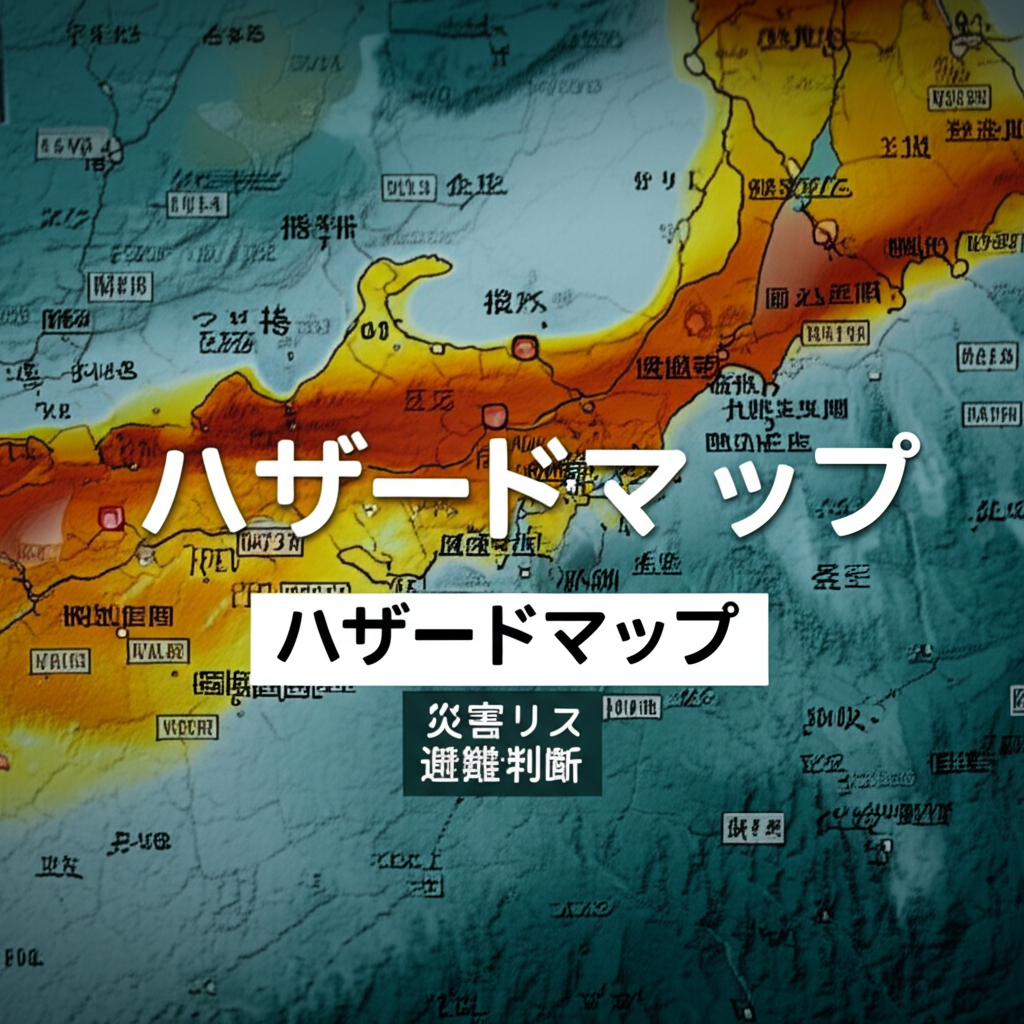子どもがいるご家庭の皆さん、災害への備えは万全でしょうか?大人だけの避難とは全く異なる準備が必要になる赤ちゃんや乳幼児との災害対策。「何から始めればいいの?」「どんなものが必要?」そんな疑問をお持ちの方も多いはずです。
2011年3月11日に発生した東日本大震災は、乳幼児のいる家庭での防災や危機管理を再度考えるきっかけになりました。当時は、直接被災されなかった地域のママからも、もしもの時の不安を訴える相談が相次ぎました。
この記事では、赤ちゃんや乳幼児がいるご家庭向けの防災対策を、具体的なアイテムリストから避難計画の立て方まで詳しく解説します。いざという時に慌てることがないよう、今のうちからしっかりと準備を整えておきましょう。
乳幼児がいる家庭が直面する災害時の課題
一般的な避難所では対応できない特別なニーズ
実は、赤ちゃん含む要配慮者のために物資を備蓄している自治体は55%という現実があります。つまり約半数の自治体では、赤ちゃん専用の物資が十分に備蓄されていないということなのです。
災害時、乳幼児がいる家庭が直面する主な課題は以下の通りです:
授乳・調乳の問題
スーパーなどでは災害発生後1週間以上、粉ミルクは品薄・欠品状態になり、配給には時間がかかる場合も。水不足で、粉ミルク用のお湯を沸かしたり、哺乳びんを洗って消毒することができない状況が発生します。
衛生面の課題
清潔を保つためのウエットティシュなどは多めに準備。災害時はお風呂に入れない、手を洗う水もないなど不衛生になりがちになります。
避難所での生活困難
避難所は混雑で足も伸ばせないほどギュウギュウになることも。避難所の集団生活では、あかちゃんがぐずるたびに気をつかい、外に出るなどの対応も必要になります。
在宅避難という選択肢
子育て家庭は在宅避難が推奨されるが、避難する場合は警戒レベル3で避難開始するとされています。在宅避難とは、災害時に自宅で避難生活を送ることです。これは、自宅が安全である場合や、避難所に行くよりも自宅に留まる方が安全で快適と判断される状況で可能となります。
在宅避難を選択する場合の条件:
– 建物の安全が確保できている
– 避難生活に必要な備蓄品が自宅に確保されている
– 家具が固定され部屋が安全である
– ライフラインの復旧見込みがある
月齢別!赤ちゃん防災グッズの必須アイテムリスト
新生児〜5ヶ月の赤ちゃんに必要なグッズ
この時期は授乳が中心で、ミルクの確保が最重要課題となります。
授乳関連アイテム(優先度:最高)
1. 液体ミルク(6回分以上)
2. 専用乳首・アタッチメント
3. 使い捨て哺乳瓶(3本以上)
4. 粉ミルク(スティック・キューブタイプ推奨)
5. ミルク用軟水(2L以上)
6. 発熱剤・加熱袋
普段は母乳のママも、災害時の緊張や疲れから、母乳が出づらくなるケースもあります。調乳不要で常温のまま哺乳瓶にうつすだけの液体ミルクなら、お湯や湯冷ましなどが手に入らなくても、すぐに赤ちゃんに授乳できます。
おむつ・衛生用品
7. 紙おむつ(1週間分=約50枚)
8. おしりふき(大容量パック2個)
9. ウエットティッシュ(除菌タイプ)
10. ガーゼハンカチ(10枚以上)
11. 母乳パッド
12. 哺乳瓶用スポンジ・洗剤
保温・快適グッズ
13. おくるみ・バスタオル(3枚)
14. 肌着・着替え(5日分)
15. 使い捨てカイロ(ミルクの温め用)
16. 体温計
17. お気に入りのおもちゃ
6ヶ月〜1歳6ヶ月の赤ちゃん向けアイテム
離乳食が始まるこの時期は、食事の準備がより複雑になります。
食事関連
18. レトルト離乳食(1週間分)
19. 赤ちゃん用せんべい・ボーロ
20. 赤ちゃん用スプーン・フォーク(使い捨て)
21. ベビー用おせち・コップ
22. 離乳食用エプロン(使い捨て)
ベビーフードは大人の配給に比べ配給量に限りがあることもあるため、十分な量の備蓄が必要です。
移動・安全グッズ
23. 抱っこ紐・スリング
24. ベビーカー用レインカバー
25. 赤ちゃん用ヘルメット
26. 迷子札・連絡先カード
1歳7ヶ月〜3歳の幼児向けアイテム
自我が芽生え、好みがはっきりしてくる時期の対策です。
食事・おやつ
27. 子ども用レトルト食品
28. 普段食べ慣れているお菓子
29. 好きなキャラクターのふりかけ
30. ストロー付きパック飲料
食事の量も増え、持ち出し食品の重さが増すので、大人と子ども両方が食べられるものを。アレルギーなどがある場合、配給には時間がかかる場合が多いため、アレルギー対応食品の備蓄も重要です。
遊び・安心グッズ
31. お気に入りのぬいぐるみ
32. 絵本(小さめサイズ)
33. 塗り絵・クレヨン
34. シールブック
35. 小さなおもちゃ
実用アイテム
36. トレーニングパンツ・普通パンツ
37. 子ども用マスク・手袋
防災リュックの作り方と収納のコツ
重量制限を意識したパッキング
女性が持てる量は10キロ程度、避難時にはあかちゃんを抱っこするので、リュックは中身を厳選し、出来るだけ軽く。おむつやタオル類などは圧縮するのもおすすめ。
パッキングのポイント
– 圧縮袋を活用して衣類をコンパクトに
– 重いものは背中側に配置
– よく使うものは取り出しやすい場所に
– 防水対策としてジップロックを活用
ローリングストック法の活用
日常生活で消費する粉ミルク・飲料・ベビーフードや紙おむつ・おしりふきなどを、少し多めに家に備蓄しておいて、古いほうから順番に使っていくことで数日分の食品や消耗品が災害に備えて確保できます。
この方法なら、常に新しい状態の備蓄品を保てるうえ、賞味期限切れの心配もありません。
避難計画の立て方と家族会議のポイント
子どもと一緒に避難ルートを確認
子どもと一緒に避難する際、みなさんが決めている避難経路は子どもにとって安全ですか。まずは、避難場所や、そこまでの道のりなどを、子どもと一緒に確認して、実際に歩いてみましょう。
確認すべきポイント
– ベビーカーで通れる道幅があるか
– 段差やスロープの状況
– 途中に危険箇所はないか
– 雨天時でも安全に移動できるか
特に、赤ちゃんや小さいお子さんの場合は、ベビーカー抱っこ紐で避難ができるルートを確保しておくことが重要です。
災害時の役割分担を決める
夫婦での役割分担例
– パパ:防災リュックと貴重品の管理
– ママ:赤ちゃんの世話と授乳用品の準備
– 避難時の抱っこ・ベビーカー担当の交代制
家族の連絡方法
– 災害用伝言ダイヤル(171)の使い方を練習
– 集合場所を複数決めておく
– 近所の方との協力体制を構築
災害時のミルク・離乳食対策の実践方法
液体ミルクを活用した授乳方法
災害時に備えておくべき食料は、少なくとも3日分と言われています。赤ちゃんの乳児用ミルクも3日分はストックがあると良いでしょう。
液体ミルクの利点
– お湯不要で常温のまま飲める
– 消毒の手間が不要
– 計量の必要がない
– 長期保存が可能
注意点
調乳した粉ミルク、開封した液体ミルクは2時間以内に飲ませます。2時間以上経ったものを、大きな子どもや大人が飲むのはかまいません。
衛生管理の徹底方法
災害時は水が不足するため、衛生管理が特に重要になります。
消毒・殺菌のポイント
粉ミルクは70°C以上(沸騰して熱いうちに溶かす)で殺菌できます。開封していない液体ミルクは殺菌の必要はありません。
– 手指消毒用アルコールを必携
– 使い捨てウエットティッシュを多めに準備
– 哺乳瓶の代わりにコップ飲みも練習しておく
避難所生活での子育てのコツ
周囲への配慮と子どものストレス軽減
避難所生活が長引けば、赤ちゃんもストレスになります。もし可能ならば、お気に入りのおもちゃを少し持っていくなどして、赤ちゃんのストレスからくるグズりを軽減できるような対策をしてあげましょう。
ストレス軽減のアイデア
– 普段と同じ生活リズムを保つ
– 静かな遊びのレパートリーを増やしておく
– 他の子どもたちとの交流を促す
– 親自身のメンタルケアも忘れずに
授乳・おむつ替えスペースの確保
多くの避難所では、授乳やおむつ替え専用のスペースが限られています。
対策方法
– 授乳ケープや大判のタオルを準備
– 折りたたみ式おむつ替えマットを活用
– 場所の確保が困難な場合は車内を活用
特別な配慮が必要な子どもへの対応
食物アレルギーがある子どもの場合
「こんな時にわがままを言って…」「非常時なのに甘えている…」そんな風に言われた経験がある方もいるかもしれません。ですが、アレルギーは決して甘えでもわがままでもありません。子どもを守るためにも、堂々と対策をとってください!
準備すべきもの
– アレルギー対応の非常食を十分に備蓄
– エピペンなどの緊急薬剤
– アレルギー情報を記載したカード
– 医師の診断書のコピー
発達障がいがある子どもの場合
発達障がいをもつ子どもは、その状況を受け入れることが大人よりもずっと苦手です。ですが、ポイントを理解し、伝え方や接し方をほんの少し変えるだけでストレスを減らすことができます。
配慮のポイント
– 視覚的に分かりやすい説明材料を準備
– 音に敏感な場合は耳栓やノイズキャンセリング機能付きヘッドフォン
– 慣れ親しんだグッズを多めに持参
– 避難所での生活ルールを事前に説明
定期的な見直しと訓練の重要性
3ヶ月ごとの備蓄品チェック
子どもの成長は早く、必要なものも急速に変化します。
チェック項目
– 衣類のサイズ確認
– 食品の賞味期限
– ミルクの缶の賞味期限
– おむつのサイズ変更
– 薬の使用期限
定期的に期限を確認します。もし賞味期限内に出番がなさそうであれば、普段のミルクや食事に使い、また新しい品に入れ替えましょう。
家族での防災訓練
普段から地域の避難訓練や防災イベントに積極的に参加することもおすすめです。特に、乳幼児のいる家庭では「災害を想定したシミュレーション」が重要な意味を持ちます。子どもは親の思い通りに行動してくれなかったり、想定外のことが起きることが多々あります。
訓練内容の例
– 夜間の避難訓練
– 抱っこひもでの階段昇降練習
– 液体ミルクの使用練習
– 子どもとの避難ルート確認散歩
– 防災リュックを背負っての移動練習
地域とのつながりづくり
ご近所さんとの協力体制
乳幼児や医療が必要な子どもは、避難時にご近所の助けが必要です。誰に助けに来てもらえるか、あらかじめ決めておきましょう。
協力体制の築き方
– 自治会や町内会への積極的な参加
– 近隣の子育て世帯との情報交換
– 地域の防災訓練への参加
– 日頃からの挨拶や声かけ
子育て支援機関との連携
– 保健センターでの相談
– 子育て支援センターでの情報収集
– 小児科医との相談
– 地域の助産師や保健師との連携
まとめ:今すぐできる行動計画
赤ちゃんや乳幼児との防災対策は、一度にすべてを完璧に準備する必要はありません。普段使っているものを少し多めにストックしておくだけでも立派な防災になります。難しく考えすぎず、まずは命を守る、安全に逃げることを第一に避難グッズを用意してみましょう。
今週中にできること
1. 液体ミルクと使い捨て哺乳瓶を1週間分購入
2. 防災リュックを1つ購入して設置場所を決める
3. 家族で避難場所の確認
4. 近所の人との挨拶を始める
今月中にできること
1. 月齢に応じた防災グッズリスト37項目を揃える
2. 子どもと一緒に避難ルートを歩く
3. ローリングストック法を開始
4. 地域の防災訓練への参加申込み
継続的に行うこと
1. 3ヶ月ごとの備蓄品見直し
2. 月1回の家族防災会議
3. 季節ごとの避難訓練
4. 地域コミュニティへの参加
災害時の備えとは「非常時の環境をどれだけ普段の環境に近づけられるか」です。この言葉を胸に、お子さんの安全と安心を守るための準備を、今日から始めてみませんか?
災害はいつ起こるか分かりません。でも、しっかりとした準備があれば、きっと家族みんなで乗り越えることができます。大切な我が子を守るために、できることから一歩ずつ始めていきましょう。
皆さんの家族が、いざという時に安全に避難し、健康に過ごせることを心から願っています。防災は「もしも」のためではなく、「必ず」のための準備です。今こそ行動を起こしましょう。