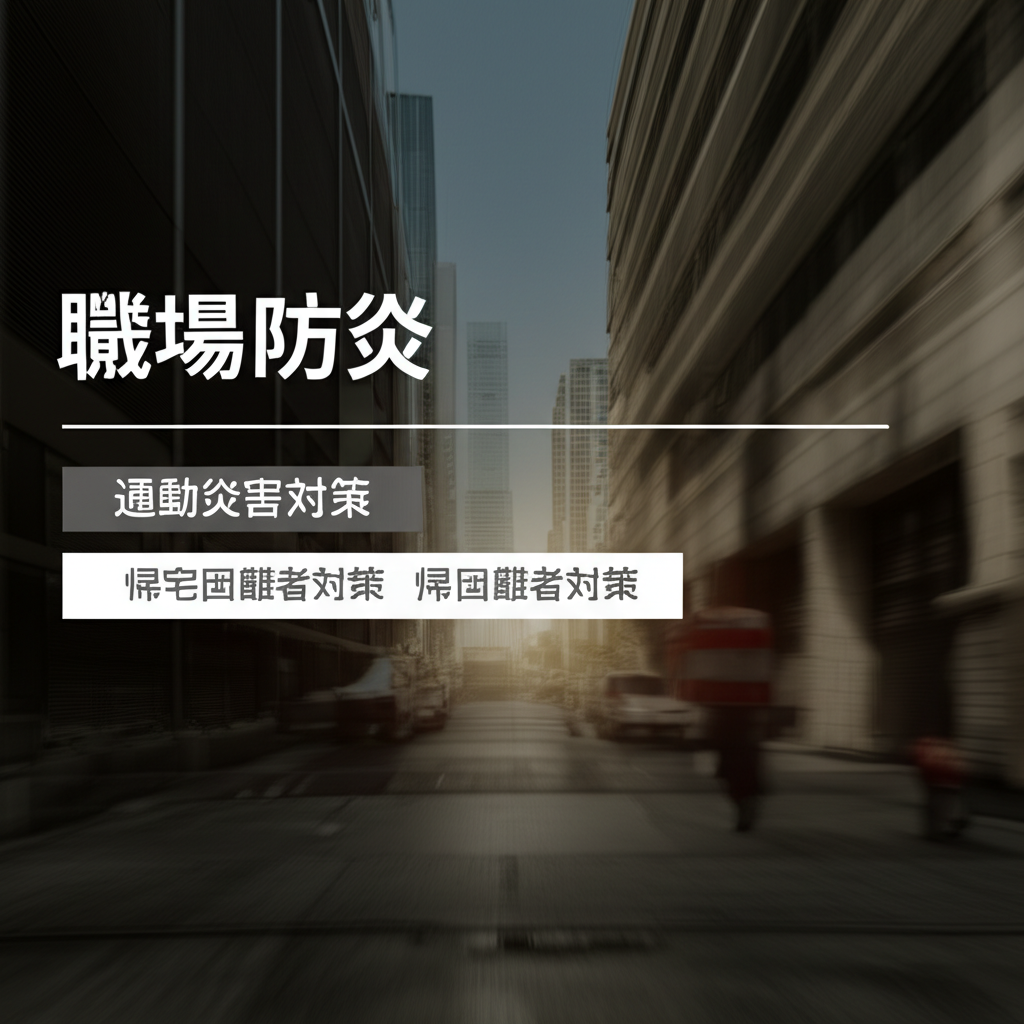
職場防災は家族を守る第一歩!災害時に備えた職場での対策が重要な理由
こんにちは!災害対策マニュアル.comです。日頃から家族の安全を気にかけている皆さんに、今回は「職場防災」について詳しくお話しします。
実は、災害は平日の昼間に発生する確率が高く、その時間帯は家族の大黒柱が職場にいることが多いんです。災害発生後は安全確認が取れるまで従業員等を3日程度安全なオフィス内に留めおくという政府の指針があるように、職場での災害対策は家族全体の安全に直結する重要な問題なのです。
東日本大震災の経験から学んだ教訓として、「むやみに移動しない」ことが基本姿勢として推奨されています。これは職場にいる家族が無理に帰宅を試みることで、かえって危険にさらされることを防ぐためです。
特に首都圏では、首都直下型地震では、東日本大震災当時の帰宅困難者数と近い、517万人の帰宅困難者の発生が想定されています。つまり、職場での防災対策は、もはや「準備しておけば安心」ではなく、「必須の生活スキル」となっているのです。
職場防災の基本:まずは職場の安全確認から始めよう
職場防災対策の第一歩:安全な職場環境の確保
職場防災の基本は、まず働く環境そのものの安全性を確保することです。家族が働く職場が災害に強いかどうかは、皆さんも気になるポイントですよね。
職場での安全確認チェックポイント:
1. 建物の耐震性確認
– 建物の築年数と耐震基準の確認
– 定期的な耐震診断の実施状況
– 非構造部材(天井、照明器具など)の落下防止対策
2. 避難経路の確認
– 複数の避難経路の把握
– 階段や非常口の位置確認
– 障害物のない避難経路の維持
3. 防災設備の点検
– 消火器の設置場所と使用方法
– 緊急時の連絡手段(非常ベルなど)
– AED(自動体外式除細動器)の設置場所
職場防災グッズの準備方法
防災グッズ・食糧を備蓄することは、企業の重要な責務です。しかし、個人レベルでも準備できることがあります。
個人デスクに常備したい防災グッズ:
– 懐中電灯:小型でLED式のもの
– 携帯ラジオ:手回し充電可能なタイプ
– 非常用の水:500mlペットボトル2本程度
– 非常食:カロリーメイトやビスケットなど
– 救急用品:絆創膏、常備薬など
– 防災用品:軍手、マスク、ホイッスル
– 現金:小銭を含む1万円程度
職場共用で準備したい備蓄品:
従業員向けの3日分の水、食料等の備蓄に努めることが企業の責務とされています。具体的には:
– 水:1人1日3リットル×3日分
– 食料:アルファ米、缶詰、乾パンなど
– 毛布:季節に応じた防寒具
– 医薬品:救急箱、持病の薬など
– 衛生用品:トイレットペーパー、ウェットティッシュなど
通勤災害対策:家族の安全な通勤を守る方法
通勤災害の現実と対策の必要性
交通労働災害は、労働者による死亡災害の約2割を占めており、そのうち6割以上が運輸交通業以外で発生していますという厚生労働省の統計からも分かるように、通勤中の災害は決して他人事ではありません。
通勤災害対策で重要なのは、「普段の通勤ルート」だけでなく、「災害時の代替ルート」を複数確認しておくことです。
通勤災害対策の具体的な方法
1. 複数の通勤ルートの確認
災害時には、普段使っている交通機関が停止する可能性があります。そのため、以下のルートを事前に確認しておきましょう:
– 主要ルート:普段の通勤ルート
– 代替ルート1:別の交通機関を使用するルート
– 代替ルート2:一部徒歩を含むルート
– 緊急ルート:完全徒歩での帰宅ルート
2. 通勤時の携帯品の見直し
災害時に役立つ通勤時の携帯品を見直しましょう:
– 歩きやすい靴:オフィスに置いておく
– 携帯電話の充電器:モバイルバッテリー
– 簡易雨具:折りたたみ傘やレインコート
– 現金:電子マネーが使えない場合に備えて
– 身分証明書:免許証や保険証のコピー
3. 職場との連絡体制の確立
災害時の連絡方法を複数確保しておくことが重要です:
– 緊急連絡先の共有:家族と職場の両方
– 災害用伝言板の活用:NTTの災害用伝言ダイヤル「171」
– SNSの活用:TwitterやFacebookの安否確認機能
– メール連絡:携帯メールと会社のメール
通勤災害対策の注意点
通勤災害対策を考える上で、以下の点に注意が必要です:
避けるべき行動:
– 災害直後の無理な移動
– 不安定な構造物の近くでの待機
– 情報収集を怠った状態での行動
– 単独での長距離移動
推奨される行動:
– 安全な場所での待機
– 正確な情報収集
– 家族との連絡確保
– 職場の指示に従った行動
帰宅困難者対策:災害時の安全な帰宅を実現する方法
帰宅困難者対策の基本的な考え方
災害発生後は安全確認が取れるまで従業員等を3日程度安全なオフィス内に留めおくという政府の方針があるように、帰宅困難者対策の基本は「むやみに移動しない」ことです。
しかし、家族の安全を考える主婦の立場としては、「3日間も連絡が取れない」という状況は非常に不安ですよね。だからこそ、事前の準備と正しい知識が重要なのです。
帰宅困難者対策の具体的な準備
1. 家族間での取り決め
災害時の行動について、家族間で以下の取り決めをしておきましょう:
– 集合場所の決定:自宅以外の避難場所
– 連絡方法の確認:複数の連絡手段
– 役割分担:誰が何を担当するか
– 重要書類の保管場所:保険証、通帳などの場所
2. 徒歩帰宅のためのルート確認
万が一、徒歩で帰宅する場合に備えて:
– 帰宅ルートの地図:紙の地図を職場に常備
– 休憩地点の確認:コンビニ、公園、公共施設
– 危険箇所の把握:崖、川、高架下など
– 帰宅支援ステーション:自治体が指定する休憩所
3. 職場での帰宅困難者対策
BCPに基づいて対応することで、災害発生後からできるだけ早いタイミングで重要な業務を復活させることができます。企業のBCP(事業継続計画)の中に、帰宅困難者対策が含まれているか確認しましょう。
帰宅困難者対策の実践的なコツ
安全な帰宅のための判断基準:
1. 気象情報の確認:二次災害の可能性
2. 交通情報の確認:公共交通機関の運行状況
3. 道路状況の確認:通行可能な道路の把握
4. 体調の確認:長距離歩行が可能かどうか
徒歩帰宅時の安全対策:
– 適切な服装:歩きやすい靴と動きやすい服装
– 水分補給:こまめな水分補給
– 休憩の取り方:30分歩いたら10分休憩
– 夜間の移動:できるだけ避ける
職場での安否確認システムの活用法
安否確認システムの重要性
安否確認システムの導入は、従業員や家族の安否を知るために重要な取り組みでもあります。現代の職場防災対策において、安否確認システムは欠かせない要素となっています。
家族ができる安否確認の方法
1. 災害用伝言板の活用
– NTT災害用伝言ダイヤル「171」
– 携帯電話各社の災害用伝言板
– インターネット災害用伝言板
2. SNSの安否確認機能
– Facebook:災害時安否確認機能
– Twitter:#安否確認 ハッシュタグ
– LINE:既読機能による安否確認
3. 職場との連絡体制
家族として知っておきたい職場の連絡体制:
– 緊急連絡先:職場の災害時連絡先
– 連絡のタイミング:いつ連絡すべきか
– 連絡方法:電話、メール、SNSなど
– 代理連絡:本人と連絡が取れない場合の対応
災害時の職場での適切な行動指針
災害発生時の初期対応
災害が発生した時の職場での適切な行動を、家族と共有しておくことが重要です。
地震発生時の行動:
1. 身の安全確保:机の下に隠れる
2. 火の始末:コンロやストーブの火を消す
3. 出口の確保:ドアを開けて避難経路を確保
4. 情報収集:ラジオやテレビで情報を確認
5. 安否確認:家族や職場への連絡
火災発生時の行動:
1. 火災の発見:「火事だ!」と大声で知らせる
2. 初期消火:安全な範囲で消火を試みる
3. 避難準備:消火が困難な場合は避難
4. 煙対策:姿勢を低くして煙を避ける
5. 避難実行:階段を使って避難
災害時の職場での待機方法
被害状況によっては国や各自治体と調整のうえ、3日目までに帰宅支援に移行することになるため、職場での適切な待機が重要です。
職場待機時の注意点:
– 水分補給:こまめな水分補給
– 体調管理:無理をしない
– 情報収集:正確な情報の入手
– 連絡確保:定期的な家族との連絡
家族全体での職場防災対策の連携
家族での防災会議の開催
職場防災対策は、家族全体で取り組むべき課題です。定期的に家族会議を開いて、以下の点を確認しましょう:
家族防災会議のチェックポイント:
1. 各自の職場の防災対策状況
2. 災害時の連絡方法と集合場所
3. 役割分担と責任範囲
4. 防災グッズの確認と補充
5. 避難場所とルートの確認
子どもの学校との連携
子どもがいる家庭では、学校との連携も重要です:
– 学校の防災対策:引き渡し方法の確認
– 通学路の安全確認:危険箇所の把握
– 緊急時の連絡方法:学校との連絡体制
– お迎えの方法:災害時の対応
高齢者がいる家庭での配慮
高齢者がいる家庭では、以下の点にも配慮が必要です:
– 避難支援の方法:介護が必要な場合の対応
– 薬の管理:常備薬の確保
– 近所との連携:地域のサポート体制
– 福祉避難所の確認:特別な配慮が必要な場合
実際の災害体験から学ぶ職場防災の教訓
東日本大震災での職場防災の実例
2011年3月11日に発生した東日本大震災では、多くの職場で防災対策の重要性が改めて認識されました。
成功事例:
– 事前の防災訓練:定期的な訓練が生きた職場
– 備蓄の充実:3日分の食料・水の確保
– 連絡体制の確立:家族との連絡が取れた企業
– 従業員の安全確保:無理な帰宅を制止した判断
課題となった点:
– 情報不足:正確な情報の入手困難
– 交通機関の停止:帰宅困難者の大量発生
– 通信障害:電話がつながらない状況
– 備蓄不足:想定を超える長期間の待機
熊本地震での職場防災の教訓
2016年の熊本地震では、建物の耐震性の重要性が再認識されました:
学んだ教訓:
– 建物の安全性確認:耐震基準の重要性
– エレベーターの停止:階段での避難の重要性
– ライフラインの停止:自家発電や非常用電源の必要性
– 地域との連携:近隣企業との相互支援
近年の水害での職場防災対策
近年頻発する水害でも、職場防災の重要性が認識されています:
水害時の職場対策:
– 浸水対策:重要書類の高所保管
– 避難判断:早めの避難決断
– 交通機関の影響:冠水による交通障害
– 在宅勤務の活用:事前の勤務体制変更
職場防災対策の定期的な見直しとメンテナンス
防災対策の定期点検
策定したBCPは、定期的に見直しを図りましょう。職場防災対策も同様に、定期的な点検と見直しが必要です。
月次点検項目:
– 防災グッズの確認:期限切れの交換
– 連絡先の更新:家族や職場の連絡先
– 備蓄品の補充:消費した分の補充
– 機器の動作確認:ラジオやライトの動作
年次点検項目:
– 避難ルートの確認:道路工事などによる変更
– ハザードマップの更新:最新版の確認
– 保険の見直し:火災保険や地震保険
– 防災訓練の実施:家族での避難訓練
職場防災対策の改善点
継続的な改善のために、以下の点を定期的に見直しましょう:
改善すべき点の例:
– 備蓄場所の見直し:アクセスしやすい場所への変更
– 連絡方法の多様化:新しい連絡手段の導入
– 家族の成長に合わせた対策:子どもの成長に応じた変更
– 職場環境の変化:転職や異動に伴う対策変更
まとめ:家族を守るための職場防災対策の重要性
職場防災対策は、単に個人の問題ではなく、家族全体の安全に関わる重要な取り組みです。災害はいつ発生するか分からないからこそ、普段からの準備と正しい知識が不可欠なのです。
「災害に強い企業」であることは、従業員から信頼を寄せられるだけでなく、顧客や取引先、地域住民からの信用にもつながります。これは同時に、そこで働く家族の安全と安心にも直結しています。
今日から始められる職場防災対策:
1. 職場の防災対策状況の確認
2. 個人レベルでの防災グッズの準備
3. 家族との連絡体制の確立
4. 複数の帰宅ルートの確認
5. 定期的な防災訓練の実施
災害に備えることは、決して大げさなことではありません。家族の安全と安心のために、今日から職場防災対策を始めてみませんか?
皆さんの家族が災害時にも安全で安心して過ごせるよう、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。災害対策は継続的な取り組みが重要です。定期的にこの記事を見返して、防災対策の見直しを行ってくださいね。
最後に、職場防災対策は一人で行うものではありません。家族、職場、地域全体で連携して取り組むことで、より効果的な災害対策が可能になります。皆さんの積極的な取り組みが、災害に強い社会づくりにつながることを願っています。





