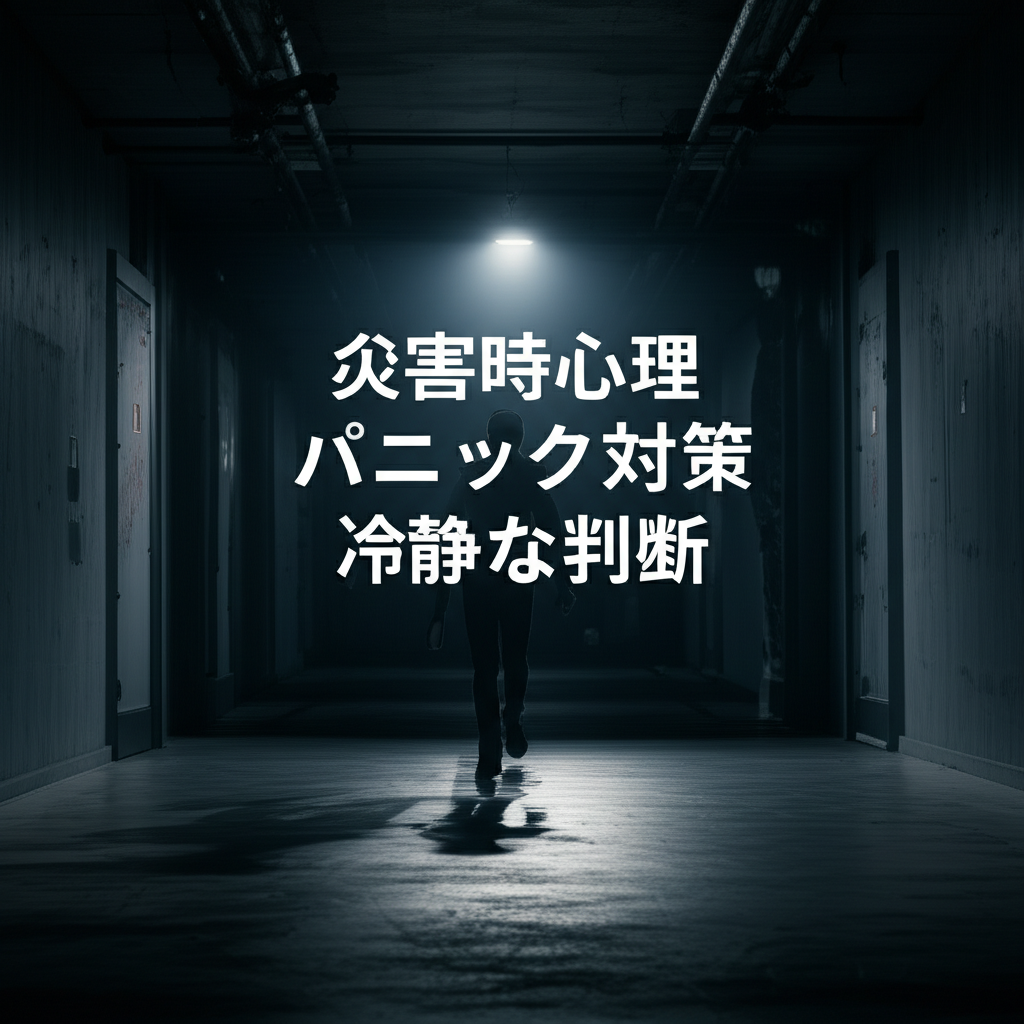
災害時に命を守る判断力を身につけよう
「もしも大地震が起きたら、私はちゃんと冷静に判断できるだろうか?」
多くの方がこのような不安を抱えているのではないでしょうか。実際、地震のときには多くの人が思考停止状態になり、この人たちは一部のパニック状態の人の行動につられてしまいがちです。
災害大国日本では、地震、津波、台風、洪水などの自然災害はいつ起こるかわかりません。そんな時、冷静な判断と適切な行動が生死を分けることもあります。しかし、人間は極限状態に置かれると、想像以上に冷静な判断ができなくなってしまうものです。
今回は、災害時の心理状態を理解し、パニックを防ぎながら冷静な判断をするための実践的な方法をお伝えします。家族を守るため、そして自分自身を守るために、ぜひ最後までお読みください。
災害時の心理状態を理解する
正常性バイアス:「大丈夫」という危険な思い込み
災害時に最も避けたい心理状態の一つが「正常性バイアス」です。正常性バイアスとは、予期してない出来事や目の前の危険に対し「自分なら大丈夫」「まさかそんな大災害なわけがない」という先入観によって、危険ではなく正常なことだと落ち着こうとする心の安定機能のようなものです。
この正常性バイアスは、無意識のうちに働いてしまうため、自覚がなくても何某かのバイアスで物事を見ていることが多くあります。日常生活では心を守る大切な機能なのですが、災害時には命に関わる危険な心理状態となってしまいます。
例えば、火災報知器が鳴っても「点検だろう」と思ったり、津波警報が出ても「まだ大丈夫」と思ったりするのは、まさに正常性バイアスの働きです。東日本大震災発生から3年後に、被災された方々へのインタビュー調査を行い、大津波発生時の心理や行動についてお話をうかがいました。その際に、地震発生後に海の様子を見に行った男性が、沖合から津波が迫ってくるのを目撃し、慌てて自転車で内陸に逃げながら『津波が来る!今すぐ逃げろ!』と大声で呼び掛けたにもかかわらず、多くの住民は聞く耳を持たない、中には『うるさい』などと言い返されたという実例もあります。
同調性バイアス:「みんなと同じ」という落とし穴
もう一つの危険な心理状態が「同調性バイアス」です。同調性バイアスとは、集団の中にいると、つい他者と同じ行動をとってしまう心の働きで、災害が発生しているにもかかわらず、「みんなが逃げていないから大丈夫だろう」と周囲の人の行動に合わせてしまうことです。
日本人は特にこの働きが強いと考えられており、本来であれば一目散に逃げるべき状況に置かれても、「誰も逃げてないから大丈夫だろう」と周りと同じ逃げない選択をする人が圧倒的に多いとされています。
実際、避難所での調査でも、「周りの人が避難していないから避難しなかった」という理由で逃げ遅れた人が多数確認されています。災害時には、この同調性バイアスが避難の遅れを招き、命に関わる危険な状況を作り出してしまうのです。
パニック対策の基本原則
事前準備でパニックを防ぐ
予期せぬ出来事でパニックになってしまうなら、日頃からさまざまな展開を想定しておくことで回避できると思いませんか。「もし職場や学校で地震に遭ったら」「家族がバラバラの状態で地震が起こったら」「遊びに行っている先や旅行先で…」など、さまざまなシチュエーションを想定して考えてみましょう。
具体的には、次のような準備を行いましょう:
1. 状況別の行動計画の策定
– 自宅にいる時
– 職場にいる時
– 外出中の時
– 家族が離れている時
2. 避難経路の確認
– 複数の避難経路を把握する
– 実際に歩いてみる
– 時間別の混雑状況を確認する
3. 情報収集手段の準備
– ラジオ、スマートフォン、テレビ
– 家族との連絡方法
– 地域の防災情報システム
状況と行動のパッケージ化
緊急時には、バイアスが生じる可能性のある「思考や判断」を行わせない、という考え方がある。この考えに基づき実行されるのが、「状況と行動のパッケージ化」だ。あらゆる災害に対してどのような危険があるかをイメージし、事前に行動計画をたて、そのための訓練を徹底的に行う──これにより、緊急時に「判断を介さず」すばやく行動を取ることができるようになるのです。
具体的な「状況と行動のパッケージ化」の例:
地震発生時のパッケージ
– 強い揺れを感じたら → 机の下に潜る
– 揺れが収まったら → 火の始末と出口の確保
– 避難指示が出たら → 迷わず指定避難場所へ
津波警報発令時のパッケージ
– 津波警報を聞いたら → 即座に高台へ避難
– 迷いや判断の時間を作らない
– 家族と合流は高台で
冷静な判断を支える心構え
率先避難者になる意識
災害発生後に誰も避難しようとしなければ、正常性バイアスや同調バイアスによって「きっと大したことない」「自分だけ逃げるのは大げさ」などといった認識が広がり、結果的に多くの人が被害に巻き込まれてしまう恐れがあります。
そこで重要なのが、率先して避難行動を起こし、周囲にも避難を呼びかけるようにしましょう。率先して避難を呼びかける人がいれば、周囲の人々に事の重大さが伝わり、早期避難につながりますという「率先避難者」の意識です。
率先避難者になるための心構え:
1. 「自分が先頭に立つ」という責任感
– 周りの様子を見てから動くのではなく、自分から動く
– 家族や近所の人に声をかけて一緒に避難する
2. 「恥ずかしがらない」勇気
– 避難が空振りでも構わない
– 命を守ることが最優先
3. 「リーダーシップを発揮する」覚悟
– 大きな声で避難を呼びかける
– 迷っている人の背中を押す
想像力を鍛える
小学生の頃に読んだ児童書のなかで、賢い主人公が「人は想像力である程度のことをカバーできる」といい、それを聞いた女の子は「想像力にそれだけの影響があれば、私はいじめられない!」と泣き叫ぶという場面がありました。
災害時においても、この想像力は非常に重要です。普段から「もしも」の状況を想像し、その時の対処法を考えることで、実際の災害時に冷静に対応できるようになります。
想像力を鍛える方法:
1. 日常的な「もしも」の想像
– 通勤途中で地震が起きたら?
– 買い物中に津波警報が鳴ったら?
– 子どもが学校にいる時に災害が起きたら?
2. 過去の災害事例の学習
– 東日本大震災や熊本地震での体験談を読む
– 災害時の映像資料を見る
– 被災者の証言を聞く
3. 防災訓練への積極的参加
– 地域の防災訓練に参加する
– 職場での避難訓練を真剣に行う
– 家族で避難経路を確認する
「釜石の奇跡」から学ぶ冷静な判断
冷静な判断が命を救った実例
東日本大震災で注目された「釜石の奇跡」は、まさに冷静な判断と適切な行動の重要性を示す事例です。海からわずか500m足らずの近距離に位置しているにもかかわらず、釜石市立釜石東中学校と鵜住居(うのすまい)小学校の児童・生徒、約570名は、地震発生と同時に全員が迅速に避難し、押し寄せる津波から生き延びることができました。
この成功の背景には、学生が「あらかじめ指定された避難場所が安全である」という先入観に引っ張られることなく、冷静に状況を判断し、安全な場所に避難した、正常性バイアスに打ち勝った事例ですがあります。
避難3原則の実践
釜石の児童・生徒たちが身に付けていた「避難3原則」:①想定にとらわれない ②状況下において最善をつくす ③率先避難者になるは、私たち大人にとっても重要な教訓です。
①想定にとらわれない
– ハザードマップや避難計画は参考程度に
– 実際の状況に応じて柔軟に判断する
– 「まさか」という思い込みを捨てる
②状況下において最善をつくす
– 完璧な状況を待たずに行動する
– 今できる最善の選択をする
– 迷っている時間があったら動く
③率先避難者になる
– 周りの様子を見ずに自分から動く
– 他の人も巻き込んで避難する
– リーダーシップを発揮する
実際の避難行動のポイント
これを見た小学校の児童は、日ごろから釜石東中学校と行っていた合同訓練を思い出し、自らの判断で校庭に駆け出しました。その後、児童・生徒は約500m先の高台にあるグループホーム「ございしょの里」まで避難しましたが、建物の裏の崖が崩れるのを見た生徒が教師にもっと高いところに避難しようと伝え、さらに高台の介護福祉施設「やまざき機能訓練デイサービスセンター」まで避難しました。
このように、一度避難した場所でも、より安全な場所があれば躊躇なく移動することが重要です。「もうここで十分」という思い込みが命取りになることもあります。
実践的なパニック対策メソッド
呼吸法による心の安定
災害時のパニックを防ぐために、日頃から実践できる呼吸法があります。
4-7-8呼吸法
1. 4秒かけて鼻から息を吸う
2. 7秒間息を止める
3. 8秒かけて口から息を吐く
この呼吸法を繰り返すことで、心拍数が安定し、冷静な判断ができるようになります。
腹式呼吸
1. 手をお腹に当てる
2. 鼻からゆっくり息を吸い、お腹を膨らませる
3. 口からゆっくり息を吐き、お腹をへこませる
情報収集と整理の方法
災害時は情報が錯綜し、正しい判断を阻害する要因となります。
信頼できる情報源の確認
– 気象庁の公式発表
– 地方自治体の防災情報
– NHKなどの公共放送
– 防災無線・防災メール
情報の整理方法
1. 複数の情報源で確認する
2. 時系列で情報を整理する
3. 自分の状況と照らし合わせる
4. 行動に必要な情報を抽出する
家族との連絡体制
災害時は通信が困難になることが多いため、事前に連絡体制を整えておくことが重要です。
連絡手段の多様化
– 携帯電話・スマートフォン
– 災害用伝言ダイヤル(171)
– 災害用伝言板(web171)
– SNS(Twitter、Facebook、LINE)
集合場所の決定
– 第一集合場所:自宅近くの避難所
– 第二集合場所:より安全な広域避難場所
– 連絡が取れない場合の行動を決めておく
心理的な準備と日頃の訓練
メンタルシミュレーション
災害時の冷静な判断のためには、頭の中で何度も災害時の状況をシミュレーションすることが効果的です。
シミュレーション項目
1. 地震発生時の初動対応
2. 避難経路の確認
3. 家族との合流方法
4. 避難所での生活
5. 復旧までの生活設計
定期的な防災訓練
冷静な判断をしていきましょうというためには、定期的な訓練が不可欠です。
家族での訓練
– 月1回の避難訓練
– 防災グッズの点検
– 連絡方法の確認
地域での訓練
– 地域防災訓練への参加
– 近所の人との連携確認
– 避難所運営の体験
ストレス耐性の向上
日頃からストレス耐性を高めておくことで、災害時でも冷静な判断ができるようになります。
ストレス耐性を高める方法
1. 規則正しい生活リズム
2. 適度な運動
3. 十分な睡眠
4. バランスの良い食事
5. リラクゼーション技術の習得
災害時の具体的な行動指針
地震発生時の行動
発生直後(0-1分)
– 机の下に潜る(DROP)
– 頭を守る(COVER)
– 揺れが収まるまで待つ(HOLD ON)
揺れが収まった後(1-5分)
– 火の始末
– 出口の確保
– 家族の安全確認
避難準備(5-15分)
– 避難の必要性を判断
– 必要最小限の荷物準備
– 近所の人との連携
津波警報発令時の行動
警報発令後(即座に)
– 迷わず高台へ移動
– 車は使わずに徒歩で避難
– 荷物は最小限に
避難中
– 周囲の人に声をかける
– より高い場所を目指す
– 津波到達時間を意識
避難所での行動
到着後
– 受付で名前を記録
– 家族の安否確認
– 避難所のルールを確認
避難生活中
– 避難所運営への協力
– 情報収集と整理
– 心のケアへの配慮
家族を守るためのリーダーシップ
家族内での役割分担
災害時に家族全員が冷静に行動するためには、事前に役割分担を決めておくことが重要です。
大人の役割
– 状況判断と避難決定
– 子どもの安全確保
– 近所への声かけ
子どもの役割
– 大人の指示に従う
– 兄弟の面倒を見る
– 決められた場所で待機
地域コミュニティとの連携
緊急時に声を上げ、たくさんの人をまとめられるリーダーになれるような人が増えれば、地震による被害を最小限に抑えられるでしょう。
地域での連携ポイント
1. 日頃からの近所付き合い
2. 防災訓練への参加
3. 要援護者の把握
4. 地域防災計画の理解
まとめ:今日から始める災害時心理対策
災害時の冷静な判断とパニック対策は、一朝一夕で身につくものではありません。しかし、正しい知識と継続的な準備により、必ず身につけることができます。
今日から始められること
1. 正常性バイアスと同調性バイアスの理解
– 「大丈夫」という思い込みの危険性を認識する
– 「みんなと同じ」行動の落とし穴を知る
2. 状況と行動のパッケージ化
– 災害種別ごとの行動計画を作成する
– 家族で避難経路を確認する
3. 率先避難者の意識を持つ
– 周りの様子を見ずに自分から動く
– 近所の人にも声をかける
4. 定期的な訓練の実施
– 月1回の家族避難訓練
– 地域防災訓練への参加
災害はいつ起こるかわかりません。しかし、適切な準備と心構えがあれば、必ず家族を守ることができます。今日から、一つずつでも実践していきましょう。
皆さんの命と大切な家族の命を守るために、この記事の内容を参考に、ぜひ災害時の心理対策と冷静な判断力を身につけてください。防災は特別なことではなく、日常の延長線上にあることを忘れずに、継続的な取り組みを心がけましょう。





